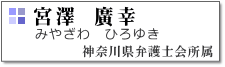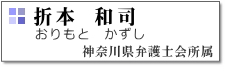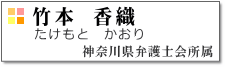еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһгғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒ®гҒҠи©ұ
гғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒЁгҒ„гҒҶз–ҫз—…гӮ’гҒ”еӯҳзҹҘгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
гғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғігҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜдәәгҒ®еҗҚеүҚгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҢ»еӯҰзҡ„гҒӘиЎЁзҸҫгҒ§гҒҜгҖҢйҳ»иЎҖжҖ§жӢҳзё®гҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
иӮҳгҒ®е‘ЁиҫәгҒ®йӘЁжҠҳгҒӘгҒ©гҒ®гҒӮгҒЁгҒ«гҖҒеҶ…еҮәиЎҖгӮ„ең§иҝ«гҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰй–үйҺ–гҒ•гӮҢгҒҹзӯӢиӮүгғ»зҘһзөҢгғ»иЎҖз®ЎгҒ®зө„з№”гҒ®еҶ…ең§гҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҖҒеҫӘз’°дёҚе…ЁгӮ’жқҘгҒ—гҖҒзӯӢиӮүгҒ®зө„з№”гҒҢеЈҠжӯ»гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒжң«жўўзҘһзөҢгҒҢйә»з—әгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ—гҒҰиӮҳгҒӢгӮүжүӢжҢҮгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®жӢҳзё®гӮ„зҘһзөҢйҡңе®ігӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгӮӢз–ҫз—…гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзү№гҒ«гҖҒе°Ҹе…җгҒ®дёҠи…•йӘЁйЎҶдёҠйӘЁжҠҳгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘеҗҲдҪөз—ҮгҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӢгҒӘгӮҠеүҚгҒ«жүұгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжңҖиҝ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ“гҒ®з–ҫз—…гҒ«й–ўгҒҷгӮӢзӣёи«ҮгӮ’д№…гҖ…гҒ«еҸ—гҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе°‘гҒ—гҒҠи©ұгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҘеүҚгҒ«жүұгҒЈгҒҹгғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒҜиЈҒеҲӨгҒ«гҒҫгҒ§иҮігҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®йҡӣгҒ«йқһеёёгҒ«еҚ°иұЎгҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдәҢгҒӨгҒ»гҒ©гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҒзҘһеҘҲе·қзңҢгҒ“гҒ©гӮӮеҢ»зҷӮгӮ»гғігӮҝгғјгҒ®гғҷгғҶгғ©гғіеҢ»её«гҒЁйқўи«ҮгҒ—гҒҹжҷӮгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
иў«е®іиҖ…гҒҜе°ҸеӯҰз”ҹгҒ®еӯҗдҫӣгҒ•гӮ“гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж ЎеҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒӢгӮүгғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеҲҘгҒ®еҢ»её«гҒҢж°—д»ҳгҒ„гҒҰгҒҷгҒҗгҒ«гҒ“гҒ©гӮӮеҢ»зҷӮгӮ»гғігӮҝгғјгҒ«йҖҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еј•гҒҚеҸ—гҒ‘гҒҹгҒ“гҒ©гӮӮеҢ»зҷӮгӮ»гғігӮҝгғјгҒ®еҢ»её«гҒҜгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«зӯӢзө„з№”гҒҢеЈҠжӯ»гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҒҷгҒҗгҒ«жүӢиЎ“гҒ«е…ҘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйқўи«ҮгҒ®йҡӣгҒ«дјәгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҖҒгғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒЁиҒһгҒ„гҒҰиӢҘгҒ„еҢ»её«гҒҢеӨ§еӢўгҖҒгҒқгҒ®еӯҗгҒ®жүӢиЎ“гӮ’иҰӢгҒ«жқҘгҒҹгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒҜгҖҒж•ҙеҪўеӨ–科гҒ®й ҳеҹҹгҒ§гҒҜгӮҲгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҹеҗҲдҪөз—ҮгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ©гӮӮеҢ»зҷӮгӮ»гғігӮҝгғјгҒ®еҢ»её«гҒ«иЁҖгӮҸгҒӣгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢеҢ»её«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®пјЎпјўпјЈгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғ¬гғҷгғ«гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжҷ®йҖҡгҒ«ж°—гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰжІ»зҷӮгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°иө·гҒҚгҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ гҒӢгӮүгҖҒгӮ»гғігӮҝгғјгҒ®иӢҘгҒ„еҢ»её«гӮүгҒҜи¬ӣеӯҰдёҠгҒҜзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ‘гӮҢгҒ©е®ҹйҡӣгҒ«иҰӢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒқгҒ®гҒҸгӮүгҒ„еҹәжң¬дёӯгҒ®еҹәжң¬гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®дәӢ件гҒ®жҷӮгҒ®еҢ»её«гҒ®еҲқжӯ©зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҖҒеҸ—дҝЎжҷӮгҒ«ж•ҙеҫ©гҒ®еҮҰзҪ®гӮ’гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«гӮ®гғ—гӮ№гӮ’е·»гҒ„гҒҰеё°е®…гҒ•гҒӣгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹпјҲе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®з—ӣгҒҝгҒӘгҒ©гҒ®и«ёз—ҮзҠ¶гҒ®иЁҙгҒҲгӮ’и»ҪиҰ–гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгғҹгӮ№гӮӮйҮҚеӨ§гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢпјүгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒйӘЁжҠҳзӣҙеҫҢгҒҜгҖҒйӘЁжҠҳйғЁдҪҚгҒҢи…«и„№гҖҒгҒӨгҒҫгӮҠи…«гӮҢгҒҰиҶЁгӮүгҒҝгӮ„гҒҷгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮжңҹгҒ®гӮ®гғ—гӮ№еӣәе®ҡгҒҜең§гҒҢеӨ–гҒ«йҖғгҒ’гҒҡгҖҒеҶ…ең§гӮ’дёҠжҳҮгҒ•гҒӣгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒйҳ»иЎҖгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®дәӢ件гҒҜгҖҒеҢ»её«гҒ®йҒҺеӨұгҒҜжҳҺзҷҪгҒ§гҖҒжң¬жқҘдәүгҒҶдҪҷең°гҒ®гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒҢиІ¬д»»гӮ’еҗҰе®ҡгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүиЈҒеҲӨгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гӮӮгҒҶдёҖгҒӨиЁҳжҶ¶гҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒқгҒ®иЈҒеҲӨгҒЁдёҰиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒҶ1件гҒ®еҢ»зҷӮйҒҺиӘӨиЈҒеҲӨгҒ®дёӯгҒ§гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒЎгӮүгҒ®дәӢ件гӮӮгӮ„гҒҜгӮҠйӘЁжҠҳеҫҢгҒ®еҜҫеҮҰгҒҢе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӨҡе°‘ж—©гҒҸйҖІиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒиў«е‘ҠгҒ®еҢ»её«гҒ®е°Ӣе•ҸгӮӮе…ҲиЎҢгҒ—гҒҰе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®е°Ӣе•ҸгҒ®йҡӣгҖҒдәӢ件гҒ®дәүзӮ№гҒЁзӣҙжҺҘй–ўдҝӮгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгӮүи©ұгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҖҒеүҚжҸҗиіӘе•ҸгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„ҹгҒҳгҒ§гӮ®гғ—гӮ№еӣәе®ҡгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиіӘе•ҸгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®еҢ»её«гҒҜгҖҒгҖҢйӘЁжҠҳеҪ“ж—ҘгҒҜгӮ®гғ—гӮ№еӣәе®ҡгҒҜгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖҚгҒЁгҒӮгҒЈгҒ•гӮҠзӯ”гҒҲгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
иў«е‘ҠгҒ®еҢ»её«гҒ«гҖҒгҒӘгҒңгҒӢгҒЁгҒқгҒ®зҗҶз”ұгӮ’е°ӢгҒӯгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҖҢгғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҜгҒҫгҒҡгҒ„гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖҚгҒЁжҳҺзўәгҒ«зӯ”гҒҲгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е’„е—ҹгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®дҫӣиҝ°иӘҝжӣёгӮ’гғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒ®ж–№гҒ®иЈҒеҲӨгҒ«иЁјжӢ гҒ§еҮәгҒқгҒҶгҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒҸгӮүгҒ„гҖҒгҒ©гӮ“гҒҙгҒ—гӮғгӮҠгҒ®еӣһзӯ”гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
зөҗеұҖгҖҒгғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒ®иЈҒеҲӨгҒ®ж–№гҒҜе°Ӣе•ҸгҒ«гҒҫгҒ§иҮігӮүгҒҡгҖҒдё»ејөж®өйҡҺгҒ§жңүиІ¬еүҚжҸҗгҒ§гҒ®е’Ңи§ЈгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®дҫӣиҝ°иӘҝжӣёгӮ’иЁјжӢ гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдёҰиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиЈҒеҲӨгҒ®дёӯгҒ§гҒ®еҮәжқҘдәӢгҒ§гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒйқһеёёгҒ«иЁҳжҶ¶гҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
жңҖеҫҢгҒ«гҖҒгғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒ®зҷәз—ҮгӮ’гҒ„гҒӢгҒ«гҒ—гҒҰйҳІгҒҗгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҠи©ұгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒҜгҖҒе°Ҹе…җгҒ®дёҠи…•йӘЁйӘЁжҠҳгҒ§жҷӮжҠҳиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒиЈҒеҲӨгҒ«гҒҫгҒ§иҮігҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮӮгҒӢгҒӘгӮҠгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЈҒеҲӨгҒ®еӢқгҒЎиІ гҒ‘гҒЁгҒ„гҒҶи©ұгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжӮЈиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜжүӢй–ўзҜҖгӮ„жҢҮгҒӘгҒ©гҒ®дјёеұ•гҖҒеұҲжӣІеҲ¶йҷҗгҒҢж®ӢгӮүгҒӘгҒ„ж–№гҒҢгҒ„гҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒж•ҷиЁ“гҒЁгҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒгғ•гӮ©гғ«гӮҜгғһгғіжӢҳзё®гҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒйӘЁжҠҳеҪ“ж—ҘгҒ®гӮ®гғ—гӮ№гҒҜйҒҝгҒ‘гӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҒ—гҖҒеҢ…еёҜгҒӘгҒ©гҒ§гӮӮгҒҚгҒӨгҒҸе·»гҒ‘гҒ°йҳ»иЎҖгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе®ҹйҡӣгҖҒгӮ®гғ—гӮ№гӮ„еҢ…еёҜгӮ’е·»гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгӮӮгҒ—гҖҒз—ӣгҒҝгӮ„еӢ•гҒҚгҒҢжӮӘгҒ„гҖҒйә»з—әгҒӘгҒ©гҒ®з—ҮзҠ¶гҖҒзҲӘгҒ®иүІгҒӘгҒ©гҒ«гӮӮжіЁж„ҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒ§гӮӮгҒҠгҒӢгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгӮүгҒҷгҒҗгҒ«еҢ»иҖ…гҒ«иЎҢгҒҸгҒ№гҒҚгҒ гҒ—гҖҒж·ұеӨңгҒ«з—ҮзҠ¶гҒҢжӮӘеҢ–гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгҒҷгҒҗгҒ«еҢ»иҖ…гҒ«жҺӣгҒӢгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒзҙ дәәгҒ«гҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢеҲӨж–ӯгҒ®йӣЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҢ»её«гҒ®еҲӨж–ӯгӮ’еҫ…гҒҹгҒҡгҒ«зӣҙгҒЎгҒ«гӮ®гғ—гӮ№гӮ„еҢ…еёҜгӮ’еҸ–гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжұәж–ӯгӮӮжҷӮгҒ«еҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ©гӮӮеҢ»зҷӮгӮ»гғігӮҝгғјгҒ®еҢ»её«гӮӮгҖҒйҳ»иЎҖе…ҶеҖҷгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮүгҖҒгҖҢгғҗгӮ«гғғгҖҚгҒЁй–ӢгҒ‘гҒӘгҒҚгӮғгҒ гӮҒгҒ гҒЁдҪ•еәҰгӮӮгҒҠгҒЈгҒ—гӮғгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ„гҒҶеұҖйқўгҒ«еҮәгҒҸгӮҸгҒ—гҒҹж–№гҒҜгҖҒгҒҸгӮҢгҒҗгӮҢгӮӮж°—гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®гҒҠи©ұпҪһеҗҲдҪөз—ҮгҒЁеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨ
еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгҒҹеҫҢгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒӢгӮүгҖҢжүҝи«ҫжӣёгҒ®дёӯгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҹеҗҲдҪөз—ҮгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҢ»зҷӮгғҹгӮ№гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиӘ¬жҳҺгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®иӘ¬жҳҺгҒҜгҖҒеҺіеҜҶгҒ«гҒ„гҒҲгҒ°дёҚжӯЈзўәгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒйҒәжҶҫгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҷӮгҒ«еҢ»зҷӮеҒҙгҒҢж„Ҹеӣізҡ„гҒ«гҖҒеҢ»зҷӮгғҹгӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зіҠеЎ—гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиӘ¬жҳҺгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
д»Ҡж—ҘгҒҜгҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҝ°гҒ№гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮӮгҒқгӮӮгҖҒеҗҲдҪөз—ҮгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҜгҖҒгӮ„гӮ„еӨҡзҫ©зҡ„гҒ§гҖҒжӣ–жҳ§гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зү№е®ҡгҒ®з—…ж°—гҒ«й–ўйҖЈгҒ—гҒҰиө·гҒҚгӮӢз–ҫз—…гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’еҗҲдҪөз—ҮгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒӢеҗҰгҒӢгҒ®иҰізӮ№гҒ§гҒ®еҲҶйЎһгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒжүӢиЎ“гӮ„жӨңжҹ»зӯүгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«гҖҒгҒқгҒ®й–ўйҖЈгҒ§иө·гҒҚгӮӢз–ҫз—…гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§з”ЁгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®е®ҡзҫ©гӮ’иёҸгҒҫгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒеҗҲдҪөз—ҮгҒҢеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгҒҜгҖҒеҗҲдҪөз—ҮгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҒқгҒ®еҫҢгҒ«з¶ҡгҒҸжӮӘгҒ„зөҗжһңгҒҢеҢ»зҷӮиҖ…гҒ®гғҹгӮ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҷәз”ҹгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢеҗҰгҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұәгҒҫгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒжүҝи«ҫжӣёгҒ®дёӯгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢеҗҰгҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұәгҒҫгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒй–ӢиғёгҖҒй–Ӣи…№зӯүгҒ®жүӢиЎ“гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гҖҒдё»иҰҒиЎҖз®ЎгӮ’жҗҚеӮ·гҒ—гҒҰжӯ»дәЎгҒ«иҮігҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶз—ҮдҫӢгӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
иЎҖз®ЎгҒ®жҗҚеӮ·гӮ„гҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮӢеҮәиЎҖиҮӘдҪ“гҒҜгҖҒйҖҡеёёгҖҒжүҝи«ҫжӣёгҒ®дёӯгҒ«еҗҲдҪөз—ҮгҒЁгҒ—гҒҰиЁҳијүгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®дё»иҰҒиЎҖз®ЎгҒ®жҗҚеӮ·гҒҢеҢ»зҷӮиҖ…гҒ®гғҹгӮ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз”ҹгҒҳгҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®еҜҫеҮҰгҒ«еҢ»зҷӮиҖ…гҒ®гғҹгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжӮӘгҒ„зөҗжһңгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒиЎҖз®ЎгҒ®жҗҚеӮ·гӮ„гҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮӢеҮәиЎҖиҮӘдҪ“гҒҢгҖҒжүҝи«ҫжӣёгҒ®дёӯгҒ«еҗҲдҪөз—ҮгҒЁгҒ—гҒҰиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҪ“然гҒ«еҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒҜжі•зҡ„иІ¬д»»гӮ’иІ гӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒжүӢиЎ“гҒӘгҒ©гҒ®еҫҢгҒ«з”ҹгҒҳгҒҹжӮӘгҒ„зөҗжһңгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮгғҹгӮ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз”ҹгҒҳгҒҹгӮӮгҒ®гҒӢеҗҰгҒӢгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҢжүӢиЎ“гҒ®жүҝи«ҫжӣёгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҹеҗҲдҪөз—ҮгҒ®зҜ„з–ҮгҒ«еұһгҒҷгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶеҢәеҲҶиҮӘдҪ“гҒҜгҖҒжі•зҡ„иІ¬д»»гҒ®жңүз„ЎгӮ’еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҒҜдҪ•гҒ®ж„Ҹе‘ігӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒдәӢж•…еҫҢгҒ«гҖҒеҢ»её«гҒӢгӮүиӘ¬жҳҺгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒеҗҲдҪөз—ҮгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒ«жғ‘гӮҸгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒгҒӘгҒңжӮӘгҒ„зөҗжһңгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгҒ“гҒ«еҢ»зҷӮеҒҙгҒ®гғҹгӮ№гҒҢд»ӢеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶиҰізӮ№гҒ§гҖҒиӘ¬жҳҺгҒ®е ҙгҒ«иҮЁгҒҝгҖҒдәӢж•…гӮ’жӨңиЁјгҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢиӮқиҰҒгҒӘгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ