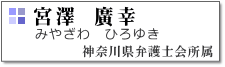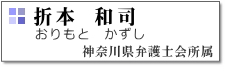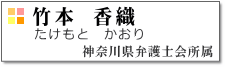еҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
жҳЁе№ҙгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҹеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ§иЁјжӢ дҝқе…ЁжүӢз¶ҡгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹдәӢ件гҒҜ3件гҒ»гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®зӣёи«ҮгӮ„еҸ—д»»гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжңҖиҝ‘гҒҜиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒд»»ж„Ҹй–ӢзӨәжүӢз¶ҡгҒ§е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгӮ«гғ«гғҶгӮ’жҢҒеҸӮгҒ•гӮҢгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁжүӢз¶ҡгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜд»ҘеүҚгӮҲгӮҠгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҸ—д»»жҷӮзӮ№гҒӢгӮүгӮ«гғ«гғҶгҒ®е…ҘжүӢгӮ’е§ӢгӮҒгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒж•ўгҒҲгҒҰжүӢй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒҫгҒ§е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰиЁјжӢ дҝқе…ЁжүӢз¶ҡгҒ®е®ҹж–ҪгҒ«иҮігӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҜеҝ…然зҡ„гҒ«жёӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒиҝ·гҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒеҫҢйЎ§гҒ®жҶӮгҒ„гӮ’гҒӘгҒҸгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮгҖҒж…ҺйҮҚгӮ’жңҹгҒ—гҒҰиЁјжӢ дҝқе…ЁгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгӮҲгҒ„гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҖҒгҒқгҒҶеҠ©иЁҖгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒҜиІ»з”ЁгӮӮдҪҷеҲҶгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒиІ»з”ЁеҜҫеҠ№жһңгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒгҒқгҒ®еҫ—еӨұгӮ’еҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҳЁе№ҙе®ҹж–ҪгҒ—гҒҹиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®еҶ…гҒ®пј‘件гҒҜгҖҒд№…гҖ…гҒ®жүӢжӣёгҒҚгӮ«гғ«гғҶгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ«гҒҜйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶзү№жңүгҒ®еӨ§еӨүгҒ•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжүӢжӣёгҒҚгӮ«гғ«гғҶгҒҜеҶҷзңҹж’®еҪұгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…然еӨҡгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҲҶйҮҸгҒ«гӮӮгӮҲгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдҪңжҘӯзҡ„гҒ«гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠеӨ§еӨүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгӮӮгҖҒеҪ“и©ІеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢиЁәзҷӮгҒ®жңҹй–“гӮ’еҢәеҲҮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҮәгҒҰгҒҚгҒҹжӨңжҹ»з”ЁзҙҷпјҲгӮ«гғ«гғҶгҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҒҜгҖҒжҷӮй–“зҡ„гҒӘй Ҷз•ӘгҒҢгӮҒгҒЎгӮғгӮҒгҒЎгӮғгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӘгҒҠгҒ•гӮүдҪҷеҲҶгҒ«жүӢй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒ3件гҒЁгӮӮиЁјжӢ дҝқе…ЁгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒзңҹзӣёи§ЈжҳҺгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжғ…е ұгҒҢе…ҘжүӢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®йҒёжҠһгҒҢжӯЈгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҲгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒиІ»з”ЁгҒ®гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“д»»ж„Ҹй–ӢзӨәгҒ§е…ҘжүӢгҒ—гҖҒз–‘е•ҸгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ«з§»иЎҢгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж”№гҒ–гӮ“гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒЁгҒ®е…јгҒӯеҗҲгҒ„гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгӮұгғјгӮ№гғҗгӮӨгӮұгғјгӮ№гҒ§еҲӨж–ӯгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жҳЁе№ҙгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ§гҒҜгҖҒгғҷгғҶгғ©гғігҒ®дҝЎй јгҒ§гҒҚгӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒ®ж–№гҒ«гӮ«гғЎгғ©гғһгғігӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
йҠҖеЎ©гӮ«гғЎгғ©гҒ®жҷӮд»ЈгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгғ—гғӯгҒ®гӮ«гғЎгғ©гғһгғігҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒд»ҠгҒ®жҷӮд»ЈгҒҜгҖҒеҶҷзңҹгҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгӮӮгғҮгӮёгӮ«гғЎгғҮгғјгӮҝгӮ’гҒқгҒ®е ҙгҒ§зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгғ—гғӯгҒ®гӮ«гғЎгғ©гғһгғігҒ§гҒӮгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҫгҒ—гҒҰгӮ„йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®д»•зө„гҒҝгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҹж®өеҸ–гӮҠгӮ’иёҸгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгӮ„гҖҒгғ‘гӮҪгӮігғідёҠгҒ§еҝ…иҰҒгҒӘжғ…е ұгҒ®зўәиӘҚгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®ж–№гҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®зөҢйЁ“гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғ‘гӮҪгӮігғідёҠгҒ§йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ§гҒҚгӮӢдәәгҒҢгғҷгӮ№гғҲгғҒгғ§гӮӨгӮ№гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒҜгҖҒдёҖжңҹдёҖдјҡгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒгғҜгғігӮўгғігғүгӮӘгғігғӘгғјгҒ®ж©ҹдјҡгҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒж„Ҹеӣізҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒӢгҒҜгҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒҢеҮәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜдёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮұгғјгӮ№гҒҜжұәгҒ—гҒҰе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгӮҲгӮҠгҒқгҒ®еӮҫеҗ‘гҒҢеј·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮӮж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒдҝқе…ЁгҒ®зҸҫе ҙгҒ§гҒҜгҖҒеҝ…иҰҒгҒӘиіҮж–ҷгӮ’жјҸгӮҢгҒӘгҒҸжҠјгҒ•гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶйӣҶдёӯгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠзө„гҒҫгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҲҶгҖҒзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгӮүз–ІгӮҢжһңгҒҰгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒӘгӮҠгҒ®зү№еҫҙгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒгғқгӮӨгғігғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰжүӢз¶ҡгҒ«иҮЁгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢиӮқиҰҒгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһиүҜгҒ„еҚ”еҠӣеҢ»гҖҒй‘‘е®ҡеҢ»гҒ«еҮәдјҡгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«Partпј‘
гҒ“гҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§гӮӮдҪ•еәҰгҒӢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮиЁҙиЁҹгҒ§жңҖгӮӮеӨ§еӨүгҒӘжҙ»еӢ•гҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҒз§Ғзҡ„й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгӮ’е°Ӯй–ҖеҢ»гҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҖҒдҪңжҲҗгҖҒгҒқгҒ—гҒҰиЈҒеҲӨжүҖгҒёгҒ®жҸҗеҮәгҒ«жј•гҒҺгҒӨгҒ‘гӮӢгҒҫгҒ§гҒ®жүӢй–“жҡҮгҒ§гҒҷгҖӮ
е…ғгҖ…гҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒӘиіҮж–ҷгҒҜеҢ»зҷӮеҒҙгҒ«еҒҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдёӯгҖҒеҺҹе‘ҠгҒҜеҢ»зҷӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜзҙ дәәгҒ®дёҖиҲ¬дәәгҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒиў«е‘ҠгҒҜеҢ»зҷӮгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ гҒЁгҒ„гҒҶгғҸгғігғҮгӮЈгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«дәӢ件гӮ’жүұгҒЈгҒҰиЎҢгҒҸдёӯгҒ§гҒ„гҒҶгҒЁгҖҒзҜҖзӣ®зҜҖзӣ®гҒ§дәӢ件гҒ®й ҳеҹҹгҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гҒ®еҚ”еҠӣгӮ’еҫ—гҒҰгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘеҠ©иЁҖгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҖҒгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгҒҫгҒ§еҚ”еҠӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒҫгҒ§гҒҢжң¬еҪ“гҒ«иӢҰеҠҙгҒ®йҖЈз¶ҡгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»её«гҒ®еҚ”еҠӣгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гӮӮгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ«гҒҜгҖҒдәӢ件еҪ“дәӢиҖ…гҒ®еҢ»её«гҖҒгҒқгҒ®жүҖеұһз—…йҷўгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜдҝқйҷәдјҡзӨҫгҒ®гғ«гғјгғҲгҒ§еҚ”еҠӣгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢеҢ»её«гӮ’зўәдҝқгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ«гҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғ«гғјгғҲгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ®зӮ№гҒ®гғҸгғігғҮгӮЈгҒҜгҒ•гӮүгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮеҪ“и©ІдәӢж•…гҒ®й ҳеҹҹгҒ§гғ”гғігғқгӮӨгғігғҲгҒ§еҚ”еҠӣгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢеҢ»её«гҒ«иҫҝгҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮжұәгҒ—гҒҰзЁҖгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзҸҫе®ҹгҒ®иЈҒеҲӨгҒ§гҒҜгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҸгғігғҮгӮЈгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүзҹҘгӮүгҒҡгҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒЁгҒҜй–ўдҝӮгҒӘгҒҸгҖҒеҺҹе‘ҠеҒҙгҒ«еҢ»еӯҰзҡ„гҒӘз«ӢиЁјжҙ»еӢ•гӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹжә–еӮҷгҒҜжҸҗиЁҙеүҚгҒ®ж®өйҡҺгҒ§иЎҢгҒЈгҒҰгҒ§гҒҚгӮӢйҷҗгӮҠгҒҠгҒҸгҒ№гҒҚгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®иЈҒеҲӨгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘгҒ«е‘ЁеҲ°гҒ«жә–еӮҷгӮ’гҒ—гҒҹгҒӨгӮӮгӮҠгҒ§гӮӮгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒӢгӮүжҖқгҒ„гҒҢгҒ‘гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘеҢ»еӯҰзҡ„дё»ејөгҒҢйЈӣгҒіеҮәгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжҷ®йҖҡгҒ«иө·гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгҒқгҒ®дё»ејөгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰеҢ»еӯҰзҡ„еҸҚи«–гӮ’иЎҢгӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«е°Ӯй–ҖеҢ»гҒ®еҚ”еҠӣгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹ次第гҒ§гҖҒиЁҙиЁҹгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҰд»ҘйҷҚгҒ«е°Ӯй–ҖеҢ»гҒӢгӮүж–°гҒҹгҒӘеҠ©иЁҖгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгӮ’дҫқй јгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒ”гҒҸжҷ®йҖҡгҒ«иө·гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ®еҢ»зҷӮиЈҒеҲӨгҒ§гҖҒиЈҒеҲӨдёӯгҒ«з§Ғзҡ„й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгӮ’дҫқй јгҒ—гҖҒжҸҗеҮәгҒ«жј•гҒҺгҒӨгҒ‘гҒҹдҪ“йЁ“пјҲиӢҰеҠҙи©ұпјүгӮ’гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ”зҙ№д»ӢгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒд»ҠеӣһгҒ®иЁҳдәӢгҒҜжҸҗиЁҙеүҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжҸҗиЁҙеҫҢгҒ«гғ•гӮ©гғјгӮ«гӮ№гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҸҗиЁҙеүҚгҒ гҒЁгҖҒз„ЎйҷҗгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®дёҖе®ҡзЁӢеәҰжҷӮй–“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҸҗиЁҙеҫҢгҒҜж¬Ўеӣһжңҹж—ҘгӮ„жҸҗеҮәжңҹйҷҗгҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒйҷҗгӮүгӮҢгҒҹжңҹй–“гҒ§й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёдҪңжҲҗгҒ«гҒҫгҒ§жҢҒгҒЈгҒҰиЎҢгҒҸиӢҰеҠҙгҒҜгҖҒжҸҗиЁҙеүҚгҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгӮӮгҒӮгӮҢгҖҒгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжңҖеҫҢгҒҜгҖҢеҪ“гҒҹгҒЈгҒҰз •гҒ‘гӮҚпјҒгҖҚпјҲз •гҒ‘гҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢпјүгҒ®зІҫзҘһгҒҢиӮқеҝғгҒЁгҒ„гҒҶзөҗи«–гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰеҢ»зҷӮдәӢ件гӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҖҒзӣёи«ҮгҒ§гҒҚгӮӢеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒЁгҒ®дҝЎй јй–ўдҝӮгӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒдёҖгҒӨдёҖгҒӨгҒ®дәӢ件гҒ®ж§ҳгҖ…гҒӘеұҖйқўгҒ§еҢ»её«гҒӢгӮүгҒ®йҒ©еҲҮгҒӘеҠ©иЁҖгӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иӢҰеҠҙгҒҜе°ҪгҒҚгҒҡгҖҒгҒқгӮҢгӮҶгҒҲгҖҒгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢгҒЁзҹҘжҒөгӮ’зөһгӮҠгҖҒиүҜгҒ„еҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒ«еҮәдјҡгҒҶгҒҹгӮҒгҒ®еҠӘеҠӣпјҲеӨұж•—гӮӮеҗ«гӮҒгҒҰпјүгӮ’з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҒҰгҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҠжӮ©гҒҝгҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒҢгҒҠгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгӮүгҖҒеӨҡе°‘гҒӘгӮҠеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
е°Ӯй–ҖеҢ»гҒ«з§Ғзҡ„й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдәӢж•…гҒ®еҢ»еӯҰзҡ„гҒӘдәүзӮ№гҒ®е°Ӯй–Җй ҳеҹҹгҒ®еҢ»её«гҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҒӘгҒ„гҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒқгҒ®иӢҰеҠҙгҒ®еәҰеҗҲгҒ„гӮӮеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дёӯгҒ§гӮӮи„ігӮ„еҫӘз’°еҷЁгҒ®й ҳеҹҹгҒ®дәӢж•…гҒҜйӣЈгҒ—гҒҸгҖҒжңҖеҲқгҒҜйқһеёёгҒ«иӢҰеҠҙгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жңҖиҝ‘гҒ§гҒҜеӨ§дҪ“гҒ®й ҳеҹҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӣёи«ҮгҒ§гҒҚгӮӢеҢ»её«гҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒҢзӣҙжҺҘгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜй–“жҺҘзҡ„гҒ«гҒ§гӮӮж§ӢзҜүгҒ§гҒҚгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзӣёи«ҮиҮӘдҪ“гҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзөҗж§ӢжӮ©гҒҫгҒ—гҒ„гҒ®гҒҜгҖҒеҢ»её«гҒ®е°Ӯй–Җй ҳеҹҹгӮӮе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜеҲҶеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҖҒз•‘йҒ•гҒ„гҒ§еҚ”еҠӣгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгҒӮгӮӢжҷӮгҖҒгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«гҒ®дәӢж•…гҒ§еҫӘз’°еҷЁеҶ…科гҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гҒ®ж–№гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҖҢиҮӘеҲҶгҒҜдёҚж•ҙи„ҲгҒ®е°Ӯй–ҖгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«гҒ®гҒ“гҒЁгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁж–ӯгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иЈҒеҲӨгҒ®дёӯгҒ§гҖҒй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜжҸҗиЁҙеүҚгҒӢгӮүеҚ”еҠӣгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢеҢ»её«гҒ«гҒқгҒ®гҒҫгҒҫиҝҪеҠ гҒ®й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢжңҖгӮӮеӨҡгҒ„гғ‘гӮҝгғјгғігҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгӮ„гҒҜгӮҠдәӢжЎҲгӮ’гӮҲгҒҸзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиў«е‘ҠеҒҙгҒ®гҒ”гҒҫгҒӢгҒ—зҡ„гҒӘеҸҚи«–гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰзҡ„зўәгҒӘеҢ»еӯҰзҡ„еҸҚи«–гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
еҗҢгҒҳй‘‘е®ҡеҢ»гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еҠҙеҠӣзҡ„гҒӘиІ жӢ…гӮӮе°‘гҒӘгҒҸжёҲгӮҖгҒ®гҒ§еҠ©гҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒҢ全然еҲҘгҒ®дәүзӮ№гӮ’жҢҒгҒЎеҮәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«еҲҘгҒ®й ҳеҹҹгҒ§гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҪ“然еҲҘгҒ®еҢ»её«гҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе ҙеҗҲгҒ«гҖҒгҒҫгҒҡи©ҰгҒҝгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒдҝЎй јй–ўдҝӮгҒ®гҒӮгӮӢеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒ«ж–°гҒҹгҒӘй ҳеҹҹгҒ®еҢ»её«гӮ’гҒ”зҙ№д»ӢгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгӮ„гӮҠж–№гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгғҸгғјгғүгғ«гҒҜй«ҳгҒҸгҖҒзҙ№д»ӢгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгӮӮй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгҒ«гҒ“гҒҺгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ®гҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ„гҒҸгӮүдҝЎй јгҒ§гҒҚгӮӢиҰӘгҒ—гҒ„еҸӢдәәгҒ®еҢ»её«гҒӢгӮүгҒ®зҙ№д»ӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҢ»еӯҰзҡ„еҠ©иЁҖгҒЁе®ҹеҗҚгҒ§й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ®й–“гҒ«гҒҜеҪјеІёгҒ®е·®гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгӮ„гҒЈгҒҰж–ӯгӮүгӮҢгҒҹжҷӮгҒ«жҲҗжһңгҒӘгҒҸеё°йҖ”гҒ«гҒӨгҒҸгҒ®гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮгҒӨгӮүгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиҮҙгҒ—ж–№гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҚ”еҠӣеҢ»гҒӢгӮүгҒ®гғ«гғјгғҲгҒ§иҰӢгҒӨгҒӢгӮүгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҗҚеҸӨеұӢгҒ«гҒӮгӮӢгҖҢеҢ»зҷӮдәӢж•…жғ…е ұгӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгғ«гғјгғҲгҒ§гҒ®зҙ№д»ӢгҒЁгҒ„гҒҶжүӢй ҶгӮ’иёҸгӮҖгҒЁгҒ„гҒҶж–№жі•гӮ’и©ҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢж•…жғ…е ұгӮ»гғігӮҝгғјгҒ§зҷ»йҢІгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢеҢ»её«гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжӨңиЁҺгҒ®зөҗжһңгҖҒз©ҚжҘөж„ҸиҰӢгҒҢгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰзөҢйЁ“гӮ’з©ҚгӮ“гҒ§гҒҠгӮүгӮҢгӮӢеҢ»её«гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒйқһеёёгҒ«иүҜгҒ„й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒе°Ӯй–Җй ҳеҹҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜзҷ»йҢІгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҢ»её«гҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҖҒжҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгӮӮиүҜгҒ„еҢ»её«гҒ«еҮәдјҡгҒҲгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶйӣЈзӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒжүӢй ҶгҒЁгҒ—гҒҰеҖҷиЈңгҒ®еҢ»её«гҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҹеҫҢгҒ«йқўи«ҮгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒжҷӮй–“гӮӮдёҖе®ҡзЁӢеәҰгҒӢгҒӢгӮҠгҖҒиІ»з”ЁгӮӮгҒӢгҒӘгӮҠй«ҳйЎҚгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгӮ»гғігӮҝгғјзөҢз”ұгҒ§гӮӮй ҳеҹҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜзҷ»йҢІгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҢ»её«иҮӘдҪ“гҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒиЈҒеҲӨжүӢз¶ҡгҒҢйҖІиЎҢдёӯгҒ®зҠ¶жіҒгҒ§гӮ»гғігӮҝгғјгҒ«з”ігҒ—иҫјгӮ“гҒ§гҖҒйқўи«ҮгҖҒж„ҸиҰӢжӣёдҪңжҲҗгҒЁгҒ„гҒҶжүӢй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢгҒ®гҒҜзҸҫе®ҹзҡ„гҒ«гҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢе®ҹзҠ¶гҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҚ”еҠӣеҢ»гҒӢгӮүгҒ®зҙ№д»ӢгӮ„гӮ»гғігӮҝгғјзөҢз”ұгҒ§гҒ®гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮӮйӣЈгҒ—гҒ„жҷӮгҒ«гҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲгҖҢеҪ“гҒҹгҒЈгҒҰз •гҒ‘гӮҚпјҒгҖҚгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
й•·гҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒз¶ҡгҒҚгҒҜPartпј’гҒ§жӣёгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһгҖҢдёҚйҒ©еҲҮгҖҚгҒЁгҖҢйҒ©еҲҮгҒ§гҒӘгҒ„гҖҚгҒ®йҒ•гҒ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
еҢ»зҷӮдәӢ件гҒ§гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒҢжңҖгӮӮиӢҰеҠҙгҒ—гҖҒиІ жӢ…гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҢй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒҢгҒқгӮҢгҒһгӮҢиҮӘгӮүдҫқй јгҒ—гҒҰдҪңжҲҗгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶз§Ғзҡ„й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒЁгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ®жүӢз¶ҡгҒЁгҒ—гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢе…¬зҡ„й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ§гҒҜжә–еӮҷгҒ®жүӢй ҶгӮӮз•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮжҲ‘гҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜйқһеёёгҒӘиІ жӢ…гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘиӢҰеҠҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжң¬ж—ҘгҒҜй‘‘е®ҡдәӢй …гҒ®иЁӯе•ҸгҒ®иЎЁзҸҫгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҒҰеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
з§Ғзҡ„й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪ•гҒҢеӨ§еӨүгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®дәүзӮ№гҒ«еҗҲиҮҙгҒҷгӮӢеҚ”еҠӣеҢ»гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҰгҖҒй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгҒ«еҚ”еҠӣгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒҫгҒ§гҒҹгҒ©гӮҠзқҖгҒҸгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒҢгҖҒжұәгҒ—гҒҰе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒдәүзӮ№гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒҹгӮҒгҒ®йқўи«ҮгӮ„иіҮж–ҷгҒ®жҸҗзӨәгҖҒиӘ¬жҳҺгҒ«еҠҙгӮ’иҰҒгҒ—гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒиЈҒеҲӨгҒ®еұ•й–ӢгҒ®дёӯгҒ§гҖҒз§Ғзҡ„й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ®дҪңжҲҗгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠзӣ®гҒ®еүҚгҒ«пј“пјҗпјҗпјҗгғЎгғјгғҲгғ«зҙҡгҒ®еұұгҒҢиҒігҒҲз«ӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ§жҡ—жҫ№гҒҹгӮӢж°—еҲҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒе…¬зҡ„й‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгҒ§гҒҜгҖҒй‘‘е®ҡеҢ»гҒ®гғӘгӮ№гғҲгҒҜиЈҒеҲӨжүҖгҒҢз”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®зӮ№гҒ§гҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгӮјгғӯгҒӢгӮүжҺўгҒҷгҒ®гҒЁгҒҜйҒ•гҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҒқгҒ“гҒӢгӮүйҒ©еҲҮгҒӘй‘‘е®ҡеҢ»гҒ®йҒёд»»гҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ§еҢ»зҷӮеҒҙгӮ„иЈҒеҲӨжүҖгҒЁгҒ®еҚ”иӯ°гӮ’зөҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒзӣёеҪ“гҒӘиӢҰеҠҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒй‘‘е®ҡеҢ»гҒ®йҒёд»»гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҚ”иӯ°гҒЁдёҰиЎҢгҒ—гҒҰгҖҒй‘‘е®ҡдәӢй …гӮ’и©°гӮҒгҒҰгҒ„гҒҸдҪңжҘӯгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгӮӮгҒӢгҒӘгӮҠеӨ§еӨүгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жңҖиҝ‘гҒ§гҒҜгҖҒиЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®дёӯгҒ§дәүзӮ№ж•ҙзҗҶгӮ’ж—©гҒ„ж®өйҡҺгҒ§иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӨ§дҪ“гҒ®дәүзӮ№гҒҜе…ұжңүгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒй‘‘е®ҡдәӢй …гҒ®дёӯгҒ«гҒ©гҒ“гҒҫгҒ§гҒқгӮҢгӮ’еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгӮӢгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜиӯ°и«–гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖиҝ‘гӮӮзөҢйЁ“гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒй‘‘е®ҡдәӢй …гҒ®иЁӯе•ҸгҒ®иЎЁзҸҫгӮ’е·ЎгҒЈгҒҰиӯ°и«–гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒҠгҒӢгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜдҪ•гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒйҒҺеӨұгҒ«й–ўгҒҷгӮӢй‘‘е®ҡдәӢй …гҒ®жң«е°ҫгҒ®иЎЁзҸҫгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҒ®еҖӢгҖ…гҒ®иЁәзҷӮиЎҢзӮәгҒҢйҒҺеӨұгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгӮ’е°ӢгҒӯгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҖҒгҖҢдёҚйҒ©еҲҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖҚгҒЁе•ҸгҒҶгҒӢгҖҒгҖҢйҒ©еҲҮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖҚгҒЁе•ҸгҒҶгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиӯ°и«–гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®зӮ№гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еӮҫеҗ‘гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢдёҚйҒ©еҲҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖҚгҒЁе•ҸгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«жұӮгӮҒгҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®йҒ•гҒ„гҒҢгҒ©гҒ®гҒҸгӮүгҒ„йҮҚиҰҒгҒӘж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒӨгҒӢгҖҒгғ”гғігҒЁгҒ“гҒӘгҒ„ж–№гҒҢеӨҡгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«еҢ»зҷӮиЁҙиЁҹгҒ«й–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз«Ӣе ҙгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒзөҗж§ӢйҮҚеӨ§гҒӘеҲҶеІҗзӮ№гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгҒӘгҒңгҖҢдёҚйҒ©еҲҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖҚгҒЁе•ҸгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«жұӮгӮҒгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
иЈҒеҲӨе®ҳгҒЁи©ұгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒгҖҢйҒ©еҲҮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӯ”гҒҲгҒҜгҖҒгӮӨгӮігғјгғ«йҒҺеӨұгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ гҖҚгҒЁгҒ®иҝ”зӯ”гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зҸҫгҒ«иЈҒеҲӨе®ҳгҒҢгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиҰӢи§ЈгӮ’ж»”гҖ…гҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢж–Үз« гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйҒ©еҲҮгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁз¬¬дёүиҖ…гҒ®еҢ»её«гҒҢжҢҮж‘ҳгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒҢйҒҺеӨұгҒ«гҒӮгҒҹгӮүгҒӘгҒ„гҒӘгӮ“гҒҰгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠеҫ—гӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
е®ҹйҡӣгҒ«гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘеҢ»её«гҒ®ж–№гҒ«гҒҠдјҡгҒ„гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒзҸҫе®ҹгҒ«гҒқгҒ®еҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒ«жҗәгӮҸгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒжӮЈиҖ…гӮӮиЁәгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„第дёүиҖ…гҒ®еҢ»её«гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒи»ҪгҖ…гҒ«гғҹгӮ№гӮ’жҢҮж‘ҳгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢеҢ»её«гҒ®еҝғжғ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜзҺҮзӣҙгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеүҚжҸҗгҒӢгӮүгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒй‘‘е®ҡеҢ»гҒҢеҪ“и©ІеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҢйҒ©еҲҮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸиҰӢгӮ’иҝ°гҒ№гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҖҒзӣёеҪ“иёҸгҒҝиҫјгӮ“гҒ иЎЁзҸҫгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҜеҢ»зҷӮгғҹгӮ№гӮ’жҳҺзўәгҒ«жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иЈҒеҲӨжүҖгҒ®дёҖйғЁгҒ«гҒӮгӮӢгҖҢйҒ©еҲҮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӯ”гҒҲгҒҢгӮӨгӮігғјгғ«йҒҺеӨұгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзҷәжғігҒҜгҖҒиЁҖи‘үйҒҠгҒігҒ«зӯүгҒ—гҒҸгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«жңәдёҠгҒ®з©әи«–гҒ гҒЁж„ҹгҒҳгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮӮгҒҶ1гҒӨгҖҒе®ҹеӢҷзҡ„гҒ«гҒҜгҒ“гҒ®зӮ№гҒҢгҒЁгҒҰгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҖҢдёҚйҒ©еҲҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖҚгҒЁе•ҸгҒ„гҒ гҒЁгҖҒгҖҢдёҚйҒ©еҲҮгҒЁгҒҫгҒ§гҒҜгҒ„гҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸиҰӢгҒҢеј•гҒҚеҮәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜзӯ”гҒҲгӮӢеҒҙгҒ®дәәй–“гҒ®еҝғзҗҶгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒй‘‘е®ҡеҢ»гҒҢеҪ“и©ІеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒҜй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҖҢйҒ©еҲҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖҚгҒЁгҒ®е•ҸгҒ„гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒ•гҒҷгҒҢгҒ«гҖҢйҒ©еҲҮгҒ§гҒҷгҖҚгҒЁгҒҜзӯ”гҒҲгҒ«гҒҸгҒ„гҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгҖҢдёҚйҒ©еҲҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖҚгҒЁгҒ®е•ҸгҒ„гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢдёҚйҒ©еҲҮгҒЁгҒҫгҒ§гҒҜгҒ„гҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжӣ–жҳ§гҒӘзӯ”гҒҲгҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢе°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒҡгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«й‘‘е®ҡеҢ»гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеҪ“и©ІеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ«зӣҙжҺҘй–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„д»ҘдёҠгҖҒж–ӯиЁҖгҒ—гҒҘгӮүгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҝғзҗҶгҒҢеғҚгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒеҗҢжҘӯиҖ…гҒ®гғҹгӮ№гӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҘгӮүгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҝғзҗҶгҒҢеғҚгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮеҗҰе®ҡгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
й‘‘е®ҡдәӢй …гҒ®иЎЁзҸҫгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘй‘‘е®ҡеҢ»гҒ®еҝғзҗҶгҒёгҒ®еҪұйҹҝгӮӮиёҸгҒҫгҒҲгҒҰжӨңиЁҺгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гҖҢдёҚйҒ©еҲҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖҚгҒЁе•ҸгҒ„гҒ«еӣәеҹ·гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒ“гҒқгҖҢдёҚйҒ©еҲҮгҒ«гӮӮгҒ»гҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
еҢ»зҷӮиЈҒеҲӨгҒ®й ҳеҹҹгҒҜгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ зҷәеұ•йҖ”дёҠгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгӮӮи©ҰиЎҢйҢҜиӘӨгҒҜз¶ҡгҒҸгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒй‘‘е®ҡгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®йҒӢз”ЁгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮ„гӮҠж–№гҒҢзңҹзӣёи§ЈжҳҺгҒ«иіҮгҒҷгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶиҰ–зӮ№гӮ’еҝҳгӮҢгҒҡгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§иЎҢгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„гҒ—гҖҒжӮЈиҖ…еҒҙд»ЈзҗҶдәәгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁиЁҙгҒҲгҒҰеӨүгҒҲгҒҰиЎҢгҒӢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…пј°пҪҒпҪ’пҪ”пј’
еүҚеӣһгҒӢгӮүз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
з ”дҝ®еҢ»гҒҢеҲқжӯ©зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гӮ’зҠҜгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮ’жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁжҢҮе°ҺгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҒгҒқгӮ“гҒӘеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒ§йҮҚеӨ§гҒӘеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒңгҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
иүІгҖ…иӘҝгҒ№гҒҹгӮҠгҖҒи©ұгӮ’дјәгҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеў—гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹиғҢжҷҜзҡ„гҒӘдәӢжғ…гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«жҖқгҒ„иҮігӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒӮгӮӢиҮЁеәҠеҢ»гҒӢгӮүдјәгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒеҢ»зҷӮй–ўдҝӮиҖ…гҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҹж–ҮзҢ®гҒ§гӮӮзӣ®гҒ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘиғҢжҷҜдәӢжғ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҢз ”дҝ®гҒ®гҒҹгӮҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒзҸҫе ҙгҒ®жҲҰеҠӣгҒЁгҒ—гҒҰз ”дҝ®еҢ»гӮ’йӣҮгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶйқўгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
д»ҠгҒ®еҢ»зҷӮгҒ®зҸҫзҠ¶гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒеӣҪгҒ®ж”ҝзӯ–гҒ§еҢ»зҷӮиІ»гҒҢеүҠжёӣгҒ•гӮҢгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҢиөӨеӯ—гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҸҫе®ҹгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒеҢ»её«гҒ®з ”дҝ®еҲ¶еәҰгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҖҒдёҖе®ҡгҒ®зөҢйЁ“гӮ’жңүгҒҷгӮӢеҢ»её«гӮ’еёӮдёӯгҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҢзўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢжғ…гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒжң¬жқҘгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒдёҖе®ҡгҒ®гӮӯгғЈгғӘгӮўгӮ’жңүгҒҷгӮӢеҢ»её«гҒҢй…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚе ҙжүҖгҒ«гҖҒзөҢйЁ“гҒ®е°‘гҒӘгҒ„з ”дҝ®еҢ»гӮ’гҒӮгҒҰгҒҢгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠжҢҮе°ҺгҖҒеҠ©иЁҖгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒ®еҒҙгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒӘгӮ“гҒҰзҹҘгӮӢиЎ“гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒз©әжҒҗгӮҚгҒ—гҒ„йҷҗгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
и…°жӨҺз©ҝеҲәгҒ®гғҹгӮ№гҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒеҪ“и©Із ”дҝ®еҢ»гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§дёҖеәҰгӮӮи…°жӨҺз©ҝеҲәгӮ’гӮ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гҒқгҒҶгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ§й«„ж¶ІжҺЎеҸ–гҒҫгҒ§пј—еӣһгӮӮз©ҝеҲәгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§гғўгғ«гғўгғғгғҲгҒӢгҒЁгҒ„гҒ„гҒҹгҒҸгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘдҝЎгҒҳгҒҢгҒҹгҒ„и©ұгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁеүҚгҒ«зңҢеҶ…гҒ®гғҷгғҶгғ©гғігҒ®еҢ»её«гҒ®ж–№гҒ«иҒһгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҘһеҘҲе·қзңҢеҶ…гҒ®гҒӮгӮӢең°еҹҹгҒ®еҹәе№№з—…йҷўгҒ§гҒҜгҖҒеӨңй–“гҒ®ж•‘жҖҘеҜҫеҝңгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰз ”дҝ®еҢ»гҒ«еҜҫеҝңгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
еҪ“и©ІеҢ»её«гҒ„гӮҸгҒҸгҖҒгҒқгҒ®гӮЁгғӘгӮўгҒ§ж•‘жҖҘи»ҠгӮ’е‘јгӮ“гҒ§гӮӮгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒзө¶еҜҫгҒ«еҲҘгҒ®з—…йҷўгҒ«гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„гӮ·гғЈгғ¬гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдҪ•еәҰгӮӮдҪ•еәҰгӮӮз©ҝеҲәгҒ«еӨұж•—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢй–“гҖҒгӮӮгҒ—жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒқгҒ°гҒ«гҒ„гҒҹгӮүгҖҒгҖҢгҒ“гӮҢд»ҘдёҠгҒҜеҚұйҷәгҖҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰйҖ”дёӯгҒ§жүӢжҠҖгӮ’дәӨд»ЈгҒҷгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гҖҒеӨҡж•°еӣһгҒ®з©ҝеҲәгҒ®еҚұйҷәжҖ§гӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒиЎ“еҫҢз®ЎзҗҶгҒҜеҪ“然еҺійҮҚгҒ«гҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒҜгҒҡгҒӘгҒ®гҒ«гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®з—ҮдҫӢгӮӮгҖҒиЎ“еҫҢгҒ«жҳҺгӮүгҒӢгҒӘз•°еёёгҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«гҖҒгҒқгҒ“гҒ«гӮӮжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢй–ўдёҺгҒ—гҒҹеҪўи·ЎгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒҜгҖҒжң¬еҪ“гҒҜиӘ°гҒ®гғҹгӮ№гҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒ„гҒҲгҒ°гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ«еҚұйҷәжҖ§гҒ®дјҙгҒҶеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгӮ’гӮ№гғ«гғјгҒ§гӮ„гӮүгҒӣгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ®ж§ӢйҖ зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гҒЁи©•дҫЎгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еүҚгҒ«гҖҒгҒҠдё–и©ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹеҢ»её«гҒӢгӮүгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹз—…йҷўгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§зӣёи«ҮгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫгҒқгҒ®з—…йҷўгҒ§з ”дҝ®еҢ»гҒҢгҒІгҒ©гҒ„зӣ®гҒ«йҒӯгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе®ҹжғ…гӮ’жүҝзҹҘгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҖҒгҒӮгҒ®з—…йҷўгҒ§гҒҜгҒҫгҒЁгӮӮгҒӘжҢҮе°ҺгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҖҒз ”дҝ®еҢ»гӮ’жҙҫйҒЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁжҶӨгҒЈгҒҰгҒҠгҒЈгҒ—гӮғгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з ”дҝ®еҢ»гӮ’иӮІгҒҰгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе®үжҳ“гҒ«жҲҰеҠӣгҒЁгҒ—гҒҰжүұгҒҶгҒ гҒ‘гҒ®з—…йҷўгҒ§гҒҜгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҒқгҒ®йҖҡгӮҠгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’жүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰжҖқгҒҶгҒ®гҒҜгҖҒжӮЈиҖ…еҒҙгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰж„ҹгҒҳгҒҹгҒ“гҒЁгҖҒж°—гҒҘгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еҢ»зҷӮеҒҙгҒ«гғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖҒжҷӮгҒ«гҒҜеҲ¶еәҰгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮзү©з”ігҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒ•гҒ«з ”дҝ®еҢ»еҲ¶еәҰгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒҢиҰӢзӣҙгҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡгҖҒдәҢгҒӨжҸҗжЎҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжӣёгҒ„гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖгҒӨгҒҜгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ«гҒҜеҗҚжңӯгҒ«дҪ•е№ҙзӣ®гҒ®з ”дҝ®еҢ»гҒӢгӮ’жҳҺиЁҳгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҖӮжӮЈиҖ…гҒҢдёҚе®үгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҹгӮүгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒ®еҜҫеҝңгӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
з—…йҷўеҒҙгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜз…©гӮҸгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒҢз–‘е•ҸгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒеЈ°гӮ’дёҠгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®йҳІжӯўгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒҜгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ«гҖҒгғ©гғ”гғғгғүгғ¬гӮ№гғқгғігӮ№гғҒгғјгғ гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеүҚгҒ«еҠ©иЁҖгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹеҢ»её«гҒӢгӮүж•ҷгӮҸгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁеҠ©иЁҖгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒ®жҢҮзӨәгҒҢй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒЁиӢҘгҒ„еҢ»её«гҒҢз–‘е•ҸгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҖҒ科гҒ®жһ гӮ’и¶…гҒҲгҒҰгҖҒжЁӘж–ӯзҡ„гҒ«зӣёи«ҮгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгғҒгғјгғ гҒҢйҷўеҶ…гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒҢгҒқгҒ“гҒ«й§ҶгҒ‘иҫјгӮҖгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®йҳІжӯўгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒЁгҖҒжңҖеҫҢгҒ«еҢ»зҷӮеҒҙгҒ«еј·гҒҸиЁҙгҒҲгҒҹгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгҒ—гҒҹжҢҮе°ҺгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҡгҖҒйҮҚеӨ§гҒӘеҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒзңҹйқўзӣ®гҒӘеҢ»зҷӮиҖ…гҒ»гҒ©гғҲгғ©гӮҰгғһгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®еҢ»её«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дәәз”ҹгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸзӢӮгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҖҒдәӢж•…гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹз ”дҝ®еҢ»гҒ®ж–№гҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪ“йЁ“и«ҮгӮ’дјәгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҜгҖҒжӮЈиҖ…гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҢ»её«гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘгғҖгғЎгғјгӮёгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢдәӢж•…гҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮеҲқжӯ©зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гҒ§гҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢзӣ®гӮ’й…ҚгҒЈгҒҰжҷ®йҖҡгҒ«ж°—гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒӢгҖҒгғӘгӮ«гғҗгғјгҒ§гҒҚгҒҹгҒҜгҒҡгҒ®гӮӮгҒ®гҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒгҒ“гҒ®зЁ®гҒ®дәӢж•…гӮ’гҒ„гҒӢгҒ«гҒ—гҒҰз„ЎгҒҸгҒҷгҒӢгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁзҹҘжҒөгӮ’зөһгҒЈгҒҰиүҜгҒ„еҢ»зҷӮгӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гҒӢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒЁеј·гҒҸжҖқгҒҶ次第гҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…пј°пҪҒпҪ’пҪ”пј‘
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«гӮӮгҖҒеҖӢеҲҘгҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®дёӯгҒ§дҪ•еәҰгҒӢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»Ҡж—ҘгҒҜз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰжӯЈйқўгҒӢгӮүеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒңз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжӯЈйқўгҒӢгӮүеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҒӢгҒЁз”ігҒ—гҒҫгҒҷгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒ“гҒ“гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиӨҮж•°гҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜжҜ”ијғзҡ„жңҖиҝ‘и§ЈжұәгҒ—гҒҹеҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®еүІеҗҲгҒҢйқһеёёгҒ«й«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰж°—гҒҘгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒзҸҫеңЁгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ§гҖҒиЁҙиЁҹгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮдҫӢгҒҜгҖҒ6件гҒ»гҒ©гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ“пј‘е№ҙдҪҷгӮҠгҒ®й–“гҒ«и§ЈжұәгҒ—гҒҹеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҢ4件пјҲжӯҜ科еҢ»гӮ„дёҖиҲ¬й–ӢжҘӯеҢ»гҒ®дәӢ件гӮ’йҷӨгҒҚгҒҫгҒҷпјүгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜжҸҗиЁҙжә–еӮҷдёӯгҒ®жЎҲ件гҒҢ2件гҒ»гҒ©гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁеҚҠж•°гҒҢз ”дҝ®еҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒҢзөЎгӮ“гҒ еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ»гҒӢгҒ«гӮӮзҸҫеңЁиӘҝжҹ»дёӯгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜзӨәи«ҮдәӨжёүдёӯгҒ®з—ҮдҫӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҺіеҜҶгҒ«гҒҜеҚҠж•°гӮҲгӮҠгҒҜдёӢеӣһгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёҖж–№гҖҒдёҠгҒ®пј‘2件гҒ®гҒҶгҒЎгҒ«гҒҜеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒд»Ӣиӯ·гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜе…ҘжөҙгҒҢгӮүгҒҝгҒ®дәӢж•…гҒҢ2件еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒз·ҸеҗҲз—…йҷўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒе®ҹж„ҹгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒ«гӮҲгӮӢдәӢж•…гҒ®жҜ”зҺҮгҒҢйқһеёёгҒ«й«ҳгҒ„еҚ°иұЎгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӮгҒҸгҒҫгҒ§еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ гҒ‘гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»–гҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒӢгӮүгӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘи©ұгӮ’иҒһгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒд»ҘеүҚгҒЁжҜ”гҒ№гҒҰгӮӮеў—еҠ гҒҜйЎ•и‘—гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒқгҒҶгҒ—гҒҹеӮҫеҗ‘гҒҢеј·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒ“гҒ“гҒ®жүҖжүұгҒЈгҒҹз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гӮ’гҒ•гӮүгҒ«еҲҶжһҗгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҒЁгҖҒгҒӮгӮӢзЁ®гҒ®еӮҫеҗ‘гҖҒзү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҒйқһеёёгҒ«еҲқжӯ©зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒдҪҝгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„и–¬гӮ’иӘӨгҒЈгҒҰжҠ•дёҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҸҫеңЁиЁҙиЁҹдёӯгҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒж•—иЎҖз—ҮгҒ®жӮЈиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиЎҖж¶Іеҹ№йӨҠжӨңжҹ»гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰиө·еӣ иҸҢгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒқгҒ®иө·еӣ иҸҢгҒ«гҒҜз„ЎеҠ№гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢи–¬гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰжҠ•дёҺгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®ж„ҹеҸ—жҖ§гғҶгӮ№гғҲгҒ§жңҖеҲқгҒ®и–¬гҒҢеҠ№гҒӢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ«гҖҒгҒҫгҒҹгӮӮгӮ„иӘӨгҒЈгҒҹи–¬гӮ’жҠ•дёҺгҒ—гҒҰгҖҒжӮЈиҖ…гҒҢжӯ»дәЎгҒҷгӮӢгҒ«иҮігӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжңҖгӮӮеӨҡгҒ„гҒ®гҒҢгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒӘжүӢжҠҖгӮ’й–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫгҒӘгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮдҫӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒ4件гҒҢз©ҝеҲәгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠйҮқгӮ’еҲәгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶжүӢжҠҖгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒдёӯеҝғйқҷи„ҲгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«гҒҢ2件гҖҒи…°жӨҺз©ҝеҲәгҒҢ1件гҖҒиӮқз”ҹжӨңгҒҢ1件гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёӯеҝғйқҷи„ҲгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«гҒ®пј’件гҒЁиӮқз”ҹжӨңгҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮеӢ•и„ҲиӘӨз©ҝеҲәгҒ§еҮәиЎҖеӨҡйҮҸгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰжӮЈиҖ…гҒҜдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒи…°жӨҺз©ҝеҲәгҒ®з—ҮдҫӢгӮӮгҖҒжӮЈиҖ…гҒ«йҮҚзҜӨгҒӘеҫҢйҒәз—ҮгҒҢж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®пј”件гҒ®гҒҶгҒЎпј“件гҒҜгҖҒеҗҲиЁҲгҒ®з©ҝеҲәеӣһж•°гҒҢгҖҒпј–еӣһгҒӘгҒ„гҒ—пј‘пјҗеӣһгҒ«еҸҠгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷпјҲиӮқз”ҹжӨңгҒҜйҖ”дёӯгҒ§гғҷгғҶгғ©гғігҒ®еҢ»её«гҒ«д»ЈгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ»гҒӢгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰз ”дҝ®еҢ»гҒҢзөӮгӮҸгӮҠгҒҫгҒ§гӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒ»гҒӢгҒ«гӮӮгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜе°‘гҒ—еүҚгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҮҚзҜӨгҒӘжҖҘжҖ§и…№з—ҮгҒ®дәӢжЎҲгҒӘгҒ®гҒ«гҖҒеҜҫеҝңгҒ—гҒҹз ”дҝ®еҢ»гҒҢгғ¬гғігғҲгӮІгғігӮӮж’®гӮүгҒҡгҖҒпј“жӯігҒ®еӯҗдҫӣгӮ’жҖҘжҖ§иғғи…ёзӮҺгҒЁиЁәж–ӯгҒ—гҒҰеё°е®…гҒ•гҒӣгҒҹгӮүгҖҒгҒқгҒ®еӨңгҖҒгӮӨгғ¬гӮҰгӮ№гҒ§жҖҘеӨүгҒ—гҒҰжӯ»дәЎгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶз—ҮдҫӢгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜз ”дҝ®еҢ»гҒ«гӮҲгӮӢжҳҺгӮүгҒӢгҒӘиӘӨиЁәгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖзӮ№гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®дәӢж•…гӮ’еҲҶжһҗгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒзңӢйҒҺгҒ—йӣЈгҒ„зү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®дәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҹж§ҳеӯҗгҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒӘгҒҸгҖҒгҒ»гҒјгғҺгғјгӮҝгғғгғҒгҒ§д»»гҒӣгҒҚгӮҠгҒ«гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒҜгҖҒзөҢйЁ“гҒҢжө…гҒҸгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒӘжүӢжҠҖгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒи–¬гӮ„жІ»зҷӮж–№йҮқгҒ®йҒёжҠһгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгғҮгғӘгӮұгғјгғҲгҒӘз—ҮдҫӢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁәж–ӯгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮзҡ„зўәгҒ«иЎҢгҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒе ҙйқўе ҙйқўгҒ§гҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢйҒ©е®ңеҠ©иЁҖгҖҒжҢҮе°ҺгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҝ…й ҲгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдёҠиЁҳгҒ®з—ҮдҫӢгҒ§гҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҖҒйҖ”дёӯгҒ§й–ўдёҺгҒ—гҒҹз—ҮдҫӢгҒҜ1件гҒ—гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹпјҲгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҒқгҒ®з—ҮдҫӢгӮӮгҖҒзөҢйҒҺиҰіеҜҹгҒ§гҒҜе®Ңе…ЁгҒ«з ”дҝ®еҢ»д»»гҒӣгҒ§гҖҒзөҗеұҖжӮЈиҖ…гҒҜеҮәиЎҖжҖ§гӮ·гғ§гғғгӮҜгҒ§дәЎгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹпјүгҖӮ
жҷ®йҖҡгҒ«иҖғгҒҲгҒҰгҖҒдёӯеҝғйқҷи„ҲгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«гҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒи…°жӨҺз©ҝеҲәгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒпј—еӣһгҒЁгҒӢпј‘пјҗеӣһгӮӮгҒ®еӣһж•°з©ҝеҲәгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒӣгҒ°гҖҒеӢ•и„ҲгҒӘгҒ©гҒ«иҮҙе‘Ҫзҡ„гҒӘжҗҚеӮ·гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷеҚұйҷәгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢйҖ”дёӯгҒ§дәӨд»ЈгҒӣгҒҡгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫжңҖеҫҢгҒҫгҒ§з ”дҝ®еҢ»гҒ«з©ҝеҲәгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгӮӮгҒ—гҒқгҒ®е ҙгҒ«жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҒӮгӮҠеҫ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒ®гғҹгӮ№гҒЁгҒ„гҒҶгҒ—гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒгӮӮгҒЈгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгғҹгӮ№гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҖҒжңӘеҝ…гҒ®ж•…ж„ҸгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ•гҒҲжҖқгҒҲгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒЁгҒҠи©ұгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ§гӮӮжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢеҝ…гҒҡгғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘд»•зө„гҒҝгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеёёгҒ«жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒқгҒ°гҒ§гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒӘгҒҢгӮүиЎҢгӮҸгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒиӘӨиЁәгҒ§пј“жӯіе…җгӮ’жӯ»гҒӘгҒӣгҒҹгӮұгғјгӮ№гҒ§гӮӮгҖҒиӨҮж•°еӣһгҒ®иӘӨз©ҝеҲәгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ§гӮӮгҖҒжҠ—иҸҢи–¬гҒ®йҒёжҠһгӮ’иӘӨгҒЈгҒҹгӮұгғјгӮ№гҒ§гӮӮгҖҒжҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒқгҒ®йҒҺзЁӢгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹеҪўи·ЎгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
еүҚиҝ°гҒ—гҒҹжҠ—иҸҢи–¬гҒ®иӘӨжҠ•дёҺгҒ®з—ҮдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гӮ“гҒӘдҝЎгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮиө·гҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒҜй»„иүІгғ–гғүгӮҰзҗғиҸҢж„ҹжҹ“гҒ§гҒ®ж•—иЎҖз—ҮгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиЎҖж¶Іеҹ№йӨҠжӨңжҹ»гҒЁдҪөгҒӣгҒҰе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢж„ҹеҸ—жҖ§гғҶгӮ№гғҲгҒ§гҒ©гҒ®жҠ—иҸҢи–¬гҒҢеҠ№гҒҸгҒӢгӮ’иӘҝгҒ№гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гғҶгӮ№гғҲгҒ®зөҗжһңгҒҢеҮәгҒҹжҷӮзӮ№гҒ§гҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒҜгҖҒж„ҹеҸ—жҖ§гғҶгӮ№гғҲгҒ®еҲӨе®ҡгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„жҠ—иҸҢи–¬гҒ§гҒӮгӮӢпј°пј©пј°пјЈгҒЁгҒ„гҒҶи–¬гӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰжҠ•дёҺгҒҷгӮӢпјҲгҒқгҒ—гҒҰгҒқгӮҢгҒҢй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјүгҒЁгҒ„гҒҶгғҹгӮ№гӮ’зҠҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гӮүж„ҹеҸ—жҖ§гғҶгӮ№гғҲгҒ§ж„ҹеҸ—жҖ§гҒӮгӮҠгҒЁеҲӨе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹпјӯпј°пј©пј°пјЈгҒЁеҗҢгҒҳгӮӮгҒ®гҒ гҒЁеӢҳйҒ•гҒ„гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е‘ҪгҒ«й–ўгӮҸгӮӢе ҙйқўгҒ§гҖҒ笑гҒ„и©ұгҒ«гӮӮгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘеҲқжӯ©зҡ„гҒӘгғҹгӮ№гӮ’зҠҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ§жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢйҒёжҠһгҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒҜеҲ°еә•иҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒз ”дҝ®еҢ»гҒ®еҢ»зҷӮиЎҢзӮәгӮ’жҢҮе°ҺеҢ»гҒҢгҒҫгҒЁгӮӮгҒ«зӣЈзқЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒӢжҖқгҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘз—ҮдҫӢгҒ°гҒӢгӮҠгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
й•·гҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒпј°пҪҒпҪ’пҪ”пј’гҒ«з¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ