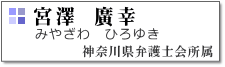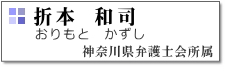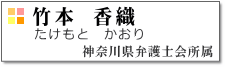еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһгҖҢеұҖжүҖйә»й…”и–¬дёӯжҜ’гҒ«гӮҲгӮӢжӯ»дәЎдәӢж•…гҖҚи§ЈжұәгҒ®гҒ”е ұе‘ҠPARTпј‘
жЁӘжөңең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҒ«дҝӮеұһгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖҢеұҖжүҖйә»й…”и–¬дёӯжҜ’гҒ«гӮҲгӮӢжӯ»дәЎдәӢж•…гҖҚгҒ®еҢ»зҷӮйҒҺиӘӨиЁҙиЁҹгҒҢгҖҒжӮЈиҖ…гҒ®жӯ»дәЎгҒҢиў«е‘ҠеҢ»её«гҒ®йҒҺеӨұгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺзўәгҒ«иӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҖҒйқһеёёгҒ«й«ҳж°ҙжә–гҒ®е’Ңи§ЈйҮ‘гӮ’иў«е‘ҠеҒҙгҒҢж”Ҝжү•гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§иЈҒеҲӨдёҠгҒ®е’Ңи§ЈгҒҢжҲҗз«ӢгҒ—гҖҒи§ЈжұәгҒ®йҒӢгҒігҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®йЎӣжң«гӮ’еҗ«гӮҒгҖҒгҒ”е ұе‘ҠгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒжң¬д»¶гҒ«гҒӨгҒҚгҒҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒз®•еұұжҰҺжң¬з·ҸеҗҲжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ®е…Ҳз”ҹж–№гҒЁе…ұеҗҢгҒ§еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒжңҖеҲқгҒ«дҝЎй јгҒ—гҒҰгҒҠеЈ°гҒҢгҒ‘гҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒеҗҢдәӢеӢҷжүҖгҒ®з®•еұұејҒиӯ·еЈ«гҖҒжҰҺжң¬ејҒиӯ·еЈ«гҖҒиҘҝз”°ејҒиӯ·еЈ«гҒ«гӮӮеҝғгҒӢгӮүж„ҹи¬қз”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҲқгӮҒгҒ«гҒҠж–ӯгӮҠгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҒЁгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢжүұгҒЈгҒҹдәӢ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ”е ұе‘ҠгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸи¶Јж—ЁгҒҜгҖҒдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮеҗҢзЁ®гҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®зҷәз”ҹгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒҢжңүз”ЁгҒӘгҒ“гҒЁгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒӢгӮүгҒ«гҒ»гҒӢгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дәӢж•…гҒ®зөҢйҒҺгӮ’жӨңиЁјгҒҷгӮӢдёӯгҒ§гҖҒгҒӘгҒңгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгҒҹгҒӢгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҹгӮүжӯ»дәЎгҒЁгҒ„гҒҶжңҖжӮӘгҒ®зөҗжһңгҒҢйҒҝгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж§ҳгҖ…гҒӘж•ҷиЁ“гӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгӮ’еәғгҒҸзҹҘгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒеҗҢзЁ®дәӢж•…гҒ®еҶҚзҷәйҳІжӯўгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒЁдҝЎгҒҳгҒҰжӯўгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…иӘҝжҹ»гғ»ж”ҜжҸҙгӮ»гғігӮҝгғјгҒ®жҙ»еӢ•гӮ„гҖҒеҖӢгҖ…гҒ®еҢ»зҷӮиҖ…гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜз—…йҷўгҒӘгҒ©гҒ§гӮӮеҸ–гӮҠзө„гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдәӢж•…йҳІжӯўгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹж§ҳгҖ…гҒӘи©ҰгҒҝгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒҜеёёгҖ…敬ж„ҸгӮ’иЎЁгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҢдәӢ件гҒЁгҒ—гҒҰйЎ•еңЁеҢ–гҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹдәӢж•…гҒ®зөҢз·ҜгҒ«й–ўгҒҷгӮӢдәӢе®ҹгӮ„дәӨжёүгӮ„иЁҙиЁҹгҒӘгҒ©гҒ®зөҢйҒҺгӮ„гҒқгҒ®зөҗжң«гӮӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒқгӮҢгҒЁгҒҜйҒ•гҒЈгҒҹж„Ҹе‘ігҒ§еҫ—гӮӢгҒ№гҒҚж•ҷиЁ“гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдәӢж•…гҒ®еҶҚзҷәйҳІжӯўгҒ«иіҮгҒҷгӮӢгҒҜгҒҡгҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӮгҒЁгҖҒгӮӮгҒҶдёҖзӮ№гҖҒдәӨжёүгҖҒиЈҒеҲӨгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҒ®еҢ»зҷӮеҒҙд»ЈзҗҶдәәгҒ®дәүгҒ„ж–№гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгӮ’еҪўгҒ«ж®ӢгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮгҒҫгҒҹгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…зҷәз”ҹеҫҢгҒ®дәӨжёүгӮ„иЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒ®гҒӮгӮҠж–№гӮ’еҗ«гӮҒгҖҒдёҚжҜӣгҒӘзҙӣдәүгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢж„Ҹе‘ігҒ§гӮ„гҒҜгӮҠж•ҷиЁ“гҒ«гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…иЁҙиЁҹгҒҜгҒҫгҒ гҒҫгҒ жңӘжҲҗзҶҹгҒӘй ҳеҹҹгҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒиЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒ«й–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ и©ҰиЎҢйҢҜиӘӨгҒҢз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒдёӯгҒ«гҒҜгҖҒзңҹзӣёи§ЈжҳҺгҒЁгҒ„гҒҶиҰізӮ№гҒӢгӮүиҰӢгҒҰйҖҶиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘе®ҹеӢҷгҒ®йҒӢз”ЁгӮӮе°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒҡгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еӨҡгҒҸгҒ®е ҙеҗҲгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҖӢгҖ…гҒ®иЈҒеҲӨе®ҳгӮӮйқһеёёгҒ«еҠӘеҠӣгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒҜгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒиЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒ®йҖІгӮҒж–№гҖҒдё»ејөз«ӢиЁјиІ¬д»»гҒ®еҲҶй…ҚгҒ®е•ҸйЎҢгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒж”№е–„гҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚзӮ№гҒҜйқһеёёгҒ«еӨҡгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢзҺҮзӣҙгҒӘж„ҹжғігҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢзөҢйЁ“гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒ—гҖҒгҒҫгҒҹж”№е–„гҒҷгҒ№гҒҚе•ҸйЎҢзӮ№гӮ’жҢҮж‘ҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮиЁҙиЁҹгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒ«иүҜгҒ„еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҒЁзўәдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬д»¶дәӢж•…гҒ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒ•гҒ—гҒҸгҒқгҒҶгҒ—гҒҹиЈҒеҲӨжүҖгҒ®жүӢз¶ҡгӮ„дё»ејөз«ӢиЁјиІ¬д»»гҒ®еҲҶй…ҚгҒ®е•ҸйЎҢзӯүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁиҖғгҒҲгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢеұҖйқўгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒжң¬ж–ҮдёӯгҒ§и§ҰгӮҢгҒҰиЎҢгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬ж–ҮгҒ«е…ҘгӮӢеүҚгҒ«гӮӮгҒҶдёҖзӮ№жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гҖҒдәӢж•…гҒ®зңҹзӣёз©¶жҳҺгҖҒиў«е®іиҖ…гҒ®ж•‘жёҲгҖҒдәӢж•…гҒ®еҶҚзҷәйҳІжӯўгӮ’зӣ®зҡ„гҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҖӢгҖ…гҒ®еҢ»зҷӮиҖ…гҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ®е®ҹеҗҚгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҖҒгӮ„гӮҠзҺүгҒ«жҢҷгҒ’гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰиЎҢгӮҸгҒӘгҒ„ж–№йҮқгҒ§иҮЁгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷпјҲгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒдәӢ件гҒ®еҶ…е®№гӮ„дәӢж•…еҫҢгҒ®еҜҫеҝңгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдҫӢеӨ–гҒҢгҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮдәӢ件гҒҢзөӮдәҶгҒ—гҒҹжҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгҖҢгғҺгғјгӮөгӮӨгғүгҖҚгҒ®зІҫзҘһгҒ§еҗ‘гҒҚеҗҲгҒ„гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјүгҖӮ
еҢ»зҷӮиҖ…гҒ®ж–№гҖ…гӮӮжң¬зЁҝгӮ’гҒ”иҰ§гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒҜз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еёҢжңӣгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒ®и¶Јж—ЁгӮ’йҮҚгҖ…гҒ”зҗҶи§ЈгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгӮҲгҒҶгҖҒгҒ©гҒҶгҒӢгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҒҠйЎҳгҒ„з”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒжң¬зЁҝгҒҜйқһеёёгҒ«й•·гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒд»ҠеӣһгҒҜPARTпј‘гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬д»¶гҒҜе№іжҲҗпј’пј”е№ҙгҒ«еёӮдёӯгҒ®ж•ҙеҪўеӨ–科гӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиө·гҒҚгҒҹеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ§гҒҷгҖӮ
иӢҘгҒҸеҒҘеә·гҒӘйқ’е№ҙгҒҢгҖҒиӮ©гҒ“гӮҠгҒ®жІ»зҷӮгҒ§гҖҒең°е…ғгҒ®ж•ҙеҪўеӨ–科гӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ§гғҲгғӘгӮ¬гғјгғқгӮӨгғігғҲжіЁе°„гӮ’ж–ҪиЎҢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒдҪҝз”ЁгҒ—гҒҹеұҖжүҖйә»й…”и–¬гҒҢй ҡеӢ•и„ҲеҶ…гҒ«иӘӨгҒЈгҒҰжіЁе…ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬гҒҢи„ігҒ®дёӯжһўгҒ«дҪңз”ЁгҒ—гҒҰгҖҒж–ҪиЎ“гҒ®зӣҙеҫҢгҒ«ж„Ҹиӯҳж¶ҲеӨұгҒӢгӮүеҝғеҒңжӯўгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еҫҢж•‘жҖҘиҰҒи«ӢгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒдҪҺй…ёзҙ и„із—ҮгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒжӯ»дәЎгҒҷгӮӢгҒ«иҮігҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢж•…гҒ§гҒҷгҖӮ
гғҲгғӘгӮ¬гғјгғқгӮӨгғігғҲжіЁе°„гҒЁгҒҜгҖҒзҘһзөҢгғ–гғӯгғғгӮҜжіЁе°„гҒЁдјјгҒҹжІ»зҷӮгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒең§з—ӣзӮ№гҒ«еұҖжүҖйә»й…”и–¬гӮ’жіЁе°„гҒ—гҒҰз—ӣгҒҝгӮ„гҒ—гҒігӮҢгҒӘгҒ©гҒ®з—ҮзҠ¶гӮ’и»Ҫеҝ«гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжІ»зҷӮгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгғӘгғүгӮ«гӮӨгғіпјҲи–¬е“ҒеҗҚгӮӯгӮ·гғӯгӮ«гӮӨгғіпјүзӯүгҒ®еұҖжүҖйә»й…”и–¬гҒ«гҒҜзҘһзөҢжҜ’жҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒи„ігҒёгҒ®дёӯжһўгҒ«дҪңз”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒе°‘йҮҸгҒ§гӮӮж„Ҹиӯҳж¶ҲеӨұгҖҒеҝғеҒңжӯўгҒ«йҷҘгӮүгҒӣгӮӢеҚұйҷәгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜйә»й…”科гҖҒгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ®й ҳеҹҹгҒ§гҒҜгҒ”гҒҸеҹәжң¬зҡ„гҒӘеҢ»еӯҰзҡ„зҹҘиҰӢгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ»гҒӢгҒ«гӮӮгӮўгғҠгғ•гӮЈгғ©гӮӯгӮ·гғјгӮ·гғ§гғғгӮҜгӮ„иҝ·иө°зҘһзөҢеҸҚе°„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹз—ҮзҠ¶гӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҘөгӮҒгҒҹзҹӯжҷӮй–“гҒ®еҶ…гҒ«еҝғеҒңжӯўгҒЁгҒ„гҒҶдәӢж…ӢгӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸ—д»»еҫҢгҖҒжң¬д»¶жӮЈиҖ…гҒ®жӯ»дәЎгҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж©ҹеәҸгҒ§з”ҹгҒҳгҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжіЁж„ҸгӮ’жү•гӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒӢгӮ’и§ЈжҳҺгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎд»ЈзҗҶдәәгҒҜгҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁеҫҢгҖҒгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еұҖжүҖйә»й…”и–¬дёӯжҜ’гҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘж©ҹеәҸгҒҜгҖҒиЎҖз®ЎеҶ…гҒёгҒ®иӘӨжіЁе…ҘгҒ®гҒҝгҒ§з”ҹгҒҳгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҖҒеұҖжүҖйә»й…”и–¬дёӯжҜ’гӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒҹгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒҢйҒҺеӨұгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҖӢгҖ…гҒ®з—ҮдҫӢгҒ«еҝңгҒҳгҒҹе…·дҪ“зҡ„гҒӘжӨңиЁјгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®зӮ№гҖҒзӣёи«ҮгҒ—гҒҹгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гҒ®ж„ҸиҰӢгҒҜжҘөгӮҒгҒҰжҳҺеҝ«гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒж©ҹеәҸгҒ®зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгғҲгғӘгӮ¬гғјгғқгӮӨгғігғҲжіЁе°„гҒ§дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹеұҖжүҖйә»й…”и–¬гҒҢиӘӨгҒЈгҒҰй ҡеӢ•и„ҲеҶ…гҒ«жіЁе…ҘгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒжҘөгӮҒгҒҰзҹӯжҷӮй–“гҒ§и„ігҒ®дёӯжһўгҒ«дҪңз”ЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиӘӨжіЁе…ҘгҒ®зӣҙеҫҢгҒ«гҖҒж„Ҹиӯҳж¶ҲеӨұгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰеҝғеҒңжӯўгҒ«иҮігӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжң¬д»¶гҒ®е ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж©ҹеәҸгӮ’иҫҝгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«з–‘гҒҶдҪҷең°гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж©ҹеәҸгҒ®зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжң¬д»¶гҒ§гҒҜгҖҒеҪ“еҲқгҖҒиў«е‘ҠеҒҙгӮӮдәүгҒҶе§ҝеӢўгҒҜиҰӢгҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒйҖ”дёӯгҒ§гҒқгӮҢгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢе§ҝеӢўгҒ«и»ўгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒйҒҺеӨұгҒ®зӮ№гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӨ§гҒҚгҒҸеҲҶгҒ‘гҒҰ2зӮ№гҒҢе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒиӘӨжіЁе…ҘгҒ•гҒӣгҒҹгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒ®йҒҺеӨұгҒ§гҒҷгҖӮ
жӮЈиҖ…гҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгӮҢгҒ°гҖҒиӮ©гҒ“гӮҠгҒ®жІ»зҷӮгҒ®гҒӨгӮӮгӮҠгҒ§ж•ҙеҪўеӨ–科гӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰеҝғеҒңжӯўгҒ«иҮігӮӢгҒӘгӮ“гҒҰгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠеҫ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘи©ұгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиӘӨжіЁе…ҘгҒ•гҒӣгҒҹгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒҢгҒЁгӮ“гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҒ®жіЁе°„гҒ®жүӢжҠҖгҒ§гҒҜгҖҒгғҗгғғгӮҜгғ•гғӯгғјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒжіЁе°„з®ЎгҒёгҒ®иЎҖж¶ІгҒ®йҖҶжөҒгҒ®жңүз„ЎгӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹжіЁе…ҘйҮҸгӮ’е°‘гҒӘгӮҒгҒ«гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®еҜҫеҮҰгҒҢз”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒҹгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒ«йҮҚеӨ§гҒӘйҒҺеӨұгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒзӣёи«ҮгҒ—гҒҹгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гҒҜгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘгҒ«жіЁж„ҸгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒиӘӨжіЁе…ҘгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’пј‘пјҗпјҗпј…жҺ’йҷӨгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҗгғғгӮҜгӮ№гғ•гғӯгғјгҒӘгҒ©гҒ®ж…ҺйҮҚгҒӘжүӢжҠҖгӮ’жҖ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒӘе ҙеҗҲд»ҘеӨ–гҒҜгҖҒгҒқгӮҢиҮӘдҪ“гӮ’йҒҺеӨұгҒЁе•ҸгҒҶгҒ®гҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶи©ұгӮӮгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгғҲгғӘгӮ¬гғјгғқгӮӨгғігғҲжіЁе°„гӮ„зҘһзөҢгғ–гғӯгғғгӮҜжіЁе°„гҒ«гҒҜиӘӨжіЁе…ҘгҒ«гӮҲгӮӢеҝғеҒңжӯўгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷгғӘгӮ№гӮҜгҒҢеӯҳгҒҷгӮӢд»ҘдёҠгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒ®жүӢжҠҖгӮ’иЎҢгҒҶеҢ»её«гҒҢгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘж•‘е‘ҪеҮҰзҪ®гӮ’еҹ·гӮӢгҒ№гҒҚгҒҜеҪ“然гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®зӮ№гҒ®йҒҺеӨұгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ•гҒҲйҒ©еҲҮгҒ«е®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°еҪ“然гҒ«ж•‘е‘ҪгҒ§гҒҚгҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢе°Ӯй–ҖеҢ»гҒ®иҰӢи§ЈгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘж•‘е‘ҪеҮҰзҪ®гҒҢеҹ·гӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еҢ»её«гҒ®жіЁж„Ҹзҫ©еӢҷйҒ•еҸҚпјҲйҒҺеӨұпјүгҒЁгҒ—гҒҰж§ӢжҲҗгҒ—гҖҒе№іжҲҗ28е№ҙгҒ«иЁҙиЁҹжҸҗиө·гҒ«иёҸгҒҝеҲҮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иЁҙиЁҹгҒҢй–Ӣе§ӢгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒгӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜеҒҙгҒӢгӮүгҒҜй©ҡгҒҸгҒ№гҒҚдё»ејөгҒҢеҮәгҒҰжқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёҖгҒӨгҒҜгҖҒеҝғеҒңжӯўжҷӮгҒ«гӮўгғүгғ¬гғҠгғӘгғіпјҲгӮЁгғ”гғҚгғ•гғӘгғіпјүгӮ’жҠ•дёҺгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢж•‘е‘ҪеҮҰзҪ®гҒЁгҒ—гҒҰдёҚйҒ©еҲҮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдё»ејөгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢиҮӘдҪ“гҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒ«иӘӨгҒЈгҒҹдё»ејөгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеҫҢгҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®й©ҡгҒҸгҒ№гҒҚдё»ејөгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒдәӢж•…зҷәз”ҹгҒ®жҷӮзі»еҲ—гҒ«й–ўгҒҷгӮӢдәӢе®ҹдё»ејөгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒжҗ¬йҖҒе…ҲгҒ®еӨ§еӯҰз—…йҷўгҒ«иў«е‘ҠеҢ»её«гҒҢеҗҢиЎҢгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжҗ¬йҖҒе…ҲгҒ§гҖҒгғҲгғӘгӮ¬гғјгғқгӮӨгғігғҲжіЁе°„гҒ®е®ҹж–ҪжҷӮеҲ»гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеҚҲеүҚ9жҷӮ20еҲҶгҒЁиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒ—гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢдёҖеәҰи©ұгӮ’иҒһгҒ„гҒҹжҷӮгӮӮгҖҒиў«е‘ҠеҢ»её«гҒҜгҖҒжіЁе°„гҒ®жҷӮеҲ»гҒҜеҚҲеүҚ9жҷӮеҚҠеүҚеҫҢгҒЁиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёҖж–№гҖҒжҖҘеӨүеҫҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«ж•‘жҖҘиҰҒи«ӢпјҲ119з•ӘйҖҡе ұпјүгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒҜеҚҲеүҚ9жҷӮ55еҲҶгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®й–“гҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢж•‘е‘ҪеҮҰзҪ®гҒҢдёҚйҒ©еҲҮгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ„ж•‘жҖҘиҰҒи«ӢгҒ®йҒ…гӮҢгӮ’жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒиў«е‘ҠгҒҜгҖҒиЁҙиЁҹгҒ®дёӯгҒ§гҖҒжҖҘеӨүгҒ—гҒҹжҷӮеҲ»гҒҢеҚҲеүҚ9жҷӮ55еҲҶй ғгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҖҘеӨүгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§зӣҙгҒЎгҒ«ж•‘жҖҘиҰҒи«ӢгӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдё»ејөгӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷпјҲжіЁе°„зӣҙеҫҢгҒ®жҖҘеӨүгҒЁгҒ„гҒҶеүҚжҸҗгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжіЁе°„гҒ®жҷӮеҲ»гӮӮгҒқгӮҢгҒ«иҝ‘жҺҘгҒ—гҒҹжҷӮеҲ»гҒЁгҒ„гҒҶдё»ејөгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиў«е‘ҠеҒҙдё»ејөгҒҜгҖҒдәӢе®ҹзөҢйҒҺгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮдёҚиҮӘ然гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиў«е‘ҠеҢ»её«иҮӘиә«гҒ®дәӢж•…зӣҙеҫҢгҒ®иӘ¬жҳҺгҒЁгӮӮзҹӣзӣҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒ©гҒҶиҰӢгҒҰгӮӮз„ЎзҗҶгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒе•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиҚ’е”җз„ЎзЁҪгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘиў«е‘ҠеҒҙгҒ®жҷӮзі»еҲ—дё»ејөгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҒқгӮҢгӮ’жҳҺзўәгҒ«жҺ’ж–ҘгҒ—гҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҖҒиЁҙиЁҹгҒҢ5е№ҙзӣ®гҒ«гҒҫгҒ§зӘҒе…ҘгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹпјҲгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҒқгҒ®й–“гҒ«ж§ҳгҖ…гҒӘдё»ејөз«ӢиЁјжҙ»еӢ•гӮ’йҮҚгҒӯгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјүгҖӮ
жңҹж—ҘгҒҢйҮҚгҒӯгӮүгӮҢгӮӢдёӯгҒ§гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®иЈҒеҲӨдҪ“гҒ®йғЁй•·гҒҢгҖҒиў«е‘ҠеҒҙгҒ®жҷӮзі»еҲ—гҒ«й–ўгҒҷгӮӢдё»ејөгҒ«гҒҜз„ЎзҗҶгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҷӮзі»еҲ—гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҝғиЁјгӮ’еҫ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘзҷәиЁҖгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®иЈҒеҲӨе®ҳгҒҢи»ўеӢӨгҒ§дәӨд»ЈгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§гҒқгҒ®еҝғиЁјй–ӢзӨәгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зҷҪзҙҷгҒ«жҲ»гӮҠгҖҒд»ҘеҫҢгӮӮиў«е‘ҠеҒҙгҒҜгҒ“гҒ®жҷӮзі»еҲ—гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҚ’е”җз„ЎзЁҪгҒӘдё»ејөгӮ’гҒІгҒЈгҒ“гӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
зөҗи«–зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢеҺҹе‘ҠеӢқиЁҙгҒ®еҝғиЁјгӮ’й–ӢзӨәгҒ—гҒҰиў«е‘ҠеҒҙгҒ®дёҚеҗҲзҗҶгҒӘжҷӮзі»еҲ—дё»ејөгҒҜжҺ’ж–ҘгҒ•гӮҢгҒҰе’Ңи§ЈгҒ«гҒ“гҒҺгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®иЁҙиЁҹгҒ«гҒҜиүІгҖ…гҒӘж„Ҹе‘ігҒ§еҫ—гӮӢгҒ№гҒҚж•ҷиЁ“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒ«еҲҶгҒ‘гҒҰгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒй•·гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒPARTпј’гҒёгҒЁз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһз—…йҷўеҶ…гҒ§гҒ®е…ҘжөҙдёӯгҒ®жәәжӯ»дәӢж•…гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжҸҗиЁҙгҒ®гҒ”е ұе‘Ҡ
гҒ“гҒ®гҒҹгҒігҖҒзҘһеҘҲе·қзңҢеҶ…гҒ®гҒӮгӮӢз·ҸеҗҲз—…йҷўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе…ҘжөҙдёӯгҒ®жәәжӯ»дәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжҸҗиЁҙгҒ®йҒӢгҒігҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ”е ұе‘ҠгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еҗҢдәӢ件гҒҜгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠеүҚгҒ®дәӢж•…гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҲҘдәӢжғ…гҒ§жҸҗиЁҙгҒ«жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҖҒгӮ„гҒЈгҒЁжҸҗиЁҙгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дәӢ件гҒ®жҰӮз•ҘгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒпј—пјҗеҸ°гҒ®й«ҳйҪўгҒ®з”·жҖ§гҒҢең°е…ғгҒ®з·ҸеҗҲз—…йҷўгҒ«е…ҘйҷўгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰж•°ж—ҘеҫҢгҒ«гҖҒеҚҳзӢ¬гҒ§е…ҘжөҙгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒжөҙж§ҪеҶ…гҒ§жәәжӯ»гҒ—гҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ§зҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®з”·жҖ§гҒҜгҖҒдәӢж•…д»ҘеүҚгҒӢгӮүзі–е°ҝз—…гҒЁиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«зҪ№жӮЈгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҖҒжң¬д»¶дәӢж•…гҒ®е°‘гҒ—еүҚгҒ«гӮӮиҮӘе®…еҶ…гҒ§еҖ’гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮ’зҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҖҒдәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгҒҹеҗҢгҒҳз—…йҷўгҒ«е…ҘйҷўгҒ—гҖҒгҒқгҒ®йҡӣгҒ«гҒҜе…ҘжөҙгҒҜиЁұеҸҜгҒ•гӮҢгҒҡгҖҒжё…жӢӯгҒ®гҒҝгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶзөҢз·ҜгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒдәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгӮӢе…ҘйҷўгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҖҒеҗҢгҒҳз—…йҷўгҒ®гӮұгғјгӮ№гғҜгғјгӮ«гғјгҒӢгӮүеә—й ӯгҒ®жҒҗгӮҢгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶзөҢз·ҜгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒзі–е°ҝз—…жӮЈиҖ…гҒҜгҖҒдҪҺиЎҖзі–гҒ§гҒӮгӮҢгҖҒй«ҳиЎҖзі–гҒ§гҒӮгӮҢгҖҒж„Ҹиӯҳж¶ҲеӨұгӮ„гҒөгӮүгҒӨгҒҚгҒҢиө·гҒҚгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒиӘҚзҹҘз—ҮжӮЈиҖ…гӮӮеҗҢж§ҳгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгӮҶгҒҲгҖҒжң¬дәӢ件гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘи»ўеҖ’гӮ„ж„Ҹиӯҳж¶ҲеӨұгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒ®й«ҳгҒ„жӮЈиҖ…гӮ’еҚҳзӢ¬гҒ§е…ҘжөҙгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁұеҸҜгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҢ»зҷӮиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жіЁж„Ҹзҫ©еӢҷйҒ•еҸҚгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз—…йҷўеҒҙгҒ«иІ¬д»»гӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгӮҲгҒҶжұӮгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒз—…йҷўеҒҙгҒҢйҒҺеӨұгӮ’еҗҰе®ҡгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒд»ҠеӣһгҒ®жҸҗиЁҙгҒ«иҮігҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
и¶…й«ҳйҪўеҢ–зӨҫдјҡгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹж—Ҙжң¬гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮҢгҖҒзҰҸзҘүж–ҪиЁӯгҒ§гҒӮгӮҢгҖҒд»ҠеҫҢгҖҒеҗҢзЁ®гҒ®дәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҜйқһеёёгҒ«й«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒиЈҒеҲӨгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒжң¬д»¶гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҢ»зҷӮиҖ…гҖҒзҰҸзҘүй–ўдҝӮиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҜҫеҝңгӮ’гҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҸҜиғҪгҒӘйҷҗгӮҠгҒ®е•ҸйЎҢжҸҗиө·гӮ’иЎҢгҒ„гҖҒиӯҰйҗҳгӮ’йіҙгӮүгҒ—гҒҰиЎҢгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®иЈҒеҲӨгҒ®зөҢйҒҺгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»ҠеҫҢгҖҒзҜҖзӣ®зҜҖзӣ®гҒ§гҒ”е ұе‘ҠгҒ—гҒҰгҒҫгҒ„гӮҠгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһеҺҡеҠҙзңҒгҒҢе®ҡгӮҒгҒҹгҖҢдёүеҺҹеүҮгҖҚгӮ’е®ҲгӮүгҒӘгҒ„йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁPart1
жңҖиҝ‘иЎҢгҒЈгҒҹиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ§е‘ҶгӮҢгҒӢгҒҲгӮӢгҒҸгӮүгҒ„гҒ§гҒҹгӮүгӮҒгҒӘйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ«еҮәгҒҸгӮҸгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁз”ұгҖ…гҒ—гҒҚе•ҸйЎҢгӮ’еҗ«гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҸ—д»»дәӢ件гҒҜж•ҙеҪўеӨ–科гҒ®з—ҮдҫӢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҢ»её«гҒ®иҗҪгҒЎеәҰгҒҜжҳҺзҷҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒӢгҒӨзөҗжһңгӮӮйқһеёёгҒ«йҮҚеӨ§гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹдәӢж•…гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҷгҒ§гҒ«д»»ж„Ҹй–ӢзӨәгҒ§дёҖйғЁгҒ®иЁҳйҢІгҒҜе…ҘжүӢжёҲгҒҝгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒжүӢиЎ“иЁҳдәӢгҒ«иӮқеҝғгҒӘзөҢйҒҺгҒҢиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҖҒиЁҳијүеҶ…е®№гҒ«з–‘зҫ©гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒж”№гҒ–гӮ“гҒ•гӮҢгҒҹеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®з”із«ӢгҒ«иёҸгҒҝеҲҮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҪ“ж—ҘгҖҒз—…йҷўгҒ«иөҙгҒҸгҒЁгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«дјҡиӯ°е®ӨгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе ҙжүҖгҒ«еҢ»зҷӮиЁҳйҢІдёҖејҸгҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ§гҒҜгҒ гӮҒгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’е‘ҠгҒ’гҖҒгғ‘гӮҪгӮігғігҒ®з”»йқўдёҠгҒ§гғҮгғјгӮҝгҒ®жӣҙж–°еұҘжӯҙгӮ„гҖҒеҮәеҠӣз”»йқўгҒ§жјҸгӮҢгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁи©ұгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдәӢеӢҷж–№гҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒҜгҖҒгҒқгҒ®зҗҶз”ұгҒҢгӮҲгҒҸзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒҜеҡҷгҒҝеҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒҢз¶ҡгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒ®дёӯгҒ§гҖҒдәӢеӢҷж–№гҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒ«гҖҒгҖҢгҒ“гҒ®з—…йҷўгҒ®йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒҜгҒ©гҒ“гҒ®гғҷгғігғҖгғјгҒ®гӮӮгҒ®гҒӢгҖҚгҒЁе°ӢгҒӯгҒҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҖҢиҮӘеүҚгҒ§ж§ӢзҜүгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиӘ¬жҳҺгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иҮӘеүҚгҒ§ж§ӢзҜүгҒ—гҒҹйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ«еҮәгҒҸгӮҸгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜ2еәҰзӣ®гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁе«ҢгҒӘдәҲж„ҹгҒҢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒҜгҖҒеҗҢгҒҳгғҷгғігғҖгғјгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гӮӮгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ®иҰҒжұӮгӮ„е®ҹжғ…гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰд»•ж§ҳгҒҢгӮўгғ¬гғігӮёгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдҝқе…ЁгҒ®йҡӣгҒ«гҒқгӮҢгҒ«еҝңгҒҳгҒҹеҜҫеҝңгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҖҒгҒҰгҒ“гҒҡгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиҮӘеүҚгҒ®йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгӮҲгӮҠз—…йҷўеҒҙгҒ«йғҪеҗҲгҒ®гӮҲгҒ„д»•ж§ҳгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдәҲжғігҒ•гӮҢгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
жң¬жқҘгҖҒд»ҠеӣһгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢиЁәзҷӮжңҹй–“гҒҜе®ҹиіӘзҡ„гҒ«гҒҜ3ж—Ҙй–“гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«иЎҢгҒ‘гҒ°еҚҲеҫҢ4жҷӮеүҚгҒ«гҒҜзөӮгӮҸгӮӢгҒЁиёҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒгҒ“гҒ®е«ҢгҒӘдәҲж„ҹгҒҢзҡ„дёӯгҒҷгӮӢдәӢж…ӢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢеӢҷж–№гҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒ§гҒҜеҹ’гҒҢжҳҺгҒӢгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгӮ’жүұгҒҲгӮӢеҲҘгҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒҢеҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгғҺгғјгғҲгғ‘гӮҪгӮігғігҒ§гҒҜеҚ°еҲ·гҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§пјҲгҒқгӮҢгӮӮгҒҠгҒӢгҒ—гҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢпјүгҖҒгғҮгӮ№гӮҜгғҲгғғгғ—гғ‘гӮҪгӮігғігҒҢзҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢдәӢеӢҷеұҖгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ«жЎҲеҶ…гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒй©ҡж„•гҒ®дәӢе®ҹгӮ’зҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®з—…йҷўгҒ®йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®иЁҳијүгҒ®жӣҙж–°еұҘжӯҙгӮ’з”»йқўдёҠгҒ«иЎЁзӨәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒжӣҙж–°еұҘжӯҙгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгғ—гғӘгғігғҲгӮўгӮҰгғҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢгҒқгӮ“гҒӘгҒ°гҒӢгҒӘгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҖҢдҪ•гҒЁгҒӢиЎЁзӨәгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖҚгҒЁйЈҹгҒ„дёӢгҒҢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжӢ…еҪ“иҖ…гҒҜгҖҒгҖҢгҒқгҒҶгҒ„гҒҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гӮҲгҒҶгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖҚгҒЁзӯ”гҒҲгӮӢгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒӮгҖҒгҒ“гҒҶжӣёгҒҸгҒЁгҒ«гҒ№гӮӮгҒӘгҒ„еҜҫеҝңгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҒһгҒ“гҒҲгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒжӢ…еҪ“иҖ…гҒ®ж–№гҒҜгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮиӘ е®ҹгҒӘж–№гҒ§гҖҒе°ӢгҒӯгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮӮгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁзӯ”гҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гӮҠгҖҒиҰҒжұӮгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮӮе«ҢгҒӘйЎ”гӮ’гҒҝгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒҸдёҒеҜ§гҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»•ж§ҳгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§еҰӮдҪ•гҒЁгӮӮгҒ—йӣЈгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§з”ігҒ—иЁігҒӘгҒ•гҒқгҒҶгҒӘж§ҳеӯҗгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҢжӣҙж–°еұҘжӯҙгҒҢиЎЁзӨәгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖҚгҖҢеҚ°еҲ·гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдёҚе…·еҗҲгҒҜгҖҒдёҖиҲ¬гҒ®ж–№гҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгғ”гғігҒЁгҒ“гҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢиЁјжӢ дҝқе…ЁгӮ’иЎҢгҒҶзӣ®зҡ„гҒҜгҖҒгҒқгҒ®жҷӮзӮ№гҒҫгҒ§гҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰе…ҘжүӢгҒ—гҖҒзңҹзӣёи§ЈжҳҺгҒ«еҪ№з«ӢгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®жӣҙж–°еұҘжӯҙгҒҢдҝқе…ЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜиЁјжӢ дҝқе…ЁгӮ’иЎҢгҒҶж„Ҹе‘ігҒҢгҒӘгҒ„гҒ«зӯүгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгӮ«гғ«гғҶгҒ®ж”№гҒ–гӮ“гҒҜгҖҒж—ҘеёёиҢ¶йЈҜдәӢгҒЁгҒҫгҒ§гҒҜиЁҖгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒ全然зҸҚгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒжӣҙж–°гҒ•гӮҢгӮӢеүҚгҒ®иЁҳдәӢгӮ’жӨңиЁјгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҝ…иҰҒдёҚеҸҜж¬ гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’йҳІжӯўгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҺҡеҠҙзңҒгҒҢе®ҡгӮҒгҒҹгҖҢдёүеҺҹеүҮгҖҚгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒҜеүҚгҒ«гӮӮжӣёгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҶҚеәҰжӣёгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮӮгҒқгӮӮгҖҒгӮ«гғ«гғҶгҒҜзҙҷеӘ’дҪ“гҒ«гӮҲгӮӢдҝқеӯҳгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®иҰҸеҲ¶гҒҢз·©е’ҢгҒ•гӮҢгҖҒйӣ»еӯҗдҝқеӯҳгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹйҡӣгҒ«гҖҒеҺҡеҠҙзңҒгҒҜгҖҒгҖҢйӣ»еӯҗдҝқеӯҳгҒ®дёүеҺҹеүҮгҖҚгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’е®ҡгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®дёүеҺҹеүҮгҒЁгҒҜгҖҒгҖҢзңҹжӯЈжҖ§гҖҚгҖҢиҰӢиӘӯжҖ§гҖҚгҖҢдҝқеӯҳжҖ§гҖҚгҒ®пј“гҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еҶ…гҖҒгҖҢзңҹжӯЈжҖ§гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒжӯЈеҪ“гҒӘдәәгҒҢиЁҳйҢІгҒ—зўәиӘҚгҒ•гӮҢгҒҹжғ…е ұгҒ«й–ўгҒ—第дёүиҖ…гҒӢгӮүиҰӢгҒҰдҪңжҲҗгҒ®иІ¬д»»гҒ®жүҖеңЁгҒҢжҳҺзўәгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒӢгҒӨгҖҒж•…ж„ҸгҒҫгҒҹгҒҜйҒҺеӨұгҒ«гӮҲгӮӢгҖҒиҷҡеҒҪе…ҘеҠӣгҖҒжӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҖҒж¶ҲеҺ»гҖҒеҸҠгҒіж··еҗҢгҒҢйҳІжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒгҖҢиҰӢиӘӯжҖ§гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒйӣ»еӯҗеӘ’дҪ“гҒ«дҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҒҹеҶ…е®№гӮ’гҖҒжЁ©йҷҗдҝқжңүиҖ…гҒӢгӮүгҒ®иҰҒжұӮгҒ«еҹәгҒҘгҒҚеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰиӮүзңјгҒ§иҰӢиӘӯеҸҜиғҪгҒӘзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҖҢиЁәзҷӮгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«ж”ҜйҡңгҒҢз„ЎгҒ„гҒ“гҒЁгҖҚгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҖҢзӣЈжҹ»зӯүгҒ«е·®гҒ—ж”ҜгҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгӮӮеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҖҢдҝқеӯҳжҖ§гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒиЁҳйҢІгҒ•гӮҢгҒҹжғ…е ұгҒҢжі•д»ӨзӯүгҒ§е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹжңҹй–“гҒ«жёЎгҒЈгҒҰзңҹжӯЈжҖ§гӮ’дҝқгҒЎгҖҒиҰӢиӘӯеҸҜиғҪгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ§дҝқеӯҳгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜеҺҡеҠҙзңҒгҒ®гӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйӣ»еӯҗгғҮгғјгӮҝгҒ§гҒӮгӮӢйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®е ҙеҗҲгҖҒе®№жҳ“гҒ«жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒз—•и·ЎгӮ’ж®ӢгҒ•гҒҡж”№гҒ–гӮ“гҒ§гҒҚгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶд»Јзү©гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҖҢзҙҷгӮ«гғ«гғҶгҒЁеҗҢзӯүгҒ®гӮӮгҒ®гҖҚгҒҢзўәдҝқгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгӮҸгҒ‘гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®з—…йҷўгҒ®йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еҶ…гҒ®гҖҢиҰӢиӘӯжҖ§гҖҚгҒ®еҺҹеүҮгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒқгҒҶгҒҜгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫеё°гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ«гҒҜиЎҢгҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒ“гҒӢгӮүгҖҒзҸҫе ҙгҒ§гҒ®жӮӘжҲҰиӢҰй—ҳгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жңҖеҲқгҒ«гӮӮжӣёгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®зңҹзӣёз©¶жҳҺгҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜйқһеёёгҒ«з”ұгҖ…гҒ—гҒҚе•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰгҖҒPart2гҒ«з¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһеҢ»зҷӮдәӢ件гҒЁгҖҢгғ—гғ¬гӮјгғігҖҚ
е…Ҳж—ҘгҖҒгҒӮгӮӢеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ§гғ—гғ¬гӮјгғігғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒӘгӮӢгӮӮгҒ®пјҲд»ҘдёӢгҖҢгғ—гғ¬гӮјгғігҖҚгҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷпјүгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰжқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иЁҙиЁҹиҮӘдҪ“гҒҜгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠйҖІиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶жіҒгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®еүҚгҒ§гҖҒдәӢ件гҒ§зӣ®гӮ’еҗ‘гҒ‘гӮӢгҒ№гҒҚгғқгӮӨгғігғҲгҖҒиЁјжӢ гҒ®гҒӮгӮӢгҒ№гҒҚи©•дҫЎгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒҜгҖҢгҒӮгӮҠгҖҚгҒ гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгӮҠгӮӮгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжә–еӮҷгӮ’гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚж„ҹгҒҳгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒ“гҒ®жүӢжі•гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮүгӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒжӨңиЁјгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҖҒгҖҢгғ—гғ¬гӮјгғігҖҚгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒгғ—гғ¬гӮјгғігҒЁгҒҜдҪ•гҒһгӮ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиҰҒгҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иЁҙиЁҹгҒ®зөҢйҒҺгҖҒеҸҢж–№гҒӢгӮүжҸҗеҮәгҒ•гӮҢгҒҹдё»ејөжӣёйқўгӮ„иЁјжӢ гӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҖҒеҰӮдҪ•гҒ«иҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®дё»ејөгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒӢгӮ’гӮўгғ”гғјгғ«гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдјҒжҘӯгҒӘгҒ©гҒ§гҒҜдјҒз”»е–¶жҘӯгҖҒгӮігғігғҡгҒӘгҒ©гҒ§гӮҸгӮҠгҒЁжҷ®йҖҡгҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғ—гғ¬гӮјгғігҒҢдё»ејөгҖҒиЁјжӢ гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰиЈҒеҲӨжүҖгҒ«еҝғиЁјгӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҖҒзҷҪй»’гӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиЁҙиЁҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰзӣёеҝңгҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒзҸҫжҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгӮ„гҒҜгӮҠз–‘е•ҸгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дҪ•гӮҲгӮҠгӮӮиЁҙиЁҹдёҠгҒ®дҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гҒҢгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгҒ“гҒ®зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜд»ҠеӣһгҒ®иЈҒеҲӨе®ҳгӮӮиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғ—гғ¬гӮјгғіиҮӘдҪ“гҒҜиЁјжӢ гҒ§гӮӮгҒӘгҒҸдё»ејөгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҖҢгҒӘгӮӢгҒ»гҒ©гҒқгҒҶгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгҖҚгҒЁгғқгғігҒЁиҶқгӮ’еҸ©гҒ„гҒҰзҙҚеҫ—гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮҢгҒ°дҪ•гӮҲгӮҠгҒ гҒ—гҖҒжә–еӮҷгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжҷӮгҒҜгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҒқгҒҶгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§дё»ејөгӮ„иЁјжӢ гӮ’ж•ЈгҖ…жҸҗеҮәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®гғ—гғ¬гӮјгғігҒ®е·§жӢҷгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұәзқҖгҒҢгҒӨгҒ„гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶж„ҹгҒҳгҒ§дёҚе®үгӮ„з–‘е•ҸгҒҢ湧гҒ„гҒҰжқҘгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ§гӮӮгҒҫгҒӮгҖҒгӮ„гӮӢгҒЁжұәгӮҒгҒҹд»ҘдёҠгҖҒжә–еӮҷгӮ’гҒ—гҒҰиҮЁгӮҖгҒ—гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гғ—гғ¬гӮјгғіеҪ“ж—ҘгӮ’иҝҺгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ§гҒ©гҒҶгҒ гҒЈгҒҹгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒзӣёеӨүгӮҸгӮүгҒҡгӮӮгӮ„гҒЈгҒЁгҒ—гҒҹгҒҫгҒҫгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®дәӢ件гҒ®гғ—гғ¬гӮјгғігҒҢжҲҗеҠҹгҒ—гҒҹгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒҜгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢеҝғиЁјгӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§зҸҫжҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӘгҒ®гҒ§гҒқгӮҢиҮӘдҪ“гҒҜеҲҘгҒ«иүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғ—гғ¬гӮјгғізөӮдәҶеҫҢгҒ«гғ—гғ¬гӮјгғігҒ®дҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гҖҒгҒқгҒ“гҒ§иӘһгӮүгӮҢгӮӢгҒ№гҒҚеҶ…е®№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҸҢж–№гҒ®д»ЈзҗҶдәәй–“гҒ§йҪҹйҪ¬гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
иў«е‘ҠеҒҙгҒҜдәүзӮ№ж•ҙзҗҶиЎЁгҒ«жҜӣгҒ®з”ҹгҒҲгҒҹзЁӢеәҰгҒ®гҖҒгӮӮгҒЈгҒЁгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгӮӮгҒ®гӮ’гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒЎгӮүгҒҜйҖҶгҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иЁҙиЁҹгҒ§еҸҢж–№гҒӢгӮүжҸҗеҮәгҒ•гӮҢгҒҹдё»ејөжӣёйқўгӮ„иЁјжӢ гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгӮ’дёҒеҜ§гҒ«жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®дё»ејөгҒ®жӯЈгҒ—гҒ•гӮ’зӨәгҒҷжүӢз¶ҡгҒЁгҒ„гҒҶжҚүгҒҲж–№гҒ§гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒӢгҒӘгӮҠйҒ•гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ§гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҸҢж–№гҒ®жҚүгҒҲж–№гҒ®дёӯй–“гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘиЁҖгҒ„ж–№гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгғ—гғ¬гӮјгғігҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгҒҜдёүиҖ…й–“гҒ§е…ұжңүгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгӮӮгҒӮгӮҢгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгғ—гғ¬гӮјгғігӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢд»ҘдёҠгҖҒгҒқгҒ®йҒ©еҗҰгҖҒе®ҹж–ҪгҒ®йҡӣгҒ®жүӢжі•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒжӮЈиҖ…еҒҙд»ЈзҗҶдәәејҒиӯ·еЈ«гҒ®й–“гҒ§гӮӮгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹиӯ°и«–гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢгҒЁеҲ‘дәӢдәӢ件гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжӨңеҜҹе®ҳгҒ®и«–е‘ҠжұӮеҲ‘гҖҒејҒиӯ·дәәгҒ®ејҒи«–гҒҜгҖҒж—©гҒ„и©ұгғ—гғ¬гӮјгғігҒ§гҒҷгҒ—гҖҒж°‘дәӢгҖҒиЎҢж”ҝиЁҙиЁҹгҒӘгҒ©гҒ§гӮӮејҒи«–гӮ’еҸЈй ӯгҒ§иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮӮеҸЈй ӯгҒ§дјқгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гғқгӮӨгғігғҲгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҠгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒж—©гҒ„и©ұгғ—гғ¬гӮјгғігҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒд»ҠеӣһгҒ®жүӢз¶ҡгҒҜжі•е»·гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸејҒи«–жә–еӮҷе®ӨгҒЁгҒ„гҒҶйғЁеұӢгҒ§гӮ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжі•е»·гҒ§е ӮгҖ…гҒЁгғ—гғ¬гӮјгғігӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒиЁҙиЁҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжӯЈж”»жі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҒӮгӮӢгҒ№гҒҚе§ҝгҒӘгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹ次第гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢд»ҘдёҠгҖҒејҒиӯ·еЈ«гӮӮгӮӮгҒЈгҒЁгҖҢгғ—гғ¬гӮјгғіиғҪеҠӣгҖҚгӮ’зЈЁгҒӢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҒгҒқгӮ“гҒӘжҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгӮҠгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒеҲҘ件гҒ®еҢ»зҷӮиЁҙиЁҹгҒ§гӮӮгғ—гғ¬гӮјгғіе®ҹж–ҪгҒ®и©ұгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰжҠҖиЎ“гӮ’зЈЁгҒҚгҒӨгҒӨгҖҒгҒҫгҒҹзөҢйҒҺгҖҒж„ҹжғізӯүгӮ’гҒ”е ұе‘ҠгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһгӮігғӯгғҠзҠ¶жіҒдёӢгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁжүӢз¶ҡ
е…Ҳж—ҘгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§еј•гҒҚеҸ—гҒ‘гҒҹгҒӮгӮӢеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ§гҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з”із«ӢиҮӘдҪ“гҒҜд»Ҡе№ҙгҒ®жҳҘе…ҲгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹдәӢ件гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒгӮігғӯгғҠгҒ«гӮҲгӮӢз·ҠжҖҘдәӢж…Ӣе®ЈиЁҖгҒ®еҪұйҹҝгҒ§гҖҒжүӢз¶ҡгҒҢгӮ№гғҲгғғгғ—гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒз”із«ӢгҒӢгӮүпј•гҒӢжңҲиҝ‘гҒҸгҒҢзөҢйҒҺгҒ—гҒҰгҖҒгӮ„гҒЈгҒЁиЁјжӢ дҝқе…Ёжңҹж—ҘгҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷпјҲйҖҡеёёгҒҜз”ігҒ—з«ӢгҒҰгҒҰпј‘пҪһпј’гғ¶жңҲд»ҘеҶ…гҒ«гҒҜжңҹж—ҘгҒҢе…ҘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠз•°еёёдәӢж…ӢгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгӮігғӯгғҠзҠ¶жіҒдёӢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҒ”е ұе‘ҠгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“гҒ®еәғгҒҢгӮҠгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒжңҖгӮӮйҮҚеӨ§гҒӘеҪұйҹҝгӮ’иў«гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ®дёҖгҒӨгҒҢеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҖӢгҖ…гҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ§е®ҹжғ…гҒ«еҝңгҒҳгҒҹеҜҫеҝңгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжӯЈзӣҙгҖҒжӮЈиҖ…гҒ®е®¶ж—ҸгҒҢиҰӢиҲһгҒ„гҒ«иЁӘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮеӨҡгҒҸгҖҒжҠңгҒҚжү“гҒЎгҒ§е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢд»ҘдёҠгҖҒеҪ“ж—ҘгҖҒиЎҢгҒЈгҒҰгҒҝгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«йҖІгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ®дәҲжё¬гҒҢгҒӨгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒҜдёҖзҷәеӢқиІ гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгҖҒдҫқй јиҖ…гҒёгҒ®зўәиӘҚгҒӘгҒ©гҒ®дёӢиӘҝгҒ№гҒҜгҖҒе№іеёёжҷӮгӮҲгӮҠгҒҜж…ҺйҮҚгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгӮҢгҒ§гӮӮз„ЎдәӢгҒ«иЁјжӢ дҝқе…ЁжүӢз¶ҡгӮ’зөӮгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒдёҚе®үгӮ’жҠұгҒҲгҒӨгҒӨиҮЁгӮҖгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒиЎҢгҒҸеүҚгҒӢгӮүжҷ®ж®өгҒЁгҒҜгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁйҒ•гҒҶз·Ҡејөж„ҹгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®дёҚе®үгҒҜеҮәгҒ гҒ—гҒ§гҒ„гҒҚгҒӘгӮҠзҡ„дёӯгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡе»әзү©гҒ«е…ҘгӮӢжҷӮзӮ№гҒ§гҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒ—гҒҹгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«иҰӢиҲһгӮҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮігғӯгғҠж„ҹжҹ“еҜҫзӯ–гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒҫгҒҡгҖҒз—…йҷўгҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгҒ§жӨңжё©гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒӘгӮ“гҒЁиЈҒеҲӨе®ҳгҒЁгӮ«гғЎгғ©гғһгғігҒ§жқҘгҒҰгҒҸгӮҢгҒҹејҒиӯ·еЈ«гҒ®дҪ“жё©гҒҢгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮпј“пј—еәҰгӮ’и¶…гҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
пј’дәәгҒЁгӮӮгҒ гӮӢгҒ•гҒӘгҒ©гҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠи¶іжӯўгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
зөҗеұҖгҖҒжҷ®йҖҡгҒ®дҪ“жё©иЁҲгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰжӯЈзўәгҒ«жё¬гӮҠгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜпј“пј—еәҰгӮ’дёӢеӣһгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢзўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒз„ЎдәӢжүӢз¶ҡгҒ«гҒҜе…ҘгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮӮгҒ—гҖҒдҪ•еәҰжё¬гҒЈгҒҰгӮӮпј“пј—еәҰд»ҘдёҠгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“пјҲзү№гҒ«иЈҒеҲӨе®ҳгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжүӢз¶ҡгҒ®дё»дҪ“гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒе®Ңе…ЁгҒ«гӮўгӮҰгғҲгҒ гҒЈгҒҹгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶпјүгҖӮ
гҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒгҒ“гҒ®ж—ҘгҒҜз•°еёёгҒ«жҡ‘гҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒй–Ӣе§ӢеүҚгҒ«еӨ–гҒ§еҫ…ж©ҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢй–“гҒ«и»ҪгҒ„и„ұж°ҙгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®и¶іжӯўгӮҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҲқгҒЈз«ҜгҒӢгӮүгӮігғӯгғҠгҒҠгҒқгӮӢгҒ№гҒ—гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҒ®жүӢз¶ҡгҒ§гӮӮгҖҒгӮігғӯгғҠгҒ®еҪұйҹҝгҒҜз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҢе…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒҹйғЁеұӢгҒ«гҒҜзӘ“гӮӮдҪ•гӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒқгҒ“гҒӢгӮүеҮәгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйҷўеҶ…гӮ’移еӢ•гҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒЁжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з¶ҡгҒ„гҒҰгҖҒдҪңжҘӯгҒ®йҖ”дёӯгҒ§гҖҒпјЈпјҙзӯүгҒ®з”»еғҸгҒ®еӯҳеңЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҜеҲҘгҒ®е ҙжүҖгҒ®гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјеҶ…гҒ«дҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒйҖҡеёёгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјгҒ®иЁӯзҪ®гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢйғЁеұӢгҒ«иЎҢгҒҚгҖҒгҒқгҒ®е ҙгҒ§ж“ҚдҪңгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®гғҮгғјгӮҝгҒ®еҮәеҠӣгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢжүӢй ҶгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҲҘе®ӨгҒёгҒ®з§»еӢ•гҒҜйҒҝгҒ‘гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„гҒЁгҒ®иҰҒи«ӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгӮ’дҝЎй јгҒ—гҖҒгҒЁгӮҠгҒӮгҒҲгҒҡгҖҒгғҮгғјгӮҝгӮ’гғҖгғ“гғігӮ°гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§зҙҚеҫ—гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮгӮігғӯгғҠгҒ®еҪұйҹҝгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒд»ҠеӣһгҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒз”»еғҸгғҮгғјгӮҝгҒҜгҒ•гҒ»гҒ©йҮҚиҰҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§жҠҳгӮҠеҗҲгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгӮӮгҒ—з”»еғҸгҒҢжұәгӮҒжүӢгҒ®дәӢ件гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгғјжң¬дҪ“гӮ’зўәиӘҚгҒ•гҒӣгҒҰгӮӮгӮүгҒҶгӮҲгҒҶеј·гҒҸжұӮгӮҒгҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§йҖҡеёёгҒЁгҒҜйҒ•гҒҶдәӢж…ӢгҒ«йҒӯйҒҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ§гҖҒжңҖгӮӮж”ҜйҡңгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒжңҖеҫҢгҒ®е ҙйқўгҒ§гҖҒдәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгҒҹйғЁеұӢгҒ®еҶ…йғЁгҒ®зңӢиҰ–зҠ¶жіҒгӮ’зўәиӘҚгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
еҢ»зҷӮеҒҙгҒӢгӮүгҒҜгҖҒдёҚзү№е®ҡеӨҡж•°гҒҢеҮәе…ҘгӮҠгҒҷгӮӢе ҙжүҖгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒе®ӨеҶ…гҒ«е…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйҒ ж…®гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„гҒЁжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒйғЁеұӢгҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгҒӢгӮүгҒ®ж’®еҪұгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҘҘиЎҢгҒҚгҒ®гҒӮгӮӢйғЁеұӢгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҶ…йғЁгҒ®зҠ¶жіҒгӮ’жӯЈзўәгҒ«зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
дәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгҒҹеҪ“жҷӮгҒЁгҒҜе®ӨеҶ…гҒ®зҠ¶жіҒгӮӮеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиӘ¬жҳҺгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢд»ҘдёҠеӣәеҹ·гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁж®ӢеҝөгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдәӢ件гҒ®гҒ“гҒЁгҒҜеҲҘгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгҒҢеӨ§еӨүгҒӘзҠ¶жіҒгҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒд»ҠеӣһгҒ®жүӢз¶ҡгҒ§гӮӮгҒІгҒ—гҒІгҒ—гҒЁе®ҹж„ҹгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е®ҹгҒҜгҖҒзҸҫеңЁжә–еӮҷдёӯгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁжЎҲ件гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮігғӯгғҠгҒ®еҪұйҹҝгҒҜгҒҫгҒ гҒҫгҒ й•·еј•гҒҚгҒқгҒҶгҒ§гҖҒдәӢжЎҲгҒ®еҶ…е®№гӮ„дҝқе…ЁгҒ®еҜҫиұЎзү©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒдҝқе…ЁжүӢз¶ҡгҒ«йҮҚеӨ§гҒӘж”ҜйҡңгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҖҒжңҖжӮӘгҖҒдҝқе…Ёеҹ·иЎҢгҒҢдёҚиғҪгҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгӮӮйҷҗгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ®гҒ§гҖҒд»ҠгҒ®жҷӮжңҹгҒҜгҖҒз”із«ӢгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮӮеҗ«гӮҒгҖҒж…ҺйҮҚгҒ«жә–еӮҷгҖҒжӨңиЁҺгҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁеј·гҒҸж„ҹгҒҳгҒҹ次第гҒ§гҒҷгҖӮ