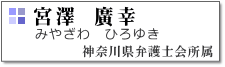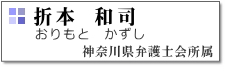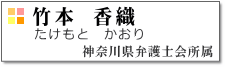еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһдёӯеҝғйқҷи„ҲгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«пјҲпјЈпј¶пјүжҢҝе…ҘгҒ®йҡӣгҒ®иЎҖз®ЎжҗҚеӮ·гҒ«гӮҲгӮӢжӯ»дәЎдәӢж•…гҒ®и§ЈжұәгҒ®гҒ”е ұе‘Ҡпј°пҪҒпҪ’пҪ”пј‘
жң¬д»¶гҒҜгҖҒд»ҘеүҚгҖҒеҪ“гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§гӮӮгҖҒдәӢж•…еҫҢгҒ®йҷўеҶ…иӘҝжҹ»гҒҢжҘөгӮҒгҒҰдёҚеҚҒеҲҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҢ»зҷӮдәӢж•…иӘҝжҹ»еҲ¶еәҰгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҹз—ҮдҫӢгҒ§гҒҷгҖӮ
дәӢж•…гҒ®еҶ…е®№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжҰӮиҰҒгҒ§з”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҒЁгҖҒдёӯеҝғйқҷи„ҲгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«пјҲпјЈпј¶пјүгҒ®жҢҝе…ҘгҒ®жүӢжҠҖгӮ’и©ҰгҒҝгҒҹйҡӣгҒ«гҖҒиӘӨгҒЈгҒҰдё»иҰҒеӢ•и„ҲгӮ’жҗҚеӮ·гҒ—гҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«еҮәиЎҖжҖ§гӮ·гғ§гғғгӮҜгҒ§дәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶйқһеёёгҒ«з—ӣгҒҫгҒ—гҒ„дәӢж•…гҒ§гҒҷгҖӮ
дәӢж•…еҫҢгҒ®йҷўеҶ…иӘҝжҹ»гҒҢжқңж’°гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒз№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжң¬зЁҝгҒ§гҒҜдёӯеҝғзҡ„гҒ«иҝ°гҒ№гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
д»ҘеүҚгҒ®иЁҳдәӢгӮ’гҒҠиӘӯгҒҝгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҗҢдәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҒҶе°‘гҒ—и©ігҒ—гҒҸиҝ°гҒ№гҒҫгҒҷгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒӮгӮӢз·ҸеҗҲз—…йҷўгҒ§гҖҒиӢҘгҒ„еҢ»её«гҒҢйј еҫ„йғЁпјҲи¶ігҒ®д»ҳгҒ‘ж №гҒӮгҒҹгӮҠпјүгҒӢгӮүгҒ®пјЈпј¶гӮ«гғҶгғјгғҶгғ«жҢҝе…ҘгӮ’и©ҰгҒҝгҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҒҶгҒҫгҒҸиЎҢгҒӢгҒҡгҖҒзҙ„пј‘пјҗеӣһгӮӮгҒ®з©ҝеҲәгӮ’иЎҢгҒҶгӮӮжҲҗеҠҹгҒӣгҒҡгҖҒз©ҝеҲәйҮқгӮ’й•·гҒ„йҮқгҒ«еӨүжӣҙгҒ—гҒҰз©ҝеҲәгӮ’зөӮгҒҲгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒиЎ“еҫҢгҒ«гҖҒиЎҖең§гҒ®жҖҘжҝҖгҒӘдҪҺдёӢгӮ„зҡ®дёӢиЎҖзЁ®еҪўжҲҗгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®дәӢж…ӢгҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ«гҖҒеҢ»зҷӮд»Ӣе…ҘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®еҫҢжҖҘеӨүгҒ—гҖҒжӯ»дәЎгҒ«иҮігҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒдәӢж•…зӣҙеҫҢгҒ®иӘ¬жҳҺгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзөҢз·ҜгӮ’зөҢгҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҖҢпјЈпјҜпј¶пј©пјӨпјҚпј‘пјҷгҒ«гӮҲгӮӢж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еў—жӮӘгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҖҚгҒЁгҒ®иӘ¬жҳҺгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зўәгҒӢгҒ«гҖҒе…ҘйҷўгҒ®гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒҜж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®иӘ¬жҳҺгҒ«йҒәж—ҸгҒҢз–‘е•ҸгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒз”»еғҸиЁәж–ӯгҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒйӘЁзӣӨеҶ…гҒ«иЎҖзЁ®ж§ҳгҒ®жүҖиҰӢгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒи§Јеү–гҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰеҸідёӢи…№еЈҒеӢ•и„ҲжҗҚеӮ·гҒ«гӮҲгӮӢеҮәиЎҖжҖ§гӮ·гғ§гғғгӮҜгҒҢжӯ»еӣ гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жң¬д»¶дәӢж•…гҒ§гҒҜгҖҒжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®еҢ»еӯҰзҡ„ж©ҹеәҸгҒҜгҒ»гҒјзўәе®ҡгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғқгӮӨгғігғҲгҒҜгҖҒйј еҫ„йғЁгҒёгҒ®CVжҢҝе…ҘгҒ®йҡӣгҒ«гҖҒжүӢжҠҖгҒ®йҒҺеӨұгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒӢеҗҰгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒЁгҖҒиЎ“еҫҢгҒ®з®ЎзҗҶгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒ®иҗҪгҒЎеәҰгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
йј еҫ„йғЁгҒёгҒ®жҢҝе…ҘгҒ®жүӢжҠҖгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒйј зөҢйқӯеёҜгӮҲгӮҠгӮӮй ӯеҒҙгҒ§гҒ®жҢҝе…ҘгҒҜеӢ•и„ҲжҗҚеӮ·гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§йҒҝгҒ‘гӮӢгҒ№гҒҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҖҒеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®иҰӢи§ЈгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒ“гҒ®зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз—…йҷўеҒҙгҒ®д»ЈзҗҶдәәгҒҜйҒҺеӨұгӮ’жҳҺзўәгҒ«иӘҚгӮҒгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒжң¬д»¶гҒ§пјЈпј¶жҢҝе…ҘгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹеҢ»её«гҒҜз ”дҝ®еҢ»гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиҮЁеәҠзөҢйЁ“гҒҢи¶ігӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«з”ҹгҒҳгҒҹзөҗжһңгҒӢгӮүгҒҝгҒҰгӮӮжҢҝе…ҘйғЁдҪҚгӮ’иӘӨгҒЈгҒҹеҸҜиғҪжҖ§гҒҜй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйј зөҢйқӯеёҜгӮҲгӮҠе°ҫеҒҙгҒ§гҒ®жҢҝе…ҘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжҢҝе…ҘгҒ®и§’еәҰгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜдёӢи…№еЈҒеӢ•и„ҲзӯүгҒ®жҗҚеӮ·гӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒҫгҒ§гҒҜгҒ„гҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒдәӢж•…гҒӢгӮүеӯҰгҒ¶гҒ№гҒҚж•ҷиЁ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒ®дё»ејөз«ӢиЁјиІ¬д»»гҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒпј°пҪҒпҪ’пҪ”пј’гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒиЎҖз®ЎжҗҚеӮ·гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеҚіеҮәиЎҖжҖ§гӮ·гғ§гғғгӮҜгҒ§жӯ»гҒ«иҮігӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒдҪ“еҶ…гӮ’еҫӘз’°гҒҷгӮӢиЎҖж¶ІйҮҸгҒҢжёӣе°‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒҹгӮҒгҖҒи„ҲжӢҚж•°гӮ„е‘јеҗёж•°гҒҢеў—еҠ гҒ—гҖҒжң«жўўгҒёгҒ®иЎҖжөҒдёҚи¶ігҒ§гғҒгӮўгғҺгғјгӮјгҒ«гҒӘгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®гҒ„гӮҸгӮҶгӮӢд»Је„ҹжҖ§гӮ·гғ§гғғгӮҜгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒӢгӮүйқһд»Је„ҹжҖ§гӮ·гғ§гғғгӮҜгҒёгҒЁз§»иЎҢгҒ—гҒҰиЎҢгҒҚгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгҒқгҒ®й–“гҒ«гҒҜдёҖе®ҡгҒ®жҷӮй–“гӮ’зөҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒд»Је„ҹжңҹгҒ«еҢ»зҷӮд»Ӣе…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒеҚҒеҲҶгҒ«ж•‘е‘ҪгҒҜеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжң¬д»¶дәӢж•…гҒ§гӮӮгҖҒпјЈпј¶жҢҝе…ҘеҫҢгҒ®з•°еӨүгҒ«ж°—д»ҳгҒ„гҒҰгҒҷгҒҗгҒ«д»Ӣе…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°ж•‘е‘ҪгҒ§гҒҚгҒҹеҸҜиғҪжҖ§гҒҜй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәҢж®өж§ӢгҒҲгҒ®жҢҮж‘ҳгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜз—…йҷўеҒҙгӮӮиІ¬д»»гӮ’иӘҚгӮҒгҖҒжӯ»дәЎгҒ®иІ¬д»»гӮ’иӘҚгӮҒгҒҹгҒЁи©•дҫЎгҒ§гҒҚгӮӢгғ¬гғҷгғ«гҒ®зӨәи«Үи§ЈжұәгӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒзӨәи«ҮгҒ«гҒӮгӮҸгҒӣгҒҰз—…йҷўеҒҙгҒӢгӮүгҒҜгҖҒи¬қзҪӘгҒЁеҶҚзҷәйҳІжӯўгӮ’зҙ„жқҹгҒҷгӮӢеҶ…е®№гҒ®жӣёйқўгӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дҪ•еәҰгӮӮжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж°‘дәӢдәӢ件гҒ§иІ¬д»»гӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгҒ®ж—©жңҹи§ЈжұәгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮжұәгҒ—гҒҰеӨ§гҒҚгҒӘиІ жӢ…гҒЁгҒӘгӮүгҒҡгҖҒгғҹгӮ№гӮ’зҠҜгҒ—гҒҹеҢ»её«гҒ®ж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒж—©жңҹгҒ«гҖҒгғҹгӮ№гӮ’ж•ҷиЁ“гҒ«гҒ—гҒҰеүҚеҗ‘гҒҚгҒ«еҢ»зҷӮгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮҒгӮӢж©ҹдјҡгҒҢиЁӘгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ§гӮӮгҖҒгҒ„гҒҹгҒҡгӮүгҒ«ж§ӢгҒҲгҒҰгҖҒй»’гӮ’зҷҪгҒЁиЁҖгҒ„繕гҒҶгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж°‘дәӢдәӢ件гҒ§ж—©жңҹи§ЈжұәгӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒ®ж„Ҹе‘ігӮ’еүҚеҗ‘гҒҚгҒ«гҒЁгӮүгҒҲгҒ№гҒҸзҷәжғігӮ’еӨүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒҶ次第гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒжң¬д»¶гҒ§ж•ҷиЁ“гҒ«гҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҜгҒ»гҒӢгҒ«гӮӮгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒй•·гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒпј°пҪҒпҪ’пҪ”пј’гҒ«з¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһдҫқй јиҖ…гҒЁеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®гҒ“гҒЁ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҢеҢ»зҷӮдәӢ件гӮ’жүұгҒЈгҒҰиЎҢгҒҸгҒҶгҒҲгҒ§еҚ”еҠӣеҢ»гҒ®еӯҳеңЁгҒҜдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжңҖиҝ‘еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеҚ”еҠӣеҢ»гҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ§гҒЁгҒҰгӮӮе¬үгҒ—гҒҸжҖқгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒ”е ұе‘ҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
йҖҡеёёгҖҒеҚ”еҠӣеҢ»гҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒдәӢжЎҲгҒ®иіҮж–ҷгӮ’дёҖз·’гҒ«жӨңиЁјгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒӘгҒ©гҒ—гҒҰгҖҒдәӢж•…гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж©ҹеәҸгҒ§иө·гҒҚгҒҹгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҖҒеҪ“и©ІеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжіЁж„Ҹзҫ©еӢҷйҒ•еҸҚгҒ®жңүз„ЎгҖҒзөҗжһңеӣһйҒҝеҸҜиғҪжҖ§зӯүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгғҮгӮЈгӮ№гӮ«гғғгӮ·гғ§гғігҒ®жҷӮй–“гӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҖҒеҠ©иЁҖгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒдәӢ件гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҰгҖҒдҫқй јиҖ…гӮ’зӣҙжҺҘиЁәеҜҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгҒ”жң¬дәәгҒҢиЁҙгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮзҠ¶гҒ®еҺҹеӣ гӮ„гҒқгҒ“гҒ«иҮігӮӢж©ҹеәҸгӮ’жӯЈзўәгҒ«жҠҠжҸЎгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒйҒҺеӨұгӮ„еӣ жһңй–ўдҝӮгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гӮӮгҖҒеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒ«жӮЈиҖ…гӮ’иЁәгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒ“гҒЁгҒҜйқһеёёгҒ«жңүз”ЁгҒӘе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒдәӨйҖҡдәӢж•…гҒӘгҒ©гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒз—…зҠ¶гҒҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢж”№е–„гҒӣгҒҡгҖҒдҫқй јиҖ…гҒ®еҒҙгҒӢгӮүеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®зҙ№д»ӢгӮ’й јгҒҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзөҢз·ҜгҒ§гҖҒдәӢжЎҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒдҫқй јиҖ…гҒ«еҚ”еҠӣеҢ»гҒҢгҒҠгӮүгӮҢгӮӢз—…йҷўгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰиЁәеҜҹгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢжҷӮжҠҳгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢиүҜгҒ„зөҗжһңгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢз«ӢгҒҰз¶ҡгҒ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёҖ件гҒҜгҖҒжүӢиЎ“гғҹгӮ№гҒ§еӢ•и„ҲгӮ’жҗҚеӮ·гҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«иЎ“еҫҢгҒ®еҜҫеҝңгҒ®йҒ…гӮҢгӮӮйҮҚгҒӘгҒЈгҒҰзӯӢиӮүгӮ„зҘһзөҢгҒҢеәғзҜ„еӣІгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰеЈҠжӯ»гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢж•…гҒ§гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®еӣһеҫ©гҒҢжҚ—гҖ…гҒ—гҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒд»ҠеҫҢгҒ®еҢ»зҷӮж–№йҮқгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиҰҒжңӣгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдҝЎй јгҒ§гҒҚгӮӢеӨ–科еҢ»гӮ’гҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгҒҢйқһеёёгҒ«жәҖи¶ігҒ®гҒ„гҒҸгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒжңҖй«ҳгҒ®еҢ»её«гҒ«еҮәдјҡгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжІ»зҷӮгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹеӨ–科еҢ»гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎејҒиӯ·еЈ«гҒ«гӮӮгҒҠзӨјгӮ’иҝ°гҒ№гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖ件гҒҜгҖҒгҒӮгӮӢеҢ»зҷӮгғҹгӮ№гҒ®гҒӣгҒ„гҒ§йҰ–гҒӢгӮүиӮ©гҖҒиғҢдёӯгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜи…•гҒ«гӮӮеј·гҒ„з—ӣгҒҝгӮ„з—әгӮҢгҒҢеҮәгҒҰгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮӮгҒҫгҒҫгҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒқгҒ“гҒ«иҮігҒЈгҒҹж©ҹеәҸгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢдёӯгҒ§гҖҒгғҡгӮӨгғігӮҜгғӘгғӢгғғгӮҜгҒ®еҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гӮ’гҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеҲқеӣһгҒ®иЁәзҷӮгҒ®йҡӣгҒ®еҮҰзҪ®гҒ§з—ҮзҠ¶гҒҢгҒӢгҒӘгӮҠжҘҪгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒд»ҘеҫҢгӮӮйҖҡйҷўгӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгӮүеҫҢйҒәз—ҮгҒҢж®ӢгӮүгҒҡгҖҒжІ»зҷ’гҒҢиҰӢиҫјгӮҒгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒҫгҒ§жқҘгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
зҸҫеңЁгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҒқгҒ®ж–№гҒ®з—ҮзҠ¶гҒҜгҒҫгҒ е®ҢжІ»гҒҫгҒ§гҒҜиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиӢҰз—ӣгҒҜгҒӢгҒӘгӮҠи»ҪжёӣгҒ—гҒҰгҒҚгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ§гӮӮгҖҒдҫқй јиҖ…гҒ®ж–№гҒӢгӮүгҒҜгҖҒзҙ№д»ӢгҒ—гҒҹеҢ»её«гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎејҒиӯ·еЈ«гҒҫгҒ§гҒҠзӨјгӮ’иЁҖгӮҸгӮҢгҖҒгҒӘгӮ“гҒ гҒӢйқўжҳ гӮҶгҒ„ж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дҫқй јиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒёгҒ®дҫқй јгҒ®зӣ®зҡ„гҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§дәӢ件гҒ®и§ЈжұәгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҒЁгҒ®еҮәдјҡгҒ„гҒҢдҫқй јиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰж•‘гҒ„гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒӮгӮӢж„Ҹе‘ігҖҒејҒиӯ·еЈ«еҶҘеҲ©гҒ«е°ҪгҒҚгӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһжҺҘйӘЁйҷўгҒЁдҝқйҷә
еҢ»зҷӮдәӢ件гӮ’еӨҡгҒҸжүұгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҒЁгҖҒй–ўйҖЈй ҳеҹҹгҒ§гҒ®дәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮзӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮҠгҖҒдәӢ件еҸ—д»»гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒиҖҒдәәгғӣгғјгғ гҒӘгҒ©гҒ®зҰҸзҘүж–ҪиЁӯгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢд»Ӣиӯ·дәӢж•…гӮ„жҺҘйӘЁйҷўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж–ҪиЎ“дәӢж•…гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдәӢ件гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҖҒзңҹзӣёгҒ®и§ЈжҳҺгҖҒиІ¬д»»гҒ®иҝҪеҸҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜеҢ»еӯҰзҡ„гҒӘи©•дҫЎгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘй ҳеҹҹгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒЁе…ұйҖҡгҒҷгӮӢзӮ№гҒҢеӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҒҶгҒЎгҖҒжҺҘйӘЁйҷўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж–ҪиЎ“дәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒдәӢж•…гҒ®еҶ…е®№иҮӘдҪ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒж„ҸеӨ–гҒЁйҮҚиҰҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒиҰӢйҒҺгҒ”гҒӣгҒӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒҢжҗҚе®ідҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§зөҢйЁ“гҒ—гҒҹдёӯгҒ§гҒҜдёҖеәҰгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
йЎ§е•ҸејҒиӯ·еЈ«гҒҢгҒ„гҒӘгҒ„жҜ”ијғзҡ„е°ҸиҰҸжЁЎгҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒдәӨжёүж®өйҡҺгҒӢгӮүејҒиӯ·еЈ«гҒҢеҮәгҒҰжқҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҖҡеёёгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒ«гҒҜдҝқйҷәдјҡзӨҫеҒҙгҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒ гҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»её«дјҡгӮ„дҝқйҷәдјҡзӨҫгҒӢгӮүгҒ®зҙ№д»ӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮжҗҚе®ідҝқйҷәгҒ§еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ®и§ЈжұәгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒдҝқйҷәйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶдҝқйҷәдјҡзӨҫгҒ®дәҶи§ЈгӮ’еҫ—гҒӘгҒҢгӮүйҖІгӮҒгҒҰиЎҢгҒҸж„ҹгҒҳгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒжҺҘйӘЁйҷўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж–ҪиЎ“дәӢж•…гҒ®е ҙеҗҲгҖҒжҺҘйӘЁйҷўиҮӘдҪ“гҒҜеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨдҝқйҷәгҒ§еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒд»ҘеүҚгҒ«жүұгҒЈгҒҹдәӢ件гҒ§зөҢйЁ“гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ«йЎһгҒҷгӮӢжҗҚе®ідҝқйҷәгҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӮгӮӢжҺҘйӘЁйҷўгҒ®дәӢж•…гҒ§гҖҒгҒқгҒ®жҺҘйӘЁйҷўгҒҜиӯҰеӮҷдҝқйҡңзі»гҒ®дјҡзӨҫгҒ®жҗҚе®ідҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨдҝқйҷәгҒ®е ҙеҗҲгҒЁеҗҢгғ¬гғҷгғ«гҒ®иі е„ҹгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒ—гҖҒеҜҫеҝңгӮӮйқһеёёгҒ«гӮ№гғ гғјгӮәгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒжңҖиҝ‘з«ӢгҒҰз¶ҡгҒ‘гҒ«зӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹиӨҮж•°гҒ®жҺҘйӘЁйҷўгҒ§гҒ®ж–ҪиЎ“дәӢж•…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®дәӢж•…гҒ§гӮӮжҺҘйӘЁйҷўгҒҜжҗҚе®ідҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
дҝқйҷәгҒ§гӮ«гғҗгғјгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеҪұйҹҝгҒ—гҒҰгҒӢгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®дәӢж•…гҒ§гӮӮгҖҒжҺҘйӘЁйҷўеҒҙгҒҢиў«е®іиҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰйқһеёёгҒ«гӮ·гғ“гӮўгҒӘеҜҫеҝңгӮ’гҒ—гҒҰгҒҚгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒиў«е®іиҖ…гҒ®ж–№гҒҢеӣ°гҒЈгҒҰзӣёи«ҮгҒ«жқҘгӮүгӮҢгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
еҖӢгҖ…гҒ®дәӢ件гҒ®и§ЈжұәгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜгҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгҖҒжҗҚе®ідҝқйҷәеҠ е…ҘгҒ®иҰҒеҗҰгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒжҺҘйӘЁйҷўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж–ҪиЎ“гҒҜгӮ«гӮӨгғӯгғ—гғ©гӮҜгғҶгӮЈгғғгӮҜгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪ“гҒ«зү©зҗҶзҡ„иІ иҚ·гӮ’гҒӢгҒ‘гӮӢйЎһгҒ®ж–ҪиЎ“гҒ§гҒҜйҮҚзҜӨгҒӘеҫҢйҒәз—ҮгҒҢж®ӢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒж•ҙеҪўеӨ–科еҢ»гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ§гӮ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘжӨңжҹ»гҒҢгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҲ¶зҙ„гӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒеҜҫеҝңгҒ®йҒ…гӮҢгҒ§йҮҚеӨ§дәӢж•…гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠеҫ—гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒжҗҚе®ідҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгӮҸгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®еҒҙгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒе®үеҝғгҒ—гҒҰж–ҪиЎ“гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«жҺҘйӘЁйҷўгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢеҒҙгҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒеҪ“и©ІжҺҘйӘЁйҷўгҒҢжҗҚе®ідҝқйҷәгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгҒҜдёҖиҰӢгҒ—гҒҰжҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ®гҒ§гҖҒдәӢж•…гҒ«йҒӯгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҖҒгҖҢе®ҹгҒҜдҝқйҷәгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҠйҮ‘гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖҚгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҰгҒӮгӮҠеҫ—гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒд»Ҡзӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢдәӢжЎҲгҒҜгҒқгӮ“гҒӘеұ•й–ӢгҒ гҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
иҮӘи»ўи»ҠдәӢж•…гҒ§ж•°еҚғдёҮеҶҶгҒ®й«ҳйЎҚиі е„ҹгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹдҫӢгӮӮгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒиҮӘи»ўи»ҠгӮ’д№—гӮӢдәәгҒ§гҒҷгӮүгҖҒгҒ„гҒ–гҒЁгҒ„гҒҶе ҙеҗҲгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰжҗҚе®ідҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ«гҒӘгӮҠгҒӨгҒӨгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒи»ҠгҒ®д»»ж„ҸдҝқйҷәгҒҜгҖҒгҖҢд»»ж„ҸгҖҚгҒЁгҒ„гҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҖҒдёҮдёҖдәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгҒҹе ҙеҗҲгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢзҫ©еӢҷгҖҚгҒ гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжҺҘйӘЁйҷўгҒ®ж–ҪиЎ“гҒ§гӮӮжҷӮгҒ«йҮҚеӨ§гҒӘжҗҚе®ігҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮӢд»ҘдёҠгҖҒжҗҚе®ідҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒжҺҘйӘЁйҷўгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒгҒӢгҒӢгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжҺҘйӘЁйҷўгҒҢжҗҚе®ідҝқйҷәгҒ«еҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгӮ’дәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢжҖқгҒЈгҒҹ次第гҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®йҷўеҶ…иӘҝжҹ»е ұе‘ҠжӣёгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҖҒжӯ»дәЎдәӢж•…гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒе№іжҲҗпј’пј—е№ҙгҒ«е§ӢгҒҫгҒЈгҒҹеҢ»зҷӮдәӢж•…иӘҝжҹ»ж”ҜжҸҙгӮ»гғігӮҝгғјпјҲеҢ»зҷӮдәӢж•…иӘҝпјүгҒ«гӮҲгӮӢиӘҝжҹ»гҒ®жүӢз¶ҡгҒҢеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒйӣЈзӮ№гҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжүӢй ҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠеҢ»зҷӮдәӢж•…иӘҝгҒ«гӮҲгӮӢиӘҝжҹ»гҒЁгҒӘгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒҫгҒҡгҒҜдәӢж•…гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹеҢ»зҷӮж©ҹй–ўеҶ…гҒ§гҒ®иӘҝжҹ»пјҲйҷўеҶ…иӘҝжҹ»пјүгҒҢе…ҲиЎҢгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒҢж–°гҒҹгҒ«з«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮӢжҷӮгҖҒжӯ»дәЎдәӢж•…гҒ«йҷҗе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ•гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҢгӮүгҖҒиӘҝжҹ»гҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒҷгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгҒҜеҢ»зҷӮж©ҹй–ўеҒҙгҒ®еҲӨж–ӯгҒ«е§”гҒӯгӮүгӮҢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«е…ҲиЎҢгҒ•гӮҢгӮӢйҷўеҶ…иӘҝжҹ»гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒжһңгҒҹгҒ—гҒҰиӘҝжҹ»гҒ®е…¬жӯЈжҖ§гҒҢжӢ…дҝқгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒӮгҒҹгӮҠгӮӮиӯ°и«–гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷпјҲд»–гҒ«гӮӮе•ҸйЎҢзӮ№гҒҜгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјүгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒйҒҺеҺ»гҒ«еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§зөҢйЁ“гҒ—гҒҹз—ҮдҫӢгҒ§гӮӮгҖҒйҷўеҶ…иӘҝжҹ»гҒҢгҒӢгҒӘгӮҠжҒЈж„Ҹзҡ„гҒ§дёҚе…¬жӯЈгҒӘеҶ…е®№гҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒҫгҒҹжңҖиҝ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§зӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹз—ҮдҫӢгҒ§гҖҒд»ҘеүҚжүұгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁйқһеёёгҒ«гӮҲгҒҸдјјгҒҹеҶ…е®№гҒ®йҷўеҶ…иӘҝжҹ»е ұе‘ҠжӣёгӮ’иӘӯгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒж–°гҒҹгҒӘз–‘е•ҸгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒӮгӮүгҒҹгӮҒгҒҰгҖҒйҷўеҶ…иӘҝжҹ»е ұе‘ҠгҒ®е•ҸйЎҢжҖ§гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҝ°гҒ№гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®з—ҮдҫӢгҒҜгҖҒгӮігғӯгғҠж„ҹжҹ“гҒ§е…ҘйҷўгҒ—гҒҹй«ҳйҪўгҒ®еҘіжҖ§гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒдёӯеҝғйқҷи„ҲгӮ«гғҶгғјгғҶгғ«пјҲпјЈпј¶пјүжҢҝе…ҘгӮ’и©ҰгҒҝгҒҹйҡӣгҒ«гҖҒиӘӨгҒЈгҒҰдё»иҰҒеӢ•и„ҲгӮ’жҗҚеӮ·гҒ—гҖҒеҜҫеҮҰгҒҢйҒ…гӮҢгҒҰдәЎгҒҸгҒӘгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒз—…йҷўеҒҙгҒҜгҖҒеҪ“еҲқгҖҒжӯ»еӣ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢгӮігғӯгғҠж„ҹжҹ“гҒ«гӮҲгӮӢж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еў—жӮӘгҖҚгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁиӘ¬жҳҺгҒ—гҖҒжӯ»дәЎиЁәж–ӯжӣёгҒ«гӮӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷпјҲе…ёеһӢзҡ„гҒӘеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒӘгҒ®гҒ«гҖҒйғҪеҗҲгӮҲгҒҸгӮігғӯгғҠй–ўйҖЈжӯ»гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮӮй©ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒйҖҶгҒ«гҖҒгӮігғӯгғҠй–ўйҖЈжӯ»гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢдёӯгҒ«гҒҜгҖҒеҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒҢзөҗж§ӢзҙӣгӮҢиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ®з–‘еҝөгҒ•гҒҲ湧гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢпјүгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйҒәж—ҸгҒ®еёҢжңӣгҒ«гӮҲгӮӢз”»еғҸиЁәж–ӯгӮ’зөҢгҒҰгҖҒи§Јеү–гҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҖҒгҖҢеҮәиЎҖжҖ§гӮ·гғ§гғғгӮҜгҖҚгҒ«гӮҲгӮӢжӯ»дәЎгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒйҷўеҶ…иӘҝжҹ»гҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ”йҒәж—ҸгҒҜгҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгӮ’иЁҳгҒ—гҒҹйҷўеҶ…е ұе‘ҠжӣёгӮ’жүӢгҒ«гҒ—гҒҰеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«жқҘгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҶ…е®№гӮ’дёҖиӘӯгҒ—гҒҰгҖҒеҘҮеҰҷгҒӘж—ўиҰ–ж„ҹпјҲгғҮгӮёгғЈгғ–пјүгӮ’иҰҡгҒҲгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
зӣ®гҒ«гҒ—гҒҹгҒқгҒ®е ұе‘ҠжӣёгҒҜгҖҒеҪўејҸзҡ„гҒ«гӮӮгҖҒгҒҫгҒҹи«–ж—ЁгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒд»ҘеүҚеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҹеҲҘ件гҒ®йҷўеҶ…иӘҝжҹ»е ұе‘ҠжӣёгҒЁй…·дјјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дҪ•гӮҲгӮҠгӮӮй©ҡгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒз—…йҷўеҒҙгҒҢжӨңиЁҺдәӢй …гӮ’иҮӘгӮүиЁӯе®ҡгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҝңгҒҳгҒҹиЁҳиҝ°гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жӨңиЁҺдәӢй …гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҖҒгҖҢиӘ¬жҳҺгҒ®еҰҘеҪ“жҖ§гҖҚгҒЁгҒӢгҖҢпјЈпј¶жҢҝе…ҘгҒ®еҰҘеҪ“жҖ§гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиЁҳијүгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гҖҒиӮқеҝғгҒӢгҒӘгӮҒгҒ®гҖҢдәӢж•…гҒҢгҒӘгҒңиө·гҒҚгҒҹгҒ®гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҰізӮ№гҒӢгӮүгҒ®жӨңиЁјгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹиЁӯе•ҸгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеҮәиЎҖжҖ§гӮ·гғ§гғғгӮҜгҒ§дәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒ®иЁҳијүгҒҜгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгҒӘгҒңдё»иҰҒиЎҖз®ЎгӮ’жҗҚеӮ·гҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘжӨңиЁјгҒ®иЁҳиҝ°гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒиЎҖз®ЎжҗҚеӮ·гҒҢеҚіжӯ»дәЎгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгӮүгҖҒиЎҖз®ЎжҗҚеӮ·еҫҢгҒ®зөҢйҒҺгӮ’иҝҪгҒЈгҒҰжӮЈиҖ…гӮ’ж•‘е‘ҪгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹиҰҒеӣ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®жӨңиЁјгҒ®иЁҳиҝ°гӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ§гҒҜдёҖдҪ“дҪ•гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®иӘҝжҹ»гҒӘгҒ®гҒӢгҖҒж„Ҹе‘ідёҚжҳҺгҒЁгҒ„гҒҶгҒ»гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢдәҢйҮҚгҒ«й©ҡгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹжӨңиЁҺдәӢй …гҒ®еҶ…е®№гҒҢгҖҒеүҚгҒ«зӣ®гҒ«гҒ—гҒҹе ұе‘ҠжӣёгҒЁз“ңдәҢгҒӨгҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
еүҚгҒ«зӣ®гҒ«гҒ—гҒҹе ұе‘ҠжӣёгҒ§гӮӮгҖҒиӘ¬жҳҺгҒ®еҰҘеҪ“жҖ§гӮ’иӨҮж•°еӣһе•ҸгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘеҶ…е®№гҒ§гҒ—гҒҹгҒ—гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгҖҢдәӢж•…гҒҢгҒӘгҒңиө·гҒҚгҒҹгҒ®гҒӢгҖҚгҖҢгҒӘгҒңжӯ»дәЎгҒЁгҒ„гҒҶзөҗжһңгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹгҒ®гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҰізӮ№гҒӢгӮүгҒ®иЁӯе•ҸгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиЁӯе•ҸгҒҢгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЁӯе®ҡгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе…·дҪ“зҡ„гҒӘиЁҳиҝ°гӮӮгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠдәӢж•…гҒ®зңҹзӣёгҒӢгӮүгҒҜгҒ»гҒ©йҒ гҒ„еҶ…е®№гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§дјјйҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜеҒ¶з„¶гҒ®дёҖиҮҙгҒЁгҒҜиҖғгҒҲгҒ«гҒҸгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁж„ҹгҒҳгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢж•…иӘҝжҹ»еҲ¶еәҰгҒҢз«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮӢжҷӮгҒ«гҖҒеӨ§гҒҚгҒӘиӯ°и«–гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…иӘҝжҹ»гҒҢеҢ»зҷӮеҒҙгҒ®иІ¬д»»иҝҪеҸҠгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒ„гҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гҖҒгҒ“гҒ®йҷўеҶ…иӘҝжҹ»е ұе‘ҠжӣёгҒ®жӣ–жҳ§гҒ•гҒҜгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒ®иІ¬д»»иҝҪеҸҠгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘиЁҳијүгӮ’жҘөеҠӣйҒҝгҒ‘гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®дёӯгҒ«гҒҜгҖҒй–“йҒ•гҒ„гҒӘгҒҸгҖҒдёҚйҒ©еҲҮгҒӘеҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиө·гҒҚгҒҹгҖҒгҒқгӮҢгҒ•гҒҲгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°жӯ»дәЎгҒЁгҒ„гҒҶзөҗжһңгӮ’йҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҒҜгҒҡгҒ®з—ҮдҫӢгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒдәӢж•…гӮ’ж•ҷиЁ“гҒ«гҒ—гҖҒеҶҚзҷәйҳІжӯўгҒ«гҒӨгҒӘгҒ’гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҲ¶еәҰгҒ®зӣ®зҡ„гҒӢгӮүгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе ҙеҗҲгҒ«еҢ»зҷӮиЎҢзӮәгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гӮ’жҢҮж‘ҳгҒ—гҒӘгҒ„е ұе‘ҠжӣёгҒҜжңүе®із„ЎзӣҠгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
иӘҝжҹ»е ұе‘ҠжӣёгҒҢгҒқгҒ®зӮ№гӮ’жҳҺзўәгҒ«жҢҮж‘ҳгҒҷгӮӢеҶ…е®№гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҗҢзЁ®дәӢж•…гӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜеҝ…иҰҒдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгҒҢгҖҒжҷӮгҒ«иІ¬д»»иҝҪеҸҠгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгӮ„гӮҖгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҒ—гҖҒйҖҶгҒ«гҒқгӮҢгҒҢжҳҺзўәгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ“гҒқгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдҝЎй јгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҢзӣ®гҒ«гҒ—гҒҹпј’гҒӨгҒ®е ұе‘ҠжӣёгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢеҒ¶з„¶гҒ®дёҖиҮҙгҒЁгҒҜиҖғгҒҲгҒ«гҒҸгҒ„гҒ»гҒ©йЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…иӘҝгҒҢгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҢҮе°ҺгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеҢ»зҷӮж©ҹй–ўеҗҢеЈ«гҒҢжғ…е ұдәӨжҸӣгӮ’гҒ—гҒҰгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзөҗжһңгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҒҜгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒгҒ“гҒ®дәҢгҒӨгҒ®еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸз„Ўй–ўдҝӮгҒ§гҖҒи·қйӣўзҡ„гҒ«гӮӮпј‘пјҗпјҗпјҗгӮӯгғӯгҒҜйӣўгӮҢгҒҹеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒ©гҒ“гҒӢгҒ«йҷўеҶ…иӘҝжҹ»еҜҫзӯ–гғһгғӢгғҘгӮўгғ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҹгӮҠгӮӮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…иӘҝжҹ»еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒ®йҒӢз”Ёжңҹй–“гӮ’зөҢгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҪ“еҲқгҒӢгӮүжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҹе•ҸйЎҢзӮ№гҒ®жӨңиЁјгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒгҒқгӮҚгҒқгӮҚиҰӢзӣҙгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚжҷӮжңҹгҒ«жқҘгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒ®дёӢгҒ§гҖҒгҒҷгҒ§гҒ«еҢ»зҷӮй ҳеҹҹгҒ”гҒЁгҒ«з—ҮдҫӢеҲҶжһҗгҒӘгҒ©гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒқгӮҢгҒ§йқһеёёгҒ«жңүж„Ҹзҫ©гҒ гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢпјҲе®ҹйҡӣгҖҒпјЈпј¶жҢҝе…ҘгҒ®дәӢж•…гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲҶжһҗгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮӮиӘӯгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒйқһеёёгҒ«еӢүеј·гҒ«гҒӘгӮӢеҶ…е®№гҒ§гҒ—гҒҹпјүгҖҒдёҚеӮҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜж”№е–„гҒ—гҒҰгҖҒгӮҲгӮҠе®ҹеҠ№жҖ§гҒ®гҒӮгӮӢеҲ¶еәҰгҒ«гғ–гғ©гғғгӮ·гғҘгӮўгғғгғ—гҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҒ№гҒҚгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһиӮқз”ҹжӨңеҫҢгҒ«з”ҹеҫҢпј‘пј‘гҒӢжңҲгҒ®д№іе…җгҒҢеҮәиЎҖжӯ»гҒ—гҒҹеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒҢзөӮдәҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҒ”е ұе‘Ҡгғ»еәҸ
е№іжҲҗпј’пјҷе№ҙгҒ«жЁӘжөңең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҒ«жҸҗиЁҙгҒ—гҒҹгҖҒд№іе…җгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиӮқз”ҹжӨңе®ҹж–ҪеҫҢгҒ®жӯ»дәЎдәӢж•…гҒ®еҢ»зҷӮиЁҙиЁҹгҒҢгҖҒжң¬е№ҙпј“жңҲпј‘пјҳж—ҘгҒ«е’Ңи§ЈгҒ«гӮҲгӮҠи§ЈжұәгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒеҲқгӮҒгҒ«з”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®и§ЈжұәгҒҜгҖҒгҒ”йҒәж—ҸгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиЈҒеҲӨгҒ®еҺҹе‘ҠгҒЁгҒӘгӮүгӮҢгҒҹгҒ”дёЎиҰӘгҒ®гҖҒзңҹзӣёи§ЈжҳҺгӮ’жұӮгӮҒгӮӢи«ҰгӮҒгҒӘгҒ„еј·гҒ„ж°—жҢҒгҒЎгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°жҲҗгҒ—йҒӮгҒ’гӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹиҺүеҘҲгҒЎгӮғгӮ“гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«й ‘ејөгӮүгӮҢгҒҹгҒ”дёЎиҰӘгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеҝғгҒӢгӮү敬ж„ҸгӮ’иЎЁгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜжң¬еҪ“гҒ«еӨҡгҒҸгҒ®ж–№гҖ…гҒ«гҒ”еҚ”еҠӣгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒеӢҮж°—гҒӮгӮӢе‘ҠзҷәгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹиў«е‘Ҡз—…йҷўгҒ®дәӢж•…еҪ“жҷӮгҒ®еҢ»зҷӮиҖ…гӮ„гҖҒзңҹзӣёи§ЈжҳҺгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«зІҳгӮҠеј·гҒҸжҚңжҹ»гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹиӯҰеҜҹй–ўдҝӮиҖ…гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®е°Ӯй–Җзҡ„гҒӘзҹҘиҰӢгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҰй‘‘е®ҡж„ҸиҰӢжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹеҚ”еҠӣеҢ»гҒ®ж–№гҖ…гҒ®гҒ”еҚ”еҠӣгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒ®зңҹзӣёи§ЈжҳҺгҒ«гҒҜиҮігӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ«йҒ•гҒ„гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жң¬еҪ“гҒ«еҝғгҒӢгӮүж„ҹи¬қз”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®дәӢ件гҒҢе’Ңи§ЈгҒ«гӮҲгӮҠи§ЈжұәгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒҷгҒ§гҒ«пј’гғ¶жңҲд»ҘдёҠгҒҢзөҢйҒҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮгҒ®гҒ“гҒЁгҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒгҒ“гҒ®дәӢж•…гҒӢгӮүеӯҰгҒ¶гҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«еӨҡеІҗгҒ«еҸҠгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ©гҒ“гҒӢгҒ§гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰе…¬иЎЁгҒ—гҒҰиЎҢгҒӢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдҪҝе‘Ҫж„ҹгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҫгҒ еҚҒеҲҶгҒӘжә–еӮҷгҒҢеҮәжқҘгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгӮҢгҒЁгҖҒжң¬д»¶гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠдҪ•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒҠдё–и©ұгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹеҢ»зҷӮй–ўдҝӮиҖ…гҒ®ж–№гҖ…гҒ«гҒ”е ұе‘ҠгҒ«дјәгҒҶгҒ“гҒЁгӮ’е„Әе…ҲгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«гҒ„гӮҚгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҷгҒҺгҒҰгҖҒз·ҸжӢ¬гҒ—гҒҰиЁҳдәӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҶ…е®№гӮ’еҗҹе‘ігҖҒжҺЁж•ІгҒҷгӮӢжҷӮй–“гҒҢгӮӮгҒҶе°‘гҒ—еҝ…иҰҒгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ«жҺІијүгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгӮӮгҒҶе°‘гҒ—е…ҲгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒеҝөгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒз”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒд»ҠеҫҢдҪ•гӮүгҒӢгҒ®еҪўгҒ§е…¬иЎЁгҒҷгӮӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжң¬д»¶дәӢж•…гҒ«й–ўгӮҸгҒЈгҒҹеҢ»её«гӮ„з—…йҷўгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢйқһгӮ’гҒӮгҒ’гҒӨгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜжң¬ж„ҸгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒдәӢж•…гӮ„иЁҙиЁҹзөҢйҒҺгӮ’жӨңиЁјгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҒз—…йҷўеҒҙгҒ®еҜҫеҝңзӯүгҒ®е•ҸйЎҢзӮ№гӮ’жҢҮж‘ҳгҒӣгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„е ҙйқўгҒҜгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гӮӮгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®еҶҚзҷәгӮ’йҳІгҒҗгҖҒеҢ»зҷӮзҸҫе ҙгӮ’иүҜгҒҸгҒҷгӮӢгҖҒеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®и§ЈжұәгҒ®гҒӮгӮҠж–№гӮ’еӨүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«ж•ҷиЁ“гҒЁгҒҷгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®гҒҜдҪ•гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶиҰ–зӮ№гҖҒе•ҸйЎҢж„ҸиӯҳгҒ«еҹәгҒҘгҒҸгӮӮгҒ®гҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҘдёҠгҖҒе ұе‘ҠгҒ®дәҲе‘ҠгҒҝгҒҹгҒ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҹгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”йҒәж—ҸгҒҜгҖҒд»ҠеҫҢгҖҒдәӢж•…гҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒиҺүеҘҲгҒЎгӮғгӮ“гҒ®жӯ»гӮ’無駄гҒ«гҒ—гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ®жүӢиЁҳгӮ’жӣёгҒҚгҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒҠж°—жҢҒгҒЎгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮ“гҒӘж„ҸгӮ’жұІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҖҒпј•жңҲпј’пј–ж—Ҙд»ҳгҒ®жҜҺж—Ҙж–°иҒһзҘһеҘҲе·қзүҲгҒ«гҖҒгҒ”йҒәж—ҸгҒ®пј”пј’пј‘пј–ж—ҘгҒ®й—ҳгҒ„гӮ’жҢҜгӮҠиҝ”гӮӢеҶ…е®№гҒ®иЁҳдәӢгҒҢжҺІијүгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒ®гғӢгғҘгғјгӮ№гӮөгӮӨгғҲгҒ§гӮӮгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®еҸҚйҹҝгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҖҒеҸ–жқҗгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹжҜҺж—Ҙж–°иҒһгҒ®иЁҳиҖ…гҒ®ж–№гҒ«гӮӮеҫЎзӨјз”ігҒ—дёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒҰгӮӮиүҜгҒ„иЁҳдәӢгҒ§гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒиЁҳдәӢгҒ®гӮҝгӮӨгғҲгғ«гҖҒгғӘгғігӮҜгӮ’иІјгҒЈгҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
https://news.yahoo.co.jp/articles/4dc7e29e470a10228e5a5cdcf2d1183b8730a49e
гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁжЁӘйҒ“гҒ«йҖёгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЁҳдәӢгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒөгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒж—ҘгҖ…зӣ®гҒ«гҒҷгӮӢгғӢгғҘгғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮйҖҹе ұжҖ§гҒ«гҒ“гҒ гӮҸгӮүгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„йғЁеҲҶгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒқгӮҢгҒ§еҝ…иҰҒгҒ гҒЁгҒҜжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҖж–№гҒ§гҖҒйҖҹе ұжҖ§гӮҲгӮҠгӮӮгҖҒд»ҠеӣһгҒ®иЁҳдәӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒдёҖгҒӨдёҖгҒӨгҒ®дәӢиұЎгӮ’жҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰеҸ–жқҗгҒ—гҖҒжҺҳгӮҠдёӢгҒ’гҒҹдёҠгҒ§иЁҳдәӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ§гҒҜгҖҒиҝ‘гҒ„жҷӮжңҹгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®дәӢ件гҒӢгӮүеҫ—гӮӢгҒ№гҒҚж•ҷиЁ“гҒЁгҒ„гҒҶи¶Јж—ЁгҒ®иЁҳдәӢгӮ’гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёдёҠгҒ«жҺІијүгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҸгҒӨгӮӮгӮҠгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҢ»зҷӮгҒ«жҗәгӮҸгӮӢж–№гҖҒжі•еҫӢй–ўдҝӮиҖ…гӮ’еҗ«гӮҒгҖҒй–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢж–№гҒҜгҖҒгҒңгҒІгҒ”дёҖиӘӯгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ