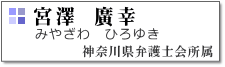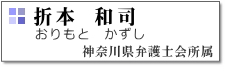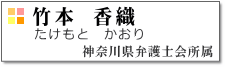еҢ»зҷӮйҒҺиӘӨгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
жҳЁе№ҙгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҹеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ§иЁјжӢ дҝқе…ЁжүӢз¶ҡгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹдәӢ件гҒҜ3件гҒ»гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®зӣёи«ҮгӮ„еҸ—д»»гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжңҖиҝ‘гҒҜиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒд»»ж„Ҹй–ӢзӨәжүӢз¶ҡгҒ§е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгӮ«гғ«гғҶгӮ’жҢҒеҸӮгҒ•гӮҢгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁжүӢз¶ҡгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜд»ҘеүҚгӮҲгӮҠгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҸ—д»»жҷӮзӮ№гҒӢгӮүгӮ«гғ«гғҶгҒ®е…ҘжүӢгӮ’е§ӢгӮҒгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒж•ўгҒҲгҒҰжүӢй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒҫгҒ§е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁеҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰиЁјжӢ дҝқе…ЁжүӢз¶ҡгҒ®е®ҹж–ҪгҒ«иҮігӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҜеҝ…然зҡ„гҒ«жёӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒиҝ·гҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒеҫҢйЎ§гҒ®жҶӮгҒ„гӮ’гҒӘгҒҸгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮгҖҒж…ҺйҮҚгӮ’жңҹгҒ—гҒҰиЁјжӢ дҝқе…ЁгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгӮҲгҒ„гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҖҒгҒқгҒҶеҠ©иЁҖгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒҜиІ»з”ЁгӮӮдҪҷеҲҶгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒиІ»з”ЁеҜҫеҠ№жһңгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒгҒқгҒ®еҫ—еӨұгӮ’еҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҳЁе№ҙе®ҹж–ҪгҒ—гҒҹиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®еҶ…гҒ®пј‘件гҒҜгҖҒд№…гҖ…гҒ®жүӢжӣёгҒҚгӮ«гғ«гғҶгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ«гҒҜйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶзү№жңүгҒ®еӨ§еӨүгҒ•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжүӢжӣёгҒҚгӮ«гғ«гғҶгҒҜеҶҷзңҹж’®еҪұгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…然еӨҡгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҲҶйҮҸгҒ«гӮӮгӮҲгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдҪңжҘӯзҡ„гҒ«гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠеӨ§еӨүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгӮӮгҖҒеҪ“и©ІеҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢиЁәзҷӮгҒ®жңҹй–“гӮ’еҢәеҲҮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҮәгҒҰгҒҚгҒҹжӨңжҹ»з”ЁзҙҷпјҲгӮ«гғ«гғҶгҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҒҜгҖҒжҷӮй–“зҡ„гҒӘй Ҷз•ӘгҒҢгӮҒгҒЎгӮғгӮҒгҒЎгӮғгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӘгҒҠгҒ•гӮүдҪҷеҲҶгҒ«жүӢй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒ3件гҒЁгӮӮиЁјжӢ дҝқе…ЁгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒзңҹзӣёи§ЈжҳҺгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжғ…е ұгҒҢе…ҘжүӢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ®йҒёжҠһгҒҢжӯЈгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҲгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒиІ»з”ЁгҒ®гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“д»»ж„Ҹй–ӢзӨәгҒ§е…ҘжүӢгҒ—гҖҒз–‘е•ҸгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ«з§»иЎҢгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж”№гҒ–гӮ“гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒЁгҒ®е…јгҒӯеҗҲгҒ„гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгӮұгғјгӮ№гғҗгӮӨгӮұгғјгӮ№гҒ§еҲӨж–ӯгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жҳЁе№ҙгҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒ§гҒҜгҖҒгғҷгғҶгғ©гғігҒ®дҝЎй јгҒ§гҒҚгӮӢејҒиӯ·еЈ«гҒ®ж–№гҒ«гӮ«гғЎгғ©гғһгғігӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
йҠҖеЎ©гӮ«гғЎгғ©гҒ®жҷӮд»ЈгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгғ—гғӯгҒ®гӮ«гғЎгғ©гғһгғігҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒд»ҠгҒ®жҷӮд»ЈгҒҜгҖҒеҶҷзңҹгҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгӮӮгғҮгӮёгӮ«гғЎгғҮгғјгӮҝгӮ’гҒқгҒ®е ҙгҒ§зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгғ—гғӯгҒ®гӮ«гғЎгғ©гғһгғігҒ§гҒӮгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҫгҒ—гҒҰгӮ„йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®д»•зө„гҒҝгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҹж®өеҸ–гӮҠгӮ’иёҸгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгӮ„гҖҒгғ‘гӮҪгӮігғідёҠгҒ§еҝ…иҰҒгҒӘжғ…е ұгҒ®зўәиӘҚгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®ж–№гҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®зөҢйЁ“гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгғ‘гӮҪгӮігғідёҠгҒ§йӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ§гҒҚгӮӢдәәгҒҢгғҷгӮ№гғҲгғҒгғ§гӮӨгӮ№гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒиЁјжӢ дҝқе…ЁгҒҜгҖҒдёҖжңҹдёҖдјҡгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒгғҜгғігӮўгғігғүгӮӘгғігғӘгғјгҒ®ж©ҹдјҡгҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒж„Ҹеӣізҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒӢгҒҜгҒЁгӮӮгҒӢгҒҸгҖҒеҢ»зҷӮеҒҙгҒҢеҮәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜдёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮұгғјгӮ№гҒҜжұәгҒ—гҒҰе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒйӣ»еӯҗгӮ«гғ«гғҶгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгӮҲгӮҠгҒқгҒ®еӮҫеҗ‘гҒҢеј·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮӮж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒдҝқе…ЁгҒ®зҸҫе ҙгҒ§гҒҜгҖҒеҝ…иҰҒгҒӘиіҮж–ҷгӮ’жјҸгӮҢгҒӘгҒҸжҠјгҒ•гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶйӣҶдёӯгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠзө„гҒҫгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҲҶгҖҒзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгӮүз–ІгӮҢжһңгҒҰгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒеҢ»зҷӮдәӢ件гҒ®иЁјжӢ дҝқе…ЁгҒӘгӮҠгҒ®зү№еҫҙгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҒгғқгӮӨгғігғҲгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰжүӢз¶ҡгҒ«иҮЁгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢиӮқиҰҒгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж–°е№ҙгҒ®гҒ”жҢЁжӢ¶
гҒӮгҒ‘гҒҫгҒ—гҒҰгҒҠгӮҒгҒ§гҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгӮӮгҖҒд»Ҡе№ҙгҒ§й–ӢиЁӯпј‘пјҗе№ҙгӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒӢгӮүгӮӮиӘ е®ҹгҒ«жҘӯеӢҷгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ©гҒҶгҒӢгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҒҠйЎҳгҒ„з”ігҒ—гҒӮгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢ件ж—ҘиЁҳпҪһйӣўе©ҡдәӢ件гҒ®иІЎз”ЈеҲҶдёҺгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҒҠи©ұ
йӣўе©ҡдәӢ件гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдё»иҰҒдәүзӮ№гҒ®дёҖгҒӨгҒҢиІЎз”ЈеҲҶдёҺгҒ§гҒҷгҖӮ
иІЎз”ЈеҲҶдёҺгҒЁгҒҜгҖҒеӨ«е©ҰгҒҢеҚ”еҠӣгҒ—гҒҰеҪўжҲҗгҒ—гҒҹиІЎз”ЈгӮ’е…ұжңүиІЎз”ЈгҒЁгҒҝгҒӘгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’еҝңеҲҶгҒ®еүІеҗҲпјҲеҺҹеүҮгҒҜпј’еҲҶгҒ®пј‘пјүгҒ§еҲҶгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒеӨ«е©ҰгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘдәӢжғ…гҖҒзөҢз·ҜгҒҢеҚғе·®дёҮеҲҘгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®зҜ„еӣІгҖҒи©•дҫЎгҒӢгӮүе…·дҪ“зҡ„з®—е®ҡж–№жі•гҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ§ж§ҳгҖ…гҒӘдәүзӮ№гҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒдәӢжЎҲгҒ®йӣҶз©ҚгҒҜгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒеҖӢгҖ…гҒ®дәӢ件гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨж–ӯгӮӮгҒҫгҒҹгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдёӯгҒ«гҒҜзҙҚеҫ—гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁгҒӢгҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸйқһеёёгҒ«жӮ©гҒҝгҒ®е°ҪгҒҚгҒӘгҒ„й ҳеҹҹгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒиІЎз”ЈеҲҶдёҺгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒҢзөҢйЁ“гҒ—гҒҹдәӢдҫӢгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒеҸӮиҖғгҒ«гҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒеҲҶдёҺгҒ®еүІеҗҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеҺҹеүҮпј’еҲҶгҒ®пј‘гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еүІеҗҲгҒ®зӮ№гҒҢдәүгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒзү№гҒ«гҒӢгҒӘгӮҠе№ҙеҸҺгҒҢеӨҡгҒ„й…ҚеҒ¶иҖ…гҒҢгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдё»ејөгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгӮҸгӮҠгҒЁиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒзөҗе©ҡеүҚгҒӢгӮүгҒ®еҠӘеҠӣгҒ§й«ҳеҸҺе…ҘгӮ’еҫ—гҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒҜгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒиӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҲӨдҫӢгӮӮгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҒқгҒ®зӮ№гӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰеҲҶдёҺеүІеҗҲгӮ’еӨүгҒҲгҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒӮгҖҒеҖӢеҲҘгҒ®дәӢжғ…гӮ’иЁҖгҒ„еҮәгҒ—гҒҹгӮүеҲҮгӮҠгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒеҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ§жүұгҒЈгҒҹгҒӮгӮӢе’Ңи§ЈдәӢжЎҲгҒ§гҒҜгҖҒеҲҶдёҺеүІеҗҲгҒҢиӘҝж•ҙгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒеӨ«гҒ®ж–№гҒҢе…ғгҖ…гҒӢгҒӘгӮҠгҒ®й«ҳеҸҺе…ҘгӮ’еҫ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҶгҒҲгҒ«гҖҒгҒ•гӮүгҒ«жүӢй–“гҒ®гҒӢгҒӢгӮӢеүҜжҘӯгҒ«жҗәгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгҒЎгӮүгҒ§гӮӮгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®й«ҳеҸҺе…ҘгӮ’еҫ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢдҫӢгҒ§гҖҒжӯЈжҘӯгҒ®гҒҝгҒ§еҚҒеҲҶгҒ«жҡ®гӮүгҒӣгӮӢзҠ¶жіҒгҒ§гҖҒеүҜжҘӯгӮ’й ‘ејөгҒЈгҒҰй«ҳеҸҺе…ҘгӮ’еҫ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜеӨ«гҒ®жүҚиҰҡгӮ„еҠӘеҠӣгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢеҰ»гҒ®еҒҙгӮ’иӘ¬еҫ—гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ®е’Ңи§ЈгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮұгғјгӮ№гғҗгӮӨгӮұгғјгӮ№гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ№гҒҚдәӢжЎҲгҒҜгҒқгӮҢгҒӘгӮҠгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒе®ҹеӢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеҲҶдёҺгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒҷгҒ№гҒҚе…ұжңүиІЎз”ЈгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе…ЁдҪ“гӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒиЁҖгҒҶгҒҜжҳ“гҒ—гҒ§е®ҹйҡӣгҒ«гҒҜзөҗж§ӢеӨ§еӨүгҒ§гҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒзүҮж–№гҒ®й…ҚеҒ¶иҖ…гҒ®гҒҝгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®иІЎз”ЈгӮ’з®ЎзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒд»–ж–№гҒ®й…ҚеҒ¶иҖ…гҒҜеӨ«е©ҰгҒ®иІЎз”ЈзҠ¶жіҒгӮ’гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгҒ§зӣёи«ҮгҒ«жқҘгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜжұәгҒ—гҒҰе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡиҮӘе®…еҶ…гҒ§зӣёжүӢж–№еҗҚзҫ©гҒ®иіҮз”ЈзҠ¶жіҒгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢжүӢжҺӣгҒӢгӮҠгҒ«гҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒӘиіҮж–ҷгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгӮ’е…ҘжүӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҠ©иЁҖгҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒ—гҖҒйӣўе©ҡгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ‘гӮҢгҒ©гҖҒеӨ«е©ҰгҒ®иІЎз”ЈзҠ¶жіҒгҒҢжӯЈзўәгҒ«жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒйғөдҫҝзү©гҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒ家гҒ®дёӯгҒ§зӣ®гҒ«е…ҘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘиіҮз”ЈгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиіҮж–ҷгӮ’гҒӮгӮӢзЁӢеәҰзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒӢгӮүејҒиӯ·еЈ«дәӢеӢҷжүҖгҒ«иЎҢгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹж–№гҒҢгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«жүұгҒЈгҒҹдәӢжЎҲгҒ§гӮӮгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҠ©иЁҖгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҒӮгҒ’гҒҰзӣёи«ҮиҖ…гҒҢ家гҒ®дёӯгҒ§иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹиіҮж–ҷгӮ’еҶҷзңҹгҒ«ж’®гҒЈгҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиӘҝеҒңжүӢз¶ҡгҒ«иҮЁгӮ“гҒ гҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеӨ«гҒӢгӮүгҒҜгҒқгҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒ®иіҮз”ЈгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸй–ӢзӨәгҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒеёӯдёҠгҒ§жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰй–ӢзӨәгӮ’жұӮгӮҒгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹгӮүеҲҶдёҺеҜҫиұЎиІЎз”ЈгҒҢпј’пјҗпјҗпјҗдёҮеҶҶд»ҘдёҠгӮӮеў—гҒҲгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«иӘҝеҒңгҒӘгҒ©гҒ®жүӢз¶ҡгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹеҫҢгҒ§гӮӮгҖҒгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒЁиӘҝгҒ№гҒҰгӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгӮ’йҮҚгҒӯгҒҰиЎҢгҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиЎЁгҒ«еҮәгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹеҲҘгҒ®иІЎз”ЈгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж–ҮжӣёйҖҒд»ҳеҳұиЁ—гҒ®жүӢз¶ҡгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж–№жі•гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”гҒҸжңҖиҝ‘жүұгҒЈгҒҹдәӢ件гҒ§гӮӮгҖҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиҮӘеҲҶеҗҚзҫ©гҒ®иІЎз”ЈгҒҜгҒӘгҒ„гҒЁдё»ејөгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеҒҙгҒ®еҸ–еј•еұҘжӯҙгӮ’и©ізҙ°гҒ«гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеҲҘгҒ®йҠҖиЎҢеҸЈеә§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ«ж•°зҷҫдёҮеҶҶгӮӮгҒ®й җиІҜйҮ‘гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒдҫқй јиҖ…гҒ«жңүеҲ©гҒӘи§ЈжұәгҒҢеӣігӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ејҒиӯ·еЈ«гҒ®гӮ№гӮҝгғігӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒдҫқй јиҖ…гҒӢгӮүдәӢжғ…гҖҒзөҢз·ҜгӮ„ж—ҘеёёгҒ®йҮ‘йҠӯз®ЎзҗҶгӮ„ж”ҜеҮәгҒ®зҠ¶жіҒгҒӘгҒ©гӮ’зҙ°гҒӢгҒҸиҒһгҒҚеҸ–гҒЈгҒҹгӮҠгҖҒе…ҘжүӢгҒ—гҒҹйҖҡеёігҒӘгҒ©гҒ®еҸ–еј•еұҘжӯҙгӮ’еӯҗзҙ°гҒ«жӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжүӢй–“гҒҜгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҲҘиіҮз”ЈгҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгӮӢгҒ«гҒӣгӮҲгҖҒиҰӢгҒӨгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ«гҒӣгӮҲгҖҒзҙҚеҫ—гҒ®гӮҶгҒҸзөҗи«–гӮ’е°ҺгҒҸгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜеҝ…иҰҒгҒӘдҪңжҘӯгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷпјҲгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁиЎЁзҸҫгҒҜгӮҲгҒҸгҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰжҲҗеҠҹдҪ“йЁ“гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҖҒгҒ©гҒ“гҒӢгҖҒе®қжҺўгҒ—гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгғ‘гӮәгғ«гӮ’и§ЈгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘж°—еҲҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒиІЎз”ЈеҲҶдёҺгҒ«йҷҗгӮүгҒҡгҖҒйӣўе©ҡй–ўдҝӮгҒҢгӮүгҒҝгҒ®жЎҲ件гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®жұәгӮҒгҒ”гҒЁгӮ„йҖІгӮҒж–№гҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгғ«гғјгғҶгӮЈгғіеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҒқгҒ“гҒ«гҒҜдёҖе®ҡгҒ®еҗҲзҗҶжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҖҶгҒ«гҖҒгғһгғӢгғҘгӮўгғ«зҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ«еҫ“гҒ„йҒҺгҒҺгҒҰгҖҒдәӢжЎҲгҒ”гҒЁгҒ®еҜҫеҝңгҒ®жҹ”и»ҹжҖ§гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒеҲӨж–ӯгҒҢдәәй–“е‘ігҒ«ж¬ гҒ‘гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жңҖиҝ‘гӮӮгҖҒгҒӮгӮӢдәӢ件гҒ§зөҢйЁ“гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӨ«гҒҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеғҚгҒӢгҒҡгҖҒеҰ»гҒҢгғ•гғ«гҒ«еғҚгҒ„гҒҰ家иЁҲгӮ’ж”ҜгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶзөҢз·ҜгҒҢгҒӮгӮӢдёӯгҒ§гҖҒеӨ«гҒӢгӮүиІЎз”ЈеҲҶдёҺгӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҹдәӢдҫӢгҒ§пјҲжҳӯе’ҢгҒ®жҷӮд»ЈгҒӘгӮүгҖҒгғ’гғўгҒ гҒЁгҒӢй«ӘзөҗгҒ„гҒ®дәӯдё»гҒЁгҒӢиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰи”‘гҒҫгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжҷӮд»ЈгҒҜгҒ©гӮ“гҒ©гӮ“гҒЁеӨүгӮҸгҒЈгҒҰиЎҢгҒҚгҒҫгҒҷгғ»гғ»гғ»пјүгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҖҒеҰ»гҒҢиІҜгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹй җиІҜйҮ‘е…ЁдҪ“гҒ®гҒҶгҒЎгҒ®пј’еҲҶгҒ®пј‘гӮ’еӨ«гҒ«еҲҶдёҺгҒҷгҒ№гҒҚгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёҖиҰӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒҹгҒ гҒЎгҒ«иӘӨгҒЈгҒҹеҲӨж–ӯгҒЁгҒҜиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒқгҒ®дәӢ件гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҰ»гҒ®еҒҙгҒҢиІҜгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹй җиІҜйҮ‘гҒҜгҖҒпј’дәәгҒ®гҒҠеӯҗгҒ•гӮ“гҒҢж•°е№ҙд»ҘеҶ…гҒ«еӨ§еӯҰгҒ«йҖІеӯҰгҒҷгӮӢдәҲе®ҡгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ“гҒ§гҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзўәе®ҹгҒӘеӯҰиІ»гҒ®ж”ҜеҮәгҒ«еӮҷгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҶдәӢжғ…гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е®ҹйҡӣгҖҒз§Ғз«Ӣй«ҳж ЎгӮ„еӨ§еӯҰгҒёгҒ®йҖІеӯҰгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒЁгҖҒдёҖжҷӮжңҹгҒ«еӨҡйЎҚгҒ®е…ҘеӯҰйҮ‘гҖҒжҺҲжҘӯж–ҷгҖҒеҸ—йЁ“иІ»з”ЁгҖҒдәҲеӮҷж ЎиІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒпј’дәәгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгғҲгғјгӮҝгғ«гҒ§ж•°зҷҫдёҮеҶҶгҒ§гҒҜеҸҺгҒҫгӮүгҒҡгҖҒе„ӘгҒ«пј‘пјҗпјҗпјҗдёҮеҶҶгҒҜи¶…гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзўәе®ҹгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҪ“然гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨҡйЎҚгҒ®ж”ҜеҮәгӮ’гҒ„гҒ–йҮ‘гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢжҷӮжңҹгҒ®еҸҺе…ҘгҒ гҒ‘гҒ§иЈңгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜеҲ°еә•дёҚеҸҜиғҪгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒгҒқгӮҢгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰгҒҠгҒҸгҒ®гҒҜиҰӘгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®иІ¬еӢҷгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дё»ејөгҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰиӘҝгҒ№гҒҹеҲӨдҫӢгҒ®дёӯгҒ«гҒҜе°ҶжқҘгҒ®еӯҰиІ»гҒёгҒ®еӮҷгҒҲеҲҶгӮ’еҲҶдёҺгҒ®еҜҫиұЎгҒ«гҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҲӨдҫӢгӮӮеј•з”ЁгҒ—гҒҰдё»ејөгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒзӣёжүӢж–№гҒ«иіҮз”Је…ЁдҪ“гҒ®пј’еҲҶгҒ®пј‘гӮ’еҲҶдёҺгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒЁгҒ®еҪўејҸзҡ„гҒӘеҲӨж–ӯгӮ’дёӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®д»•дәӢгҒ«й•·гҒҸй–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒжҳҺгӮүгҒӢгҒ«еёёиӯҳгҒ«ж¬ гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгӮҠгҖҒжҙһеҜҹеҠӣгҖҒжғіеғҸеҠӣгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒдәәй–“е‘ігҒ«ж¬ гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘиЈҒеҲӨе®ҳгҒҢе°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒҡгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжүҝзҹҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЈҒеҲӨе®ҳгҒЁеҜҫеіҷгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢд»•дәӢдёҠгҒ®гӮ№гғҲгғ¬гӮ№гҒ®гҒӢгҒӘгӮҠгҒ®еүІеҗҲгӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®дәӢ件гҒ®жҷӮгӮӮеҝғеә•гҒқгҒҶж„ҹгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒЁгҒҫгҒӮгҖҒгҒ„гҒ„гҒ“гҒЁгҒ°гҒӢгӮҠгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸйӣўе©ҡй–ўйҖЈдәӢ件гҒҜгҖҒжӨңиЁҺгҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҢдәӢдҫӢгҒ”гҒЁгҒ§еҚғе·®дёҮеҲҘгҒ§еұұгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜж—©гӮҒгҒ«ејҒиӯ·еЈ«гҒ®еҠ©иЁҖгӮ’д»°гҒ„гҒ§гҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§еҫ—гҒҹеҠ©иЁҖгҒҢжҷӮгҒ«жңүз”ЁгҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒзӣёи«ҮиҖ…гҒ®ж¬ЎгҒ®дәәз”ҹгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜгҒҠеӯҗгҒ•гӮ“гҒ®дәәз”ҹгӮ’гӮӮеӨ§гҒҚгҒҸе·ҰеҸігҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжұәгҒ—гҒҰзЁҖгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒйӣўе©ҡдәӢ件гҒ«йҷҗгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒёгҒ®зӣёи«ҮгӮ„дҫқй јгҒҜгҖҒеҫ—жүӢдёҚеҫ—жүӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгҒ©гҒ“гҒҫгҒ§иҰӘиә«гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒӢгҒЁгҒӢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜзӣёжҖ§гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒиӨҮж•°гҒ®ејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒҠиҖғгҒҲгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹж–№гҒҢгӮҲгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—ҘгҖ…йӣ‘ж„ҹпҪһеәғйҷөй«ҳж ЎгҒ®дёҚзҘҘдәӢгӮ’иҖғеҜҹгҒҷгӮӢгҖҖPartпј’
Partпј‘гҒӢгӮүгҒ®з¶ҡгҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®дёҚзҘҘдәӢгҒёгҒ®еҜҫеҝңгҒ§гҖҒгҒ•гӮүгҒ«е•ҸйЎҢгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒҜй«ҳйҮҺйҖЈгҒӘгҒ©гҒ®й–ўдҝӮеӣЈдҪ“гҒ®еҜҫеҝңгҒ§гҒҷгҖӮ
жң¬д»¶гҒҢпј‘жңҲжҷӮзӮ№гҒ«зҷәиҰҡгҒ—гҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒеәғеі¶гҒ®й«ҳйҮҺйҖЈгҒҜеәғйҷөй«ҳж ЎеҒҙгҒ®е ұе‘ҠгӮ’йөңе‘‘гҒҝгҒ«гҒ—гҒҹеҪўгҒ§гҖҒеҺійҮҚжіЁж„ҸгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒ«дҪ•гҒ®еҮҰеҲҶгҒ«гӮӮгҒӘгӮүгҒӘгҒ„еҜҫеҝңгӮ’гҒ—гҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ“гҒқгҒҢд»ҠгҒ®й«ҳж ЎгӮ№гғқгғјгғ„з•ҢгҒ®дёҚеҒҘе…ЁгҒ•гҒ®иЎЁгӮҢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒйҮҚеӨ§гҒӘдәәжЁ©дҫөе®ігӮ„гҒқгӮҢгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷйғЁжҙ»гҒ®з—…е·ЈгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒҢиҰӢйҒҺгҒ”гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒй«ҳйҮҺйҖЈгҒҜгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„иӘ°гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгҒ®еӯҳеңЁж„Ҹзҫ©гҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгҒҰгӮӮиҮҙгҒ—ж–№гҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮӮгҒқгӮӮгҖҒжӣ–жҳ§гҒ§гҒӘгҒӮгҒӘгҒӮгҒӘеҮҰеҲҶгӮ’жұәгӮҒгҒҹеәғеі¶гҒ®й«ҳйҮҺйҖЈгҒ®еүҜдјҡй•·гҒҢеәғйҷөй«ҳж ЎгҒ®ж Ўй•·гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҖҒеҮҰеҲҶгҒ®е…¬жӯЈгҒ•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒзө„з№”гҒҢжӯЈеёёгҒ«ж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒйҮҚеӨ§гҒӘз–‘зҫ©гӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«жң¬д»¶гҒ®е ҙеҗҲгҖҒиў«е®іиҖ…гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒЁйЈҹгҒ„йҒ•гҒҶеҶ…е®№гҒ§гҒ®е ұе‘ҠгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒеәғйҷөй«ҳж ЎгҒ®ж Ўй•·гҒҜгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҜгҒҡгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮиў«е®іиҖ…гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒЁдёЎи«–дҪөиЁҳгҒ§й«ҳйҮҺйҖЈеҒҙгҒ«е ұе‘ҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷпјҲгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒ件гҒ®е ұе‘ҠжӣёгҒҢжң¬зү©гҒ§гҖҒеҠ е®із”ҹеҫ’гҒӢгӮүиҒһгҒҚеҸ–гҒЈгҒҹеҶ…е®№гҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиҷҡеҒҪе ұе‘ҠгҒ®иІ¬д»»гҒҜгӮҲгӮҠйҮҚеӨ§гҒ§гҒҷпјүгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеәғйҷөй«ҳж ЎгҒ®ж Ўй•·пјҲе…јй«ҳйҮҺйҖЈеүҜдјҡй•·пјүгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҷгӮүгҒ—гҒӘгҒ„гҒ§йҮҺзҗғйғЁгҒ®жҙ»еӢ•гҒ«жңүеҲ©гҒ«гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘе ұе‘ҠгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒеәғеі¶гҒ®й«ҳйҮҺйҖЈгҒҢжҳҘеӯЈеӨ§дјҡгҖҒеӨҸгҒ®дәҲйҒёгҒёгҒ®еҮәе ҙгҒ«ж”ҜйҡңгҒ®гҒӘгҒ„еҮҰеҲҶгҒ§жёҲгҒҫгҒӣгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒй«ҳйҮҺйҖЈгҒ®иҮӘжө„иғҪеҠӣгҒ«з–‘е•Ҹз¬ҰгҒҢд»ҳгҒҸгҒ®гҒҜеҪ“然гҒ®гҒ“гҒЁгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
иӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒең°еҹҹгҒ®й«ҳйҮҺйҖЈгҒҜгҖҒең°еҹҹгҒ®жңүеҠӣж ЎгҒ®жҢҮе°ҺиҖ…гӮүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гҒ®зЁ®гҒ®дәӢжЎҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжҳҺж—ҘгҒҜжҲ‘гҒҢиә«гҒ§иҮӘгҒҡгҒЁиә«еҶ…еәҮгҒ„зҡ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒжңүеҠӣж ЎгӮ„еј·гҒ„зҷәиЁҖжЁ©гӮ’жҢҒгҒӨзҗҶдәӢгӮүгҒ«й…Қж…®гҒ—гҒҹдёҚе…¬жӯЈгҒӘзөҗи«–гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒд»ҠеӣһгҒ«йҷҗгӮүгҒҡгҖҒеҚҒеҲҶгҒ«иө·гҒ“гӮҠеҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒй«ҳйҮҺйҖЈгҒЁгҒ„гҒҶзө„з№”иҮӘдҪ“гҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҪ№зӣ®гӮ’еҝҳгӮҢгҖҒеҪўйӘёеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮеҗҰе®ҡгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒй«ҳйҮҺйҖЈгҒ®зө„з№”йҒӢе–¶гҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢе•ҸгҒ„зӣҙгҒ•гӮҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒдёҚзҘҘдәӢгҒ®иӘҝжҹ»гӮ„еҮҰеҲҶгҒ®еҲӨж–ӯгҒ®йҒҺзЁӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжңүеҠӣж ЎгӮ„еј·гҒ„зҷәиЁҖжЁ©гӮ’жҢҒгҒӨзҗҶдәӢгҒ®еҪұйҹҝгӮ’жҺ’йҷӨгҒ—гҖҒдёӯз«ӢгҒӘеӨ–йғЁгҒ®е§”е“ЎгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰдёҖе®ҡгҒ®еј·гҒ„иӘҝжҹ»жЁ©йҷҗгӮ’дёҺгҒҲгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹиӘҝжҹ»гҒЁеҜ©жҹ»гҒҢдҝқйҡңгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘд»•зө„гҒҝгӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгӮ„гҖҒгҒқгҒ“гҒ§гҒ®иӘҝжҹ»зөҗжһңгӮ„еҮҰеҲҶгҒ«й–ўгҒҷгӮӢж„ҸиҰӢгҒҢе°ҠйҮҚгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҜеҝ…й ҲгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶпјҲгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒдёҖж–№гҒ§гҖҒиІ¬д»»гҒ®еҸ–гӮҠж–№гҒҢж—§ж…Ӣдҫқ然гҒҹгӮӢйҖЈеёҜиІ¬д»»гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гӮӮжҷӮд»ЈйҢҜиӘӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮҲгӮҠжҹ”и»ҹгҒӘеҜҫеҝңгҒҢжӨңиЁҺгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҖҶгҒ«дәӢе®ҹгӮ’йҡ и”ҪгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒзҹ®е°ҸеҢ–гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜгӮҲгӮҠеҺігҒ—гҒ„еҮҰеҲҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮжӨңиЁҺгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶпјүгҖӮ
д»®гҒ«гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹж”№йқ©гҒҷгӮүгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒй«ҳйҮҺйҖЈгҒ®иҮӘжө„дҪңз”ЁгҒ«гҒҜжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгӮ№гғқгғјгғ„иЈҒеҲӨжүҖгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨ–йғЁзө„з№”гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒдёҚзҘҘдәӢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢз”із«ӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘҝжҹ»гҖҒеҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘеҲ¶еәҰгӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ№гҒҚгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷ(еҢ»зҷӮдәӢж•…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеҢ»зҷӮдәӢж•…иӘҝжҹ»еҲ¶еәҰгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдјјгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘжһ зө„гҒҝгҒ«гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгӮҲгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“)гҖӮ
гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгҖҒд»ҠеӣһгҒ®дәӢ件гҒҜгҖҒд»ҠгҒ®й«ҳж ЎйҮҺзҗғгҒҢйқһеёёгҒ«ж №ж·ұгҒ„е•ҸйЎҢгӮ’жҠұгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶз–‘еҝөгӮ’зӨҫдјҡгҒ«зҹҘгӮүгҒ—гӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮөгғғгӮ«гғјгҒ«жҠјгҒ•гӮҢж°—е‘ігҒЁгҒҜгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒйҮҺзҗғгҒҜгӮўгғһгғҒгғҘгӮўгҒӢгӮүгғ—гғӯгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ«ж§ҳгҖ…гҒӘеҲ©е®ігҒҢзөЎгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢе·ЁеӨ§гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ®й ҳеҹҹгҒ§гҒҷгҖӮ
дёӯгҒ§гӮӮй«ҳж ЎйҮҺзҗғгҒҜгҖҒз”Іеӯҗең’гҒ«еҮәгҒҰжҙ»иәҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒйҒёжүӢгҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒжҢҮе°ҺиҖ…гҖҒеӯҰж ЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒеӯҰж ЎгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜиҮідёҠе‘ҪйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ«гҖҒеҪјгӮүгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰз”Іеӯҗең’гҒ«еҮәгӮӢгҒҶгҒҲгҒ§дёҚйғҪеҗҲгҒӘдёҚзҘҘдәӢгҒҜиЎЁжІҷжұ°гҒ«гҒ—гҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеӢ•ж©ҹгҒҢеғҚгҒҚгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиө·гҒҚгҒҹдёҚжӯЈгӮ’жӯЈгҒ•гҒҡгҖҒдёҚжӯЈгҒ®жё©еәҠгӮ’иҰӢгҒҰиҰӢгҒ¬гҒөгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰйҮҺж”ҫгҒ—гҒ«гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҲгҒ°й«ҳж ЎйҮҺзҗғгҒ«жңӘжқҘгҒҜгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒгҒқгҒҶгҒӘгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгҒҜгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҚгҒЎгӮ“гҒЁгҒ—гҒҹж”№йқ©гӮ’е®ҹж–ҪгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ«гҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
иҮӘжө„дҪңз”ЁгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒ„гҒҲгҒ°гҖҒе…ұеӮ¬гҒ«еҗҚгӮ’йҖЈгҒӯгӮӢжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҒжҜҺж—Ҙж–°иҒһгҒ®иІ¬д»»гӮӮйҮҚеӨ§гҒ§гҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гӮӮдёЎзӨҫгҒ®е ұйҒ“гҒҜеҸҠгҒіи…°гҒЁгҒ„гҒҶеҚ°иұЎгӮ’еј·гҒҸеҸ—гҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зө„з№”гҒ®дёҚжӯЈгҒ«еҲҮгӮҠиҫјгӮ“гҒ§зңҹе®ҹгӮ’е ұгҒҳгӮӢе…¬еҷЁгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®иІ¬д»»гӮ’иІ гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгғһгӮ№гӮігғҹгҒҢгҖҒиҮӘзӨҫгҒ®еҲ©е®ігҒ«зөЎгӮҖеұҖйқўгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁйҖ”з«ҜгҒ«жҺ§гҒҲгӮҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгӮ·гғјгғігҒҜгғ•гӮёгғҶгғ¬гғ“гҒ®жҷӮгҒ«гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжң¬еҪ“гҒ«жғ…гҒ‘гҒӘгҒҸгҖҒеј·гҒ„жҶӨгӮҠгӮ’иҰҡгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
дё»еӮ¬иҖ…еҒҙгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҒ“гҒқгҖҒгҒӘгҒҠгҒ®гҒ“гҒЁиҘҹгӮ’жӯЈгҒ—гҒҰгҖҒиёҸгҒҝиҫјгӮ“гҒ иӘҝжҹ»гҒЁе ұйҒ“гӮ’иЎҢгҒҶгҒ№гҒҚгҒ гҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒҷгӮүгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒӘгӮүдёЎж–°иҒһзӨҫгҒЁгӮӮй«ҳж ЎйҮҺзҗғгҒӢгӮүгҒ•гҒЈгҒ•гҒЁжүӢгӮ’еј•гҒҸгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
з”Іеӯҗең’гӮ’еӨўиҰӢгӮӢйқ’е°‘е№ҙгҒҢеӨ§дәәгҒ®йғҪеҗҲгӮ„жҖқжғ‘гҒ§йЈҹгҒ„зү©гҒ«гҒ•гӮҢгҖҒдёҚеҪ“гҒӘжүұгҒ„гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж”ҫзҪ®гҒ—гҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒе·ЁеӨ§гҒӘеҲ©жЁ©гҒҢзөЎгӮҖгҒӢгӮүгҒ“гҒқгҖҒиҰҡжӮҹгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰзңҹзӣёи§ЈжҳҺгҒЁж”№йқ©гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
е…ғйҮҺзҗғе°‘е№ҙгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒй«ҳж ЎйҮҺзҗғгҒҢеҺҹзӮ№гҒ«жҲ»гҒЈгҒҰеӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒ®еӨўиҰӢгӮӢгҒ«зӣёеҝңгҒ—гҒ„е ҙжүҖгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еҝғгҒӢгӮүйЎҳгҒЈгҒҰгӮ„гҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
ж—ҘгҖ…йӣ‘ж„ҹпҪһеәғйҷөй«ҳж ЎгҒ®дёҚзҘҘдәӢгӮ’иҖғеҜҹгҒҷгӮӢгҖҖPartпј‘
з§ҒгҒҢеӯҗдҫӣгҒ®й ғгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҖҒеәғйҷөй«ҳж ЎгҒ«е®Үж №гҒЁгҒ„гҒҶжҠ•жүӢгҒҢгҒ„гҒҰгҖҒз”Іеӯҗең’гҒ§еӨ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹпјҲзўәгҒӢгҖҒжә–е„ӘеӢқгҒ—гҒҹгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒд»ҠеәҰгҒҜдҪҗдјҜгҒЁгҒ„гҒҶжҠ•жүӢгҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҰеҪјгӮӮз”Іеӯҗең’гҒ§жҙ»иәҚгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дҪҗдјҜжҠ•жүӢгҒ®еҗҚеүҚгҒҜз§ҒгҒЁеҗҢгҒҳе’ҢеҸёгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒ”гҒҸиҰӘиҝ‘ж„ҹгӮ’иҰҡгҒҲгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еҫҢгҒ«дҪҗдјҜжҠ•жүӢгҒҜеәғеі¶гӮ«гғјгғ—гҒ«е…ҘеӣЈгҒ—гҖҒпј‘пјҷпј—пј•е№ҙгҒ«гҒҜдёүжң¬жҹұгҒ®дёҖдәәгҒЁгҒ—гҒҰгӮ«гғјгғ—гҒ®еҲқе„ӘеӢқгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒӘгҒҠгҒ•гӮүиЁҳжҶ¶гҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҖҒеәғйҷөй«ҳж ЎгҒҜе…ЁеӣҪзҡ„гҒ«жңүеҗҚгҒӘеј·иұӘж ЎгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»ҠгҒқгҒ®еәғйҷөй«ҳж ЎгҒ§еӨ§еӨүгҒӘдёҚзҘҘдәӢгҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘзӨҫдјҡе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒд»ҠгҒ®жҷӮд»ЈгҒҜиүҜгҒҸгӮӮжӮӘгҒҸгӮӮгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒ§жғ…е ұгҒҢзһ¬гҒҸй–“гҒ«жӢЎж•ЈгҒ—гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеәғйҷөй«ҳж ЎгӮ„й«ҳйҮҺйҖЈгҒ®еҜҫеҝңгҒ«дёҚеҸҜи§ЈгҒӘзӮ№гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒйЁ’еӢ•гҒҜеҸҺгҒҫгӮӢгҒ°гҒӢгӮҠгҒӢжҶ¶жё¬зҡ„гҒӘжғ…е ұгҒ®жӢЎж•ЈгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдәӢж…ӢгҒ®еҸҺжӢҫгҒҢеӣігӮҢгҒӘгҒ„зҠ¶жіҒгҒҢз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзҹҘгӮҢгҒ°зҹҘгӮӢгҒ»гҒ©гҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒ®ж №гҒҜж·ұгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒҲгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒиӨҮйӣ‘гҒ«еҲ©е®ігҒҢзөЎгҒҝеҗҲгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒз«Ӣе ҙгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҚүгҒҲж–№гҒҢз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮӢе•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеәғеі¶еҮәиә«гҒ®е…ғйҮҺзҗғе°‘е№ҙпјҲгҒ®ејҒиӯ·еЈ«пјүгҒЁгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҖҒиҖғеҜҹгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒдёҚзҘҘдәӢгҒҢеӨ§гҒҚгҒӘзӨҫдјҡе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹжҷӮзӮ№гҒ§еәғйҷөй«ҳж ЎгҒҜпјіпј®пјігҒ®иў«е®іиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҒ”гҒЁгҒҚиЁҖгҒ„иЁігӮ’гҒ—гҒҰеҮәе ҙиҫһйҖҖгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜжң¬иіӘгҒӢгӮүзӣ®гӮ’йҖёгӮүгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®ејҒи§ЈгҒ«гҒ—гҒӢиҒһгҒ“гҒҲгҒҡгҖҒеҚұж©ҹз®ЎзҗҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜйқһеёёгҒ«жӢҷгҒ„еҜҫеҝңгҒ гҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иҫһйҖҖзӣҙеҫҢгҒ®дҝқиӯ·иҖ…дјҡгҒ§иӘ°гҒӢгӮүгӮӮиіӘе•ҸгҒҢеҮәгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжҷ®йҖҡгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°д»ҠеӣһгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§еӯҗгӮ’й җгҒ‘гӮӢиҰӘгҒҢеӯҰж ЎеҒҙгҒ«е•ҸгҒ„гӮ’жҠ•гҒ’гҒӢгҒ‘гҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒҜгҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒиіӘе•ҸгҒ•гҒҲеҮәгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҖҒгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰе•ҸйЎҢгҒ®й—ҮгҒ®ж·ұгҒ•гҖҒж°—жҢҒгҒЎжӮӘгҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®зҷәз«ҜгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ件гҒ§гҒҜгҖҒиў«е®іиҖ…гҒҢиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢдәӢе®ҹгҒЁй«ҳж ЎеҒҙгҒ®й«ҳйҮҺйҖЈгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе ұе‘ҠгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘйЈҹгҒ„йҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„дҪ•гҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒгҒҫгҒҡдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮгҒқгҒ®зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзңҹе®ҹгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
иў«е®іиҖ…гҒ®дё»ејөгҒ©гҒҠгӮҠгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеҜ®гҒ®дёӯгҒ§жҳҺгӮүгҒӢгҒ«иЁұе®№зҜ„еӣІгӮ’и¶…гҒҲгҒҹзҠҜзҪӘзҡ„иЎҢзӮәгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮйҮҺзҗғйғЁгҒ®жҢҮе°ҺиҖ…гӮ„еӯҰж ЎеҒҙгҒҢдәӢ件гӮ’йҡ и”ҪгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜзҹ®е°ҸеҢ–гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒЁгҒҜжҘөгӮҒгҒҰйҮҚеӨ§гҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиў«е®іиҖ…еҒҙгҒӢгӮүгғҚгғғгғҲдёҠгҒ«жөҒеҮәгҒ—гҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢеӯҰж ЎдҪңжҲҗгҒ®е ұе‘ҠжӣёгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®е ұе‘ҠжӣёгҒ®и©•дҫЎгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӯҰж ЎеҒҙгӮӮгҖҒиў«е®іиҖ…еҒҙгҒ«е ұе‘ҠжӣёгӮ’жёЎгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜиӘҚгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгӮӮгҒ—гғҚгғғгғҲдёҠгҒ«жөҒеҮәгҒ—гҒҹе ұе‘ҠжӣёгҒҢжң¬зү©гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиў«е®іиҖ…еҒҙгҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгӮ’еҗҰе®ҡгҒҷгӮӢеӯҰж ЎеҒҙгҒ®дё»ејөгҒ«гҒҜйҮҚеӨ§гҒӘз–‘зҫ©гҒҢз”ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҚгғғгғҲдёҠгҒ«жөҒеҮәгҒ—гҒҹе ұе‘ҠжӣёгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒй»’еЎ—гӮҠйғЁеҲҶгҒҜгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒдёӯиә«гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁдәӢе®ҹгҒ®иЁҳијүгҒ®гҒ•гӮҢж–№гҒ«зү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜиҒһгҒҚеҸ–гҒЈгҒҹдәӢе®ҹзөҢйҒҺгҒ®иЁҳиҝ°гҒ®з®ҮжүҖгҒ§гҖҒгҖҢгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЎЁзҸҫгҒЁгҖҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЎЁзҸҫгҒҢдҪҝгҒ„еҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҖҒгҒқгҒ®йҒ•гҒ„гҒ«гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒңгҒӘгӮүгҖҒгҖҢгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЎЁзҸҫгҒҜеҠ е®іиҖ…еҒҙгҒӢгӮүиҒһгҒҚеҸ–гҒЈгҒҹдәӢе®ҹгҖҒгҖҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЎЁзҸҫгҒҜиў«е®іиҖ…гҒ®дё»ејөдәӢе®ҹгҒЁиӘӯгӮҖгҒ®гҒҢиҮӘ然гҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒ«иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҳиҝ°гҒҜгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢи№ҙгӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҖҚгҖҢж¬ЎгҖ…гҒЁжүӢгӮ’еҮәгҒ—гҒҹгҖҚгҖҢгғ“гғігӮҝгӮӮгҒ—гҒҹгҖҚзӯүгҖҒеҹ·жӢ—гҒӘжҡҙеҠӣгҒҢз№°гӮҠиҝ”гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе…ЁдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜиў«е®іиҖ…гҒ®дё»ејөгҒ«иҝ‘гҒ„еҶ…е®№гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҒ®ж–Үз« гҒ§гҒҜгҖҒгҖҢгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҖҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҚгҒҢж··еңЁгҒ—гҒҰдёҖдҪ“еҢ–гҒ—гҒҹйғЁеҲҶгӮӮеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒеӯҰж ЎеҒҙгӮӮиў«е®іиҖ…гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒҢжӯЈгҒ—гҒ„гҒЁи©•дҫЎгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ®еҚ°иұЎгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒжҡҙеҠӣгҒ«й–ўгӮҸгҒЈгҒҹз”ҹеҫ’гҒ®дәәж•°гӮӮпјҳдәәгҒЁгҒӢпјҷдәәгҒҢй–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮиў«е®іиҖ…еҒҙгҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгҒ«иҝ‘гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»®гҒ«гҒ“гҒ®е ұе‘ҠжӣёгҒҢжң¬зү©гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеҠ е®із”ҹеҫ’гҒ®дёӯгҒ«гҖҒиў«е®іиҖ…гҒ®иЁҖгҒ„еҲҶгӮ’иӘҚгӮҒгҒҹдәәзү©гҒҢгҒҠгӮҠпјҲгҒ—гҒӢгӮӮиӨҮж•°гҒ„гҒқгҒҶгҒ§гҒҷпјүгҖҒгҒқгӮҢгӮ’еӯҰж ЎеҒҙгҒҢзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҒқгҒ®еҫҢгҒ®еӯҰж ЎеҒҙгҒ®еҜҫеҝңгҒ«гҒҜйҮҚеӨ§гҒӘз–‘е•ҸгҒҢз”ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
еҠ е®із”ҹеҫ’гҒӢгӮүиҒһгҒҚеҸ–гҒЈгҒҹгҒҶгҒҲгҒ§дҪңжҲҗгҒ—гҒҹе ұе‘ҠжӣёгӮ’иў«е®іиҖ…еҒҙгҒ«дәӨд»ҳгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒЁжҳҺгӮүгҒӢгҒ«з•°гҒӘгӮӢгҖҒдәӢж…ӢгӮ’зҹ®е°ҸеҢ–гҒ—гҒҹеҶ…е®№гҒ®е ұе‘ҠгӮ’й«ҳйҮҺйҖЈгҒ«жҸҗеҮәгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒ—гҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеҠ е®із”ҹеҫ’гҒ®йҒ•жі•иЎҢзӮәд»ҘдёҠгҒ«гҖҒдәӢе®ҹгӮ’зҹ®е°ҸеҢ–гҒ—гҖҒиў«е®із”ҹеҫ’гӮ’ж•‘жёҲгҒӣгҒҡгҖҒй«ҳйҮҺйҖЈгҒ«иҷҡеҒҪе ұе‘ҠгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеӯҰж ЎеҒҙгҒ®е§ҝеӢўгҒ“гҒқгҒҢжҘөгӮҒгҒҰйҮҚеӨ§гҒӘе•ҸйЎҢгҒЁгҒ—гҒҰгӮҜгғӯгғјгӮәгӮўгғғгғ—гҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
зҸҫеңЁгҖҒеӯҰж ЎеҒҙгҒҜгҖҒиЎЁеҗ‘гҒҚгҖҒзӣЈзқЈгӮ’дәӨд»ЈгҒ•гҒӣгҒӨгҒӨгҖҒ第дёүиҖ…гҒ«гӮҲгӮӢиӘҝжҹ»гӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҒЁзҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҖҢ第дёүиҖ…гҖҚгҒ«гӮҲгӮӢиӘҝжҹ»гҒЁгҒҜгҖҒејҒиӯ·еЈ«дјҡгҒӘгҒ©гҒ®гҖҒеӯҰж ЎгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ„е…¬жӯЈдёӯз«ӢгҒӘ第дёүиҖ…гҒҢдё»е°ҺгҒҷгӮӢеҪўгҒ§гҒ®гҖҢ第дёүиҖ…委員дјҡгҖҚгҒ§гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“пјҲгҒ“гҒ®жүӢгҒ®дёҚзҘҘдәӢгҒ§гҒ„гҒӨгӮӮе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮӮгҒ—еәғйҷөй«ҳж ЎгҒҢгҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒ®з¬¬дёүиҖ…гҒҢеҪўгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒдәӢж…ӢгҒ®йҺ®йқҷеҢ–гҒ©гҒ“гӮҚгҒӢгҖҒиЈҸзӣ®гҒ«еҮәгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒ„гҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒ第дёүиҖ…委員дјҡгҒ«гӮҲгӮӢиӘҝжҹ»гҖҒжӨңиЁјгҒ®еҜҫиұЎгҒҜгҖҒиЎЁгҒ«еҮәгҒҹеҖӢгҖ…гҒ®дәӢ件гҒ®гҒҝгҒ§гҒҜдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®зөҢйҒҺгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒжң¬д»¶д»ҘеүҚгҒӢгӮүгҒ®жӮӘгҒ—гҒҚдјқзөұгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе®ҹж…ӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹиғҢжҷҜдәӢжғ…гӮӮиӘҝжҹ»еҜҫиұЎгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—пјҲе®ҹйҡӣгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®жҡҙеҠӣжЎҲ件гҒ®жғ…е ұгӮӮеҮәгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒжң¬д»¶гӮ’ж©ҹгҒ«жіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҹеәғйҷөй«ҳж ЎеҮәиә«гҒ®йҮ‘жң¬зҹҘжҶІж°ҸгҒ®и‘—жӣёгҒ§гӮӮгҒ«гҒҜгҖҒеҗҢж§ҳгҒ®гғӘгғігғҒгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹж—ЁгҒ®иЁҳиҝ°гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒеҪ“然гғЎгӮ№гӮ’е…ҘгӮҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖҒдәӢ件зҷәиҰҡеҫҢгҒ®жҢҮе°ҺиҖ…гӮ„еӯҰж ЎеҒҙгҒ®еҜҫеҝңгҒ®йҒ©еҗҰгӮӮиӘҝжҹ»гҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®зӮ№гҖҒиҫһйҖҖгҒ®йҡӣгҒ®ж Ўй•·гҒ®зҷәиЁҖгӮ„гҒқгҒ®еҫҢгҒ®еҜҫеҝңгӮ’гҒҝгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒжҷӮй–“зЁјгҒҺгӮ’гҒ—гҒҰеөҗгҒҢйҒҺгҒҺгӮӢгҒ®гӮ’еҫ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮӮиҰӢгҒҲгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе•ҸйЎҢгҒ®е…ҲйҖҒгӮҠгҖҒдёӯйҖ”еҚҠз«ҜгҒӘеҜҫеҝңгҒҜеәғйҷөй«ҳж ЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӯҰж ЎиҮӘдҪ“гҒ®еӯҳз¶ҡгҒҷгӮүеҚұгҒ¶гҒҫгӮҢгӮӢдәӢж…ӢгҒ«гҒҷгӮүгҒӘгӮҠгҒӢгҒӯгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӘгҒңгҒӘгӮүгҖҒй«ҳж ЎйҮҺзҗғгҒ®е…ЁеӣҪеӨ§дјҡгҒҜжҜҺе№ҙжҳҘгҒЁеӨҸгҒ«й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гҒҹгҒігҒ”гҒЁгҒ«гҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒҢи’ёгҒ—иҝ”гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒеәғйҷөй«ҳж ЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®гғҲгғјгӮҝгғ«гҒӘеҲ©зӣҠгҒЁзҸҫеңЁгҒ®дёҠеұӨйғЁгҖҒжҢҮе°ҺиҖ…гҒҹгҒЎгҒ®еҲ©зӣҠгҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮдёҖиҮҙгҒ—гҒӘгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®е…ҲгӮӮгҒ©гҒҶйҖІгӮҖгҒӢгҒҜдәҲж–ӯгӮ’иЁұгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеӨ§еұҖзҡ„гҒӘиҰӢең°гҒ§дәӢ件гҒ®иғҢжҷҜгӮӮеҗ«гӮҒгҒҹзңҹзӣёгҒҢеҫ№еә•зҡ„гҒ«жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ•гӮҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҲгҒқгӮҢгҒҢгҒ§гҒҚгҒҡгҒ«иЎ°йҖҖгҒ—гҒҹйҮҺзҗғеҗҚй–Җж ЎгҒ®дҫӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гӮӮгҒ—гҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒдёҖйғЁгҒ§иЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒҢеҒ¶зҷәзҡ„гҒӘдәӢиұЎгҒ§гҒӘгҒҸгҖҒйғЁеҶ…гҖҒеҜ®еҶ…гҒ§з№°гӮҠиҝ”гҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹжӮӘгҒ—гҒҚдјқзөұгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжҢҮе°ҺиҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҺійҮҚгҒӘеҮҰеҲҶгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒйҮҺзҗғйғЁгҒ®дј‘йғЁгӮ„е»ғйғЁгӮӮеҪ“然иҰ–йҮҺгҒ«е…ҘгӮҢгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒҢгҖҒеҫ№еә•гҒ—гҒҹзңҹзӣёи§ЈжҳҺгҒЁгҒЁгҒ“гҒЁгӮ“иҶҝгӮ’еҮәгҒ—еҲҮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҰҡжӮҹгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰдәӢж…ӢгҒ«иҮЁгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒеәғйҷөй«ҳж ЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰе”ҜдёҖгҒ®еҶҚз”ҹгҒёгҒ®йҒ“гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гҖҢиә«гӮ’жҚЁгҒҰгҒҰгҒ“гҒқжө®гҒӢгҒ¶зҖ¬гӮӮгҒӮгӮҢгҖҚгҒӘгҒ®гҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й•·гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒPartпј’гҒ«з¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ